■写真:『大学院レヴュー』プレゼンテーション風景(洋画コース院生)
-------------------------------------------------------------------------- 先日、教育改善活動(FD)プログラムの一環として教職員対象に開催された「少子化時代の大学運営」に関する講演を拝聴しました。講師は武蔵野美術大学の小井土満教授です。実は学生の頃、僕は教職課程で小井土先生のお世話になったのです。合評会でのコメントが抜群に面白いのと、研究室でコーヒー生豆を焙煎する(!)ことで有名な方でした。講義前に挨拶に行って「おー意外なところで会うねぇ」とがっちり握手、かれこれ10年ぶりの再会です。僕が教育機関で働いていることを、とても喜んでくださりました。 講演会では、80年代末から今日に至るまでの少子化の推移と、それに対応した武蔵美の学科編成およびカリキュラム改革の詳細について語られました。伝統あるかの大学でさえ教職員が一丸となって、少子化対策に年間100を超える会議を繰り返していると聞き、ちょっと驚きました。美大に限らず「全入学時代」(=大学進学を希望する高校生が「選り好み」さえしなければ、必ずどこかの大学に入学できるという時代)を目前に控え、全国の大学が熾烈な受験生獲得競争を繰り広げているのです。 東北では、私立大学の7割が、既に定員割れを起こしているそうです。幸い芸工大は入試課スタッフの営業努力もあり、まだ沢山の受験生のみなさんに支持されていますが、その絶対数は減っていく一方。しかも早稲田や立命館といった名門の総合大学が、美術学科の新設に着手していくという状況下にあって、本学のみならず、30年後も盤石な芸術系大学は殆どない、というのが偽らざる実情ではないでしょうか。国公立大学であっても、独立法人化を受けて、これまでのような安定とは無縁です。テレビタレントを教授にしたり、個性的な学科を新設したりと、美大生予備軍に向けたアピールに余念がありません。 高校生の理解レベルに「大学」運営の基準を合わせてしまうのもいかがなものかと思います。しかし、だからといって専門性の聖域に閉じこもっていてはどうにもなりません。情報化社会において、目まぐるしく変化する時代のニーズに呼応するセンスを身につけなければ、学内の研究・制作活動を保証する大学の経営そのものが傾いてしまうのですから・・・大学関係者には難しい時代ですね。 小井土先生は、魅力的なアトラクションをずらりと並べた大学のアミューズメント・パーク化を踏まえて、「全入学時代において、4年間の学部時代よりも、その次の段階の〈大学院・博士課程〉での学びが、これまでの〈大学〉に相当する高等専門教育に該当するでしょう」とおっしゃっていました。なるほど。学部の4年間が、ほぼ高校の延長上にあるのならば、受験生向けの「大学」広告と、制作・研究活動の高度化を並走させる鍵は、大学院教育の充実にかかっている、ということです。 *** 上の写真は本学大学院の授業風景です。「大学院レヴュー」といって、院生たちが、日頃の制作・研究の成果を学内各所にコンセプトシートとともに展示し、3日間にわたって、順次作品の前でのプレゼンをおこなっているのです。指導教官が進行役を務め、作者による10分程度のプレゼンの後、様々な学科コースの教授が、自由なスタンスで批評をしていきます。勿論、学生同士でも意見交換は活発におこなわれています。 はじめてレヴューに参加したとき「自分が院生だった頃にこんな機会があったらどんなによかったろう!」と思いました。コース内の講評会では、同じ領域だからこそ理解し合える微妙な差異にまつわる指摘に終始しがちで、クリエイションへの根本的な姿勢を問われたり、他メディアへの展開の可能性についてアドバイスをもらえる機会はあまりありませんから。 また、プレゼンには院生だけでなく他学年の学生たちが多く聴講しています。それはこの会が、蛸壺化しがちなアトリエ中心の生活において、自分のポジションを客観的に見極めることのできる、ある種の「モノサシ」のように作用しているからだと思います。 僕が受けた大学教育(油絵)は徹底的な放任主義でした。「どうせ100人中アーティストとしてやっていけるのは1人でるかでないかの世界だから」を常套句に、教授はほとんど何も語りませんでした。学外に出るしかない僕たち学生は、作品ファイルをギャラリストに売り込んだり、在野の批評家筋と交流したりして、かえって鍛えられはしましたが、やっぱり「大学院レヴュー」のように、大学がきちんとした批評の場を設定し、教員がまとまって指導している光景は羨ましく思います。 それぞれの専門領域における経験値を根拠にしながら、現代社会におけるアートやデザインのあり方を議論する知的な関係ないしは空間。大学院レヴューの真剣な集いのかたちに、「大学」本来の魅力を感じました。 全入学時代は大学にとって冬の時代には違いありませんが、日本の「大学」や「美術教育」の質を高め、存在価値を再構築する、いい契機なのかも知れません。 美術館大学構想室学芸員/宮本武典 |
■写真上:西雅秋氏の作品『彫刻風土・山形』のまわりで踊る舞踏家・森繁哉教授
■写真下:クライマックスで水上能舞台から池に飛び降りた森先生。この時、闇の中には学生スタッフが流木で木造船を叩く鈍い音が響き渡り、頭上には秋の名月がありました。 -------------------------------------------------------------------------- 一昨日、11月16日[木]をもって、7階ギャラリーの『西雅秋-彫刻風土-』展を終了しました。(本館1F周辺の展示は27日まで継続します) 西さんの作品は、サイズ、重量ともに大きな金属彫刻が中心のため、本学での滞在制作や展覧会設営には多くの困難が伴いましたが、大勢の学生スタッフに支えられ、タイトな準備日程ながら、当初の作品プランのスケール感を損なうことなく展示し、無事期間を全うすることができました。 本展運営にあたり、学生への周知や機材の貸し出しなどでご協力いただいた関係者の皆様には心より御礼申し上げます。ありがとうございました。 今、西さんは上海での『〈With Sword〉Contemporary Art Exhibition(http://www.jingart55.com)』参加のため、山形で制作したシリコン型とともに中国に滞在しています。現地では7Fで展示されていた『デスマッチ-山形-』の中国バージョンを制作しているとのこと。 会場の撤収にあたって西さんは、作品『デスマッチ・山形』や『バルチック・テイスト』で積み上げた数百個にもおよぶ石膏パーツを「皆で分け合って、持ち帰ってほしい」との伝言を残して山形を去られました。 その旨、掲示やメールで周知したところ、16日の夜には大勢の方が拾いに集まり、大学の同僚たちも『バルチック・テイスト』のテーブルから西さんがバルト海沿岸諸国で収集したレーニンやスターリン、マルクスの石膏胸像を持ち帰っていきましたが、これらが事務局のデスクに並んでいる景色を想像してちょっと心配になりました。(笑) 人々が石膏の瓦礫の中から、めいめい気に入った石膏片を大事そうに箱や紙袋に詰めていく姿を眺めながら、僕はミレーの『落穂拾い』や、熊谷守一の『焼き場の帰り』といった絵画作品とその絵の背後にあるストーリーについて考えていました。家々に散らばっていったこれらのカタチたちは、棚や、机の上や、引き出しの中で、ゆっくりと時間をかけて、石膏の欠片に、カタチなき存在に還っていくことでしょう。 『彫刻風土』展制作にかけた西さんとスタッフの一ヶ月間は、最後には、いくつかの小さなダンボール箱に収まってしまいました。 **** さて、もっとも大きな規模で展開した能舞台『伝統館』における西さんの彫刻作品についても、説明しておかなければ。 池に浮かぶ水上の舞台に、西さんが葉山の老漁師から譲り受けたという2艘の木造船(各5m)が置かれ、その中に石膏製の二宮金次郎像、卵、木魚、金精さま(木製の奉納男根)、砲弾、弁財天の頭、連座、梵鐘がたくさん積み上げられています。 オープン当初には整然と能舞台への渡り橋に並んでいたこれらの石膏像が、10月30日[月]の朝には、すべて木造船に暴力的といってもいい荒々しさで投げ込まれていたのですが、これは10月28日[土]の夕刻、『彫刻風土-時の溯上-』と題したパフォーマンスにおいて、西さんの彫刻と森繁哉教授の舞踏がコラボレーションした結果の景色なのです。 表現領域は違えど、里山に生き、その土地の風土と向き合いながら制作を続けるお二人の出会いは、今回のプログラムなかでももっともスリリングな空間を創出しました。 「西さんの作品は鑑賞するのではなく体感する作品だ。本番では観客席を排してお客さん自身も作品の中に取り込んでしまおう」という森繁哉教授の強い提案によって、公演当日は桟敷席を使用せず、133名の観客全員が「能舞台」に上がり、至近距離で西さんの彫刻と、森さんの舞踏の出会いに立ち合ったのでした。(公演の記録映像を、エントランス北側のプラズマテレビで27日まで放映しています) 頭からつま先まで真白な装いの森さんが舟から這い出して踊っていくにつれ、舟に満載された石膏像の白い小山は徐々に崩れていき、そのうちいくつかの欠片は、能舞台からこぼれ落ちて周囲の池に沈みました。路肩に積み上げられた小象ほどの山形の寝雪が、春の日差しを受けて徐々に溶け出し、路面を這って大地に染み入って消えていくように。 クライマックスでは、池に飛び込んだ森さんが、四国は足摺岬から黒潮に放たれた桂の大木(『colonist』の記録映像)に導かれるように、冷たい水の上をゆっくりと東へと進み、薄暮から漆黒へ、蔵王丘陵の夜の訪れとともに幕となりました。 大きな拍手とカーテンコール、感極まった西さんが森さんを抱えて石膏の中に一緒に倒れ込むというハプニングもありました。 この公演の前にこども劇場で開催されていたシンポジウム『神秘の樹と明日の鳥たち-詩・旅・思索-』で、1人の学生が「土地や風景から受ける神秘的な印象や体験を、どのように理解し消化すればいいのでしょうか」と質問したのに対して、詩人の吉増剛造氏が「イングランドには〈ghosty/ゴースティー〉っていう表現がある。的を得た、いい言葉だと思いませんか」と答えておられましたが、「奇跡のような一日」(※吉増氏談)となったこの夜の能舞台周辺は、まさに「Ghosty Night」と形容してもいい、この世の光景とは思えない場となっていました。 **** 石膏の粉に塗れていた7階ギャラリーでは、撤収と念入りなクリーニングによって元通り完全に〈empty〉な空間に戻り、今日からはまた、新しい展覧会『助手展2006』がはじまっています。飯能のアトリエに戻された彫刻群は、また土中に埋め戻され、次の展示機会までの束の間の眠りにつくことでしょう。 美の殿堂として名高いルーブルに展示されている名画や古代エジプトの彫像も、見方を変えると死者たちの視覚や触感の残像という、ある種の「幽霊的な存在」を眺めていると言えます。 そういう、近代以降の芸術作品や美術館における「永遠」の思想そのものに、批判的でいることが彫刻家・西雅秋氏の作品の本質なのだと、撤収を終えて、あらためて気付かされたのでした。 宮本武典/美術館大学構想室学芸員 |
■写真:土井ビルディング2Fの空き部屋で滞在制作中の後藤拓朗さん。壁紙を剥がして露出した板面に、鉛筆で直接にドローイングを施しています。(撮影:近藤浩平)
---------------------------------------------------------------------------- 開催まで2週間を切った今年の『I'm here.』。 ですが、現在7階ギャラリーで開催中の『SHINJO SAITO -一心觀佛-』展の京都巡回が突然に決まり、また、来月中旬に公開予定の肘折温泉郷での灯籠プロジェクト『ひじおりの灯』が、プランがまとまりきらないまま、連日マスコミに取り上げられてしまうなど、いつも通りの拡大展開への対応で、バタバタと慌ただしく準備が進んでいます。 今回の最大の特徴は、はじめての地元・山形での開催、さらに市内のギャラリーやカフェなど、7ヶ所を同時に結んでの展観にあり、アートスポットのガイドマップも兼ねた本展のポスター兼フライヤーも好評をいただいていますが、この17,000枚のB2判印刷用紙は、全て地元企業の田宮印刷株式会社さんからの提供で賄うなど、地域との連携がよりクローズアップされてきたかたちです。 これまで仙台で開催していた『I'm here.』シリーズですが、地元に帰ったとたん、盛り上がりと反響が違うことに驚きました。この企画も、土地の力を借りる事で年々拡大+進化を続けているようです。 昨晩は、レセプションパーティー(7/7)を担当するプロダクトデザイナー集団『Link』と、パーティーで提供する「地産地消」をテーマにしたオリジナルフードについて夜遅くまでミーティングをしていましたし、他にも、日本の若手アーティストを取り巻く現状について、アートライターの白坂ゆりさんを招いての開催するディスカッション(7/8)開催など、昨年度の卒展テーマ『OUR ART. OUR SITE.』と『I'm here.』を混合させながら、ここ東北だからこそ可能なアートシーン創造に挑戦していきます。 詳細は既に〈Information〉で公開されていますので、ぜひチェックしてください。 ***** 参加する作家たちの中でも、駅前のすずらん通り沿いにあるギャラリー『ぎゃるり葦』さんの協力で、「住み込み制作」を続けている後藤拓朗さんは、本展タイトル『根の街へ』をそのまま体現するような、コンセプチャルかつ美しい作品を描いてくれています。 古いビルの壁に、徹底的に書き込まれた鉛筆画のタイトルは『共同体(仮設)』。 展覧会が終了すれば店舗工事が入り、全て塗りつぶされてしまう運命にあるこの作品は、既に本展のポスターを飾り、全国の美術館やギャラリーの壁に「移設」されていますが、上記の写真を見ての通り、まだまだ増殖中。 ぜひ夏の山形で、彼のたった一人のプロジェクトに立ち合ってみてください。 宮本武典/美術館大学構想室学芸員 |
■写真上:岩本あきかずさんの作品ブースでのトーク風景。左から、私・宮本、橋本ダイスケさん、小林和彦さん、坂田啓一郎さん、岩本あきかずさん、鈴木伸さん、山崎環さん。
■写真下:舞踏家・森繁哉氏(東北文化研究センター教授)によるパフォーマンス。『カフカ・掟の門』と題した即興的な舞踏を、坂田さんの彫刻作品の周りで踊りました。 -------------------------------------------------------------------------- 先週末の土曜日に『I'm here.2006』展のレセプションが開催され、午後2:00からのギャラリー・トークおよびダンスパフォーマンスのプログラムには、教職員、卒業生、在学生の他、仙台美術研究所の生徒さんたちなど、約150名の関係者が集まり、若いアーティストをとりまく環境について語り合いました。 内容の詳細は、追ってレポートいたします。取り急ぎ、写真のみUPしておきます。 |
(※写真をクリックすると拡大画面で見られます)
■写真上:ギャラリー絵遊で松岡圭介作品『a standing man』を鑑賞するグラフィックコース准教授の坂東慶一先生とアートライターの白坂ゆりさん。 ■写真中:馬見ヶ崎川沿いのカフェで観客参加型のインスタレーション『1984-espresso』を鑑賞。制作した大学院生たちとの対話。 ■写真下:7月8日に蔵を改造したカフェ『灯蔵 オビハチ』で開催された2人よるレクチャー『仕事はつくるもの』。立ち見が出るほど大勢の学生が詰めかけた。スクリーンに映し出されているのは、白坂さんがいまもっとも注目している作家の一人、ベルリン在住のアーティスト小金沢健人氏の作品。 ---------------------------------------------------------------------------------- 山形市内で開催した『I'm here.07-根の街へ-』に、ゲストとしてお招きしたアートライターの白坂ゆりさんが、トータルアートサイト『LOAPS』の連載コラムにて、本展の様子を紹介してくださいました。 『白坂ゆり トウキョウアートリズム』=http://www.loaps.com/art+index.id+hp.htm 坂東慶一准教授との対談『仕事はつくるもの』では、白坂さんが情報誌『ぴあ』のライターとして、90年代から今日まで、「観て・書いて・立ち合って」きたアート発生の現場を、豊富な写真資料とともに証言してくださいました。 また、ロンドン、アムステルダムと欧州を拠点にデザイナーとして活動してきた坂東准教授は、日本のオルタナスペースの草分け『スタジオ食堂』での自らの実践を示しつつ、自治体や企業の助成を得ながら、地域住民と連携して展開した伝説的な『スタ食』のクリエイティブなコミュニケーション・スキルについて丁寧にレクチャーしてくださいました。 2007現在。日本の有力ギャラリーはグローバルなビジネスに乗り出し、所属アーティストのマネジメントや、若手の発掘に意欲的です。美大の卒業制作展に多くのギャラリストたちが訪れるようになり、フレッシュな才能が銀座の貸画廊システムを飛び越してチャンスをつかんでいます。 アーティスト側にも、こうした市場のニーズからこぼれ落ちないように、積極的に売り込んでいくセルフ・プロデュース能力が問われています。 後半、会場からの質問を交えたディスカッションは、昨今見られるようになったギャラリーやメディア、時には大学が連携して「今、売れる作家」を量産していくシステムのあり方や、ギャラリストと作家との複雑な駆け引きについてなど、アート業界のリアルな体験談で盛り上がりましたが、最後の締くくりの白坂さんの発言が良かった。 「今、アートシーンで何が起こっているのかを知ることは大切ですが、どのギャラリーが有力だとか、欧州のトレンドがどうこうといった〈情報〉に、アーティストの作品や制作は左右されるべきではないと思います。アート作品自体の魅力も同様に。」 90年代とは明らかに異なる「実感なき好景気」の中で、ビックメゾンや広告業界を巻き込んで流通していくアートマネーの恩恵。これらを、ただ盲目的に甘受しようとするのではなく、現実の生活を取り巻く様々な環境と、内省的な制作活動の幸福な一致のために、インディペンデントに生きていく術を模索する…。 途中、白坂さんが紹介してくれた、東京のネオンサインをモチーフにしたベルリン在住のアーティスト・小金沢健人氏のユーモアかつリリカルな映像は、日常にありふれた現象を、視線や解釈のズレによって、説明しようがない心地よい調和へと変換していました。 あの映像のアノニマスな美しさは、「アーティストとしての成功」だけを求めて制作していく態度とは根本的にベクトルの異なる眼差しでもって、アートへの真摯で純粋な「trial and error(試行錯誤)」を、若いアーティストたちに求めたいとする、この日のレクチャーに臨んだ2人のポリシーが端的に表現されていたように思います。 美術館大学構想室学芸員/宮本武典 |
(※画像をクリックすると拡大画面で見られます)
■写真上:7月7日に、『ギャラリー絵遊』+『蔵大マス』の庭で開催された、『I'm here. 2006』のレセプションパーティーの幕開けです。写真は乾杯の様子。左から松本哲男学長、ギャラリー絵遊オーナーの駒谷氏、そして、フライヤー17,000枚分の印刷用紙を無償提供していただいた田宮印刷株式会社の工藤社長。祝杯は工藤社長から差し入れていただいた高級ジャンパンで景気良く。 ■写真中上:『Link』プロデュースのベーグルパーティーに、強力助っ人として参加していただいたCafe Espressoの高橋昌平マスター(左)。高橋さんからベーグルにチーズを挟んでもらっているのは、『ぎゃるり葦』オーナーの土井忠夫さん。今回は後藤+池谷+阿部の洋画出身のペインター3人組がお世話になりました。『I'm here.2007』で、もっともパワフルだったのは、間違いなくこのお2人でした。 ■写真中下:芸工大の在学生・卒業生にとって何でも相談できる「お母さん」的存在の大学職員の方々。手前左から学生課の小林さん、原田さん。中央奥は図書館の谷川さん。この日はパーティーの仕込みに主婦パワーを発揮しつつ、大勢集まった卒業生たちと久しぶりの再会を喜び、そして『Link』プロデュースのオリジナルベーグルサンドを頬張る。息子の手料理を味わう気分? ■写真下:梅雨の奇跡的な晴れ間。夕方からスタートしたパーティーは、真っ暗になっても立ち去り難く、結局夜の9時過ぎまで続きました。参加者は300名を超えました。 (撮影:加藤芳彦) ---------------------------------------------------------------------------------- 正直に告白すると、昨年の暮れに、今年の『I'm here.』の開催日時を決めた段階では、頭の中から「日本の梅雨」の存在がすっかり抜け落ちていたのです。 『ギャラリー絵遊』さんの手入れの行きとどいた庭を見た時、「これだ!」と直感的にひらめいたガーデンパーティーのアイデアでしたが、日時をフライヤーに刷り込み、卒業生約4,000人に送付し、いよいよその詳細を詰めていこうとしたところで、山形市内の雲行きが連日おかしくなり、地元出身の職員から「山形の七夕は晴れたことがない」と困惑げに聞かされ…た時すでに遅し。 パーティーのプロデュースをお願いした『Link』のメンバーと、ハラハラしながらyahoo!の天気欄をチェックする日が続いたのですが、あえて雨天の代替え案はなし! と背水の陣で準備を進めたところ、関係者の日頃のおこないが宜しいのか(?)ずっと雨続きの『I'm here.』展の会期中、不思議とパーティーと翌日のトークイベントは天気に恵まれました。 18:30パーティー開始の30分前から、続々と卒業生+在校生が集まり、松本学長の豪快なシャンパンオープンが、夕方の空にコルクの弧を描き、パーティーの幕開けを告げると、『Link』が用意した250食分のベーグルは次々と無くなっていきました。(なかには4つ食べた学生も!) この日のために、『Link』メンバーが考案したオリジナルベーグルは、地元で人気のベーカリー『シャルマン』に焼いてもらった品で、生地に山形の「だだちゃ豆」「山ぶどう原液」「県産トマト」を練り込んだ特別なもの。 ボランティアスタッフの女子学生が、包丁とまな板持参で集まり、お昼過ぎから2/1スライスし続けたベーグルに、参加者がおのおのテーブルに並べられた食材をサンドして食べるという趣向。パーティーのコンセプトをオリジナルスタンプに仕立てて捺した紙に、色とりどりのベーグルに挟んで食材を乗せれば、無駄な食器やカトラリーは使わなくていいというエコなパーティーなのでした。 大きなテーブルに所狭しと並べられた各種の具材は、これまた山形産にこだわり、ギャラリーのすぐ隣にある『佐藤牛肉店』からは「米沢牛コロッケ」(※写真上の看板に注目)や特選サラミをフューチャーし、通り沿いにある豆腐店からは「豆腐ハンバーグ」をセレクト(「塩気と効かせて」と特別オーダー)。これらは余計な包装をせず、お店からトレイごとドサッと届きました。 この他、『Cafe Espresso』高橋マスター手づくりのサクランボのジャムや、本格チーズ、県産の瑞々しい野菜たちが、『Link』メンバーデザインによる有田焼の皿にレイアウトされます。 ドリンクも、大学内ではないので堂々とお酒が並びます。高畠のスパークリングワインに出羽桜の吟醸酒。アルコールNGの未成年には、県産フルーツの濃厚なジュースが振舞われました。 様々な「味」を組み合せる楽しさ。パーティーを通して交流する在学生と卒業生。地元にある様々な美味しいものとの出会い。そして、「食」と「デザイン」の融合が演出するピースフルな空間と交流。『Link』のねらいは見事的中し、パーティーは大成功でした。 会の途中で『I'm here.2007』参加作家や各ギャラリーのオーナーさんたちによるマイクパフォーマンスも会場をおおいに盛り上げましたが、たくさんのお酒にも関わらず、だらしない酔っぱらいは一人も出ず、終始なごやかな会話がざわめく大人の雰囲気ただようパーティーでした。本当に。 こういうリラックスした、さりげないクリエイトが、参加者に与える創造的な刺激ははかり知れません。 ただ酔っぱらうための安っぽいフランチャイズの居酒屋ではなくて、街の歴史を感じさせる場所に手づくリのテーブルを囲んで、ささやかな食べ物を持ち寄って。 世代をこえて楽しく語らった、家族のような親密な時間でした。 これが伝統になればいいなぁ。毎年、七夕の夜が晴れるかどうかは怪しいのですが。 宮本武典/美術館大学構想室学芸員 |
■写真上:描きはじめる前の真成師の講話。美しい夕日の射し込む7Fギャラリーには、300名を超える観客が集まり、なかには庄内地方や東京や、はるばる京都から駆けつけた熱心なファンの姿も。
■写真中:1時間に及んだ制作の様子は、作品とともにモニターで展示した。 ■写真下:学生たちの目の前で、大判の鳥の子紙に綴られた文人画風の作品『念佛注語』。 (※写真をクリックすると拡大画面で見られます) --------------------------------------------------------------------------------- 洋画コース主催で、美術館大学構想室が会場構成を手がけた齋藤真成師の展覧会『一心觀佛』が、先日、盛況のもと無事終了しています。ここで初日の6/13夕刻に、展示会場で開催された講話と公開制作『紙に点を置くところから』の写真をアップしておきます。 この小企画は洋画コースの課外授業の一環として有志学生により実施・運営され、設営作業から会場管理(受付/監視/解説)まで、すべて学生が自主的に取り組みました。 その過程で、90歳とはとても思えない、真成先生の軽妙かつ品のある人柄に魅せられた学生たち(多くは女子学生)は、公開制作終了後に老画家を取り巻いて、延々たる悩み相談(中には涙を浮かべていた学生も!)+ケータイで記念写真。 疲れていたはずの真成先生も、「ほんまに近ごろはよう見かけん、素朴でかわいらしい子らやなぁ」と、穏やかな笑みを浮かべつつ、実に丁寧に対応してくださいました。 (その時の、実にユーモアとペーソスに溢れた問答はまたの機会に紹介します) 年金問題や孤独死、少子化・過疎化などなど、「老い」のネガティブなイメージが先行するこの社会で、天台宗の僧として厳しい修行を積みながら、半世紀以上も静かに描き続けてきた老画家の、品のある「軽み」と「まるみ」は、苦しく漠然とした「自分探し」としてでしか、自らの作品制作の理由を咀嚼できない多くの若い学生たちに、不断の制作や思索によってもたらされる、ある種の「格式」の在処を知らしめたのではないかと思います。 人生は長い。芸術の道も同じ。 詩でも書でも、画においても、東洋における芸術の伝統は、老齢に至って真の深まりに到達する道を重んじてきましたが、近頃のアートシーンは若い作家にすぐに結果を求めがちで、みなシーンから切り捨てられないようにと必死です。あえて斜に構えて独自の「回り道」を楽しもうとするような余裕が失われている気がします。 マーケッティング、セルフプロデュース、…そんなことは広告代理店に任せておけばいいじゃないですか。 無理せず、無駄な雑音に耳を塞ぎ、ゆっくり淡々と、己の芸術世界の確立を目指して進みたいのですが、学生も、僕も、ついついオーバーワーク気味(この大学も?)です。余分なところに汗をかいている気がします。 短い期間でしたし、あくまで「お手伝い」的なキュレイションだったので、はじめは心情的にあまり全力投球できなかったのですが、それがかえって今の自分を自然体に見つめ直すいいタイミングとなりました。アートの意外な、いや本来の効用でしょうか? 京都風に言うと「はんなり」な、いや「おかげさん」な出会いのある展覧会でした。 宮本武典/美術館大学構想室学芸員 |
写真上:富田俊明ワークショップ「『二重体』、『泉の話』を読む」
写真下:舞踏+ポエトリーリーディングの会/森繁哉×富田俊明 先月開催された富田俊明さんによる上記2つのイベントについて、工芸コース3年の竹田佳代さんと、洋画研究生で美術館大学構想室スタッフの後藤拓朗君がレポートにまとめてくれました。 読んでみると、彼らにとって、深い内省と対話の契機となっていたことが分かります。 この企画、その閉ざされた濃密さ故に、立ち会えた人たちは決して多くなかったですので、彼らのレポートからその場の雰囲気を読み取ってもらえたら幸いです。 「アーカイブ」中、富田展ページの2ページ目に掲載しています。 宮本武典(美術館大学構想室学芸員) |
■写真上:和太守卑良の展示ブース。花器と生け花の即興的なコラボレーション。
■写真下:金子透による鍛造の手桶には小原流によりオーガスタのドライフラワーが生けられた。 24日土曜日、鶴岡アートフォーラムで、工芸コース教員の作品を中心にした作品展『作座考-BANDED BLUE2-』がオープンしました。 私宮本が企画コーディネートを手がけた本展では、「座」をキーワードに、陶芸・金工・漆芸・木工の各領域を、茶室に見立てたヒューマンスケールのブースに点在、干渉させる空間構成を試みました。 会場造作の設計を建築家集団「みかんぐみ」の竹内昌義助教授にお願いし、本学教授陣の花器に小原流師範・三橋光彩氏が生け込みをおこなうという贅沢な展観は、古き良き伝統文化が息づく城下町・鶴岡のつつましい佇まいに、上質な現代性・先鋭性を加えることに成功したと自負しています。 また、会場には、各参加作家が制作した茶道具を組み合わせた「茶室」のコラボレーションや、制作行程を紹介する映像インスタレーションなどもあり、現代工芸の多様な可能性を示すものとなっています。 山形からはまだ雪を冠った月山を越え、約2時間の道のりとなりますが、ぜひ足を運んでみてください。 美術館大学構想室学芸員/宮本武典 |
■写真上:出品作家および展覧会スタッフ
左から、和太教授(陶芸)、降旗教授(プロダクト)、尾崎くん(竹内研の院生)、酒井さん(構想室スタッフ)、加藤事務長(構想室)、竹内助教授(建築)、宮本学芸員(構想室)、佐々木講師(陶芸)、小林教授(漆芸)、金子助教授(金工)、水上助教授(漆芸) ■写真下:内覧会直前の会場風景 佐々木理知作品ブースから金子透ブース(右奥)と降旗英史ブース(中央奥)を眺める ----------------------------------------------------------------------------------- 前回に引き続き『作座考-BANDED BLUE2・東北芸術工科大学の7作家-』展の様子をお伝えします。 写真は内覧会直前に展示作業を終え、ホッとした関係者一同。 囲んでいるのは、畳代にエンコ板を張った、竹内助教授デザインの特注台で、出品作家がそれぞれに自作の茶道具を持ち寄り展示しました。 なお、ここには写っていませんが、鶴岡側の学芸部のお2人・那須孝幸さん、山岸早苗さんをはじめ、アートフォーラムの皆さんのきめ細やかなサポートをいただきました。 山岸さんは本学美術史・文化財保存修復学科の卒業生です。 上下とも法人本部の中嶋健治さんの撮影。 |
■写真上:朝日町立旧立木小学校の教室で発表された西さんの作品『余韻』は、本学建築学科生との共同制作となりました。撮影の視点が高いのは、廊下側に朝礼台が置かれ、来場者はその上に乗って、教室の高い窓から俯瞰して眺めるという設定ため。扉の閉ざされた教室の中では2人の学生がダイアローグ形式でおのおのの家族や学校にまつわる記憶の物語を、教室の床に石膏でトレースしていました。
■写真中:隣の教室では石膏の鋳込み作業を継続中。原型となるのは、朝日町のワインや林檎、冬瓜、この廃校に残されていた郷土玩具など。石膏に写し取られた「朝日町のカタチ」は、隣の教室に運ばれ、記憶の断片に組み込まれていく。 ■写真下:廊下には西さんの棲む里山(埼玉県飯能市)で同様に廃校になった小学校におかれていた二宮金次郎像が佇んでいました。台座には古い鉄製の金庫が使われています。 -------------------------------------------------------------------------- 大地に落下した『CASTING IRON』が朝日町立木地区を賑していた一方で、旧立木小学校の校舎の中では、西雅秋さんと本学建築・環境デザイン学科生との共同制作による展覧会『彫刻風土-ASAHIMACHI'06-』が静かにオープンしていました。 学生たちと西さんが連夜の話し合いの末、生み出した作品は『余韻』。これは、オープン・スタジオ形式をとり、参加した学生一人一人が「家族・学校・記憶」の語り部となり、石膏のフィギアを用いて自らの物語を、円の中で「箱庭」のように客体化していく、というものです。 けれども、その小さな石膏像による箱庭は、次の語り部に移る前に取り外され、後には置かれていた「カタチ」の関係図が、失われた記憶の影のように、雪の模した石膏の粉によって教室の床にトレースされていきます。 取り去られていない石膏像は、語り部が「失ってしまいたくない」としてあえて残したもの。語りの内容は黒板に詳細に記述されていきますが、そのはじまりに西さんは「円の中心には、決してかえることはできない」と、くっきりと書いていました。 山形の展示会場では骨のような、軽く、鋭利な印象だった石膏は、ここではふわりと軽く、柔らかく空間に積もっていて、西さんは「何だか少し女性的で自分の作品じゃないみたいだ」と語っていましたが、廃校の教室で眺めるこの作品は、どこか哀しく、美しく、僕はとても好きでした。 作品は10月29日から雪が降り始める今月後半(11/27)まで展示されています。紅葉狩りを兼ねて、是非、朝日町立立木小学校を訪ねて、作品『余韻』の成り行きを見届けてください。 宮本武典/美術館大学構想室学芸員 (アクセスに関して詳しくは→http://www.tuad.ac.jp/asahi-a-gakko/) |
写真上:山形で採集したカタチが石膏に鋳抜かれ、藁籠に盛られている。
写真下:宴の後。参加した人々のカタルシスが白い粉となって作品に定着した。 -------------------------------------------------------------------------- 11月5日日曜の早朝。既に山形からの帰路・東北道を走っている筈の西雅秋さんから思いがけず電話が入り「ちょっと窓から顔を出してみなよ」との呼びかけに応じて3階の部屋から慌てて視線を落としてみると、そこには一緒に山形じゅうを駆け巡ったダットラと、缶コーヒー片手に、いたずらっぽく笑う彫刻家の姿がありました。 紅葉燃え立つ朝日町旧立木小学校でのオープン・スタジオ終了後は、山形市には寄らずに、まっすぐ飯能の工房に帰る予定を遠回りし、西さんは妊娠後あまり経過のよくなかった家内の具合を心配して、大学近くの僕のマンションに来てくれたのです。 そして、かの地では地元の猟師さんたちとの連日の交歓で、熊や鹿、キジや猪、果てはダチョウまで、野趣に富んだ肉ばかリ食べさせられて腹の調子が悪いよと語りつつ、活力あふれる声で、弱気になっていた僕たち夫婦を励ましてくれたのでした。(家内と西さんの息子さんは、偶然にも同じ大学、同じ学科の同級生なのでした) *** 彫刻家・西雅秋さんをお迎えして、連日100名を越える観客とともに進行した『西雅秋-彫刻風土-』展にまつわるプログラムも、彫刻家の次なるプロジェクト(11/19〜上海)への旅立ちとともに、熱を失ってしまいました。 けれども7階ギャラリーには彫刻家の格闘の残骸が散らばり、能舞台には2艘の舟が座礁し、朝日町の廃校には白い輪と、地表に沈み込んだ5tの鉄塊が、そこで何がおこなわれたのかを静かに語っています。 彫刻家が去っても、これらの遺物を頼りに、彼がこの地で何を造り、壊していったのか、そのアクションを想像することはできます。 10月24日から10月29日にかけて、西さんが用意したいくつかの神話的な光景に、毎回多くの人々が立ち合いましたが、この大学の総学生数は2000人です。目撃することにできなかった多くの学生諸君の為に、これより4回に分けて、このブログで補足説明をしていきたいと思います。 *** 上の写真は10月24日夜に7階ギャラリーでおこなわれた非公開パフォーマンスです。山形での西さんの制作をサポートした学生・教職員約60名が、「彫刻の宴」に招かれ、作品『デスマッチ・山形』の「最後の仕上げ」に参加しました。 かつて養蚕に使われた藁の平籠に、西さんが山形滞在中に収集した野菜や果実、郷土玩具や、仏像やコケシ、金精様など信仰の造形が石膏で鋳抜かれ、「カタチ」に込められたさまざまな意味が渾然一体となって積み上げられています。 まるで巨大な亀の甲羅に盛られた古代インドの世界観のような、神聖さとキッチュさの共存する不思議な塚が7つ、ギャラリーの床に築かれ、招待客がそのまわりに円座を組みました。 西さんの「乾杯!」の合図とともに山盛りの石膏が次々と砕かれていきます。 歓声と、耳をつんざく破壊音が5分間響き渡って、再び西さんの「終わり!」との掛声が響き、一同が拍手のともに退場すると、その後には粉々になった石膏片が、恐いくらい静かな緊張感を、白い澱のように空間にたなびかせていました。 永遠に属する彫刻ではなく、一瞬の魂の高まりに懸ける「彫刻」への熱狂。 駅前や公園に立つ、厳めしい政治家の銅像や、ぬるりとした裸婦像や、金ぴかのモニュメントにおける「彫刻」とは明らかに異質で、むしろ伊勢神宮や、沖縄の御嶽、竜安寺の石庭にも通じる「なにも置かない」ことをギリギリまで研ぎすました、この国の文化でもっとも上質な地霊(ゲロウス・ニキ)へのアプローチを感じました。 彫刻家としては異端な、その感性が存分に発揮された、西さんによる初日のイベントでした。 その後は宮島達男副学長が(本物の)一升瓶を差し入れてくださり、しみじみと乾杯。秘密の宴は、その夜遅くまで。 宮本武典/美術館大学構想室学芸員 |
■写真:『Eden』1999年/宮本武典(武蔵野美術大学大学院修了制作)
液晶プロジェクター映像、曲げ木椅子、髪の毛、ガラス etc. 武蔵野美術大学美術資料図書館写真スタジオでのインスタレーション風景 --------------------------------------------------------------------------- 卒業修了制作展のコーディネートを、美術館大学構想室が担当することになりました。そして今、芸工大ではこの「卒展」のあり方について議論が巻き起こっています。 これまで東北芸術工科大学では、卒展会場をキャンパス内だけでなく、山形美術館(日本画/洋画/工芸/彫刻/写真の展示)や、市内の映画館『ミューズ』(映像)に分散させて開催してきました。それを、今年度からキャンパス会場で一本化するという改革を、松本学長が提案されたのです。 大学内のギャラリーや劇場を活用するだけでなく、学内の一部のアトリエやラボも展示空間にリノベーションして、「制作の現場」を「公開・交流の場」に改造していく。それは、借り物の「箱」に収めるのではなく、制作現場の熱気を感じながら、その成果を来場者に見ていただこうというものです。 もちろん、提案の背景には、定員増による従来の卒展展示スペースの不足や、会場の分散化による鑑賞導線の困難さなど、様々な現実的な要因があるのですが、一番大きなコンセプトは、卒展を東北から発信するアートとデザインの「展覧会」として、メッセージ性のある、魅力あるものにしたいという思いです。 昨年夏、松本哲男学長はベネチア・ビエンナーレの視察に出られました。 ベネチアでは「アルセナーレ」と呼ばれる赤煉瓦の造船所群が展示会場として利用されていました。過ぎ去った大航海時代の記憶を留める古びた空間に、新しいアートが、新しい世界からのメッセージを運んできていました。 僕も同行しましたが、公園内に林立する各国のパピリオンを、炎天下をものともせず、誰よりも熱心に見て回っていたのが松本学長でしたね。(ただし、ビール片手に)海の上に浮かぶ小さな都市・ベニスに、点在するアート・パピリオンを巡りあるく行為は、あたかも世界とリンクする自らの「声」を聞いて回る、内省の旅のように感じられたものでした。 山形の僕は、「新しい卒展」担当者の一人として、様々な立場の、様々な視点からのヒヤリングに奔走している毎日を送っていますが、松本哲男学長をはじめ、執行部の先生方の、新しい卒展創造にかける意欲は、確実に大学を活性化していると感じています。サポートする僕たち大学スタッフは「卒展とは何か? 」の根本を問う一連の試行錯誤の果てを、クオリティーの高い展覧会として結晶させねばなりません。 今年もオフィスで迎える朝が多くなりそうです。 *** 上の写真は宮本自身の懐かしの作品『Eden』の会場風景です。 大学院の修了制作として発表したこのインスタレーションも、キャンパス内のデットスペースを活用した展示でした。 民族研究室でアルバイトしていた僕は、民具の倉庫として使われていた美術資料図書館内の写真スタジオを作業中に偶然「発見」し、現状復帰とスタジオ内の整理清掃を条件に、展示空間として使わせてもらったのでした。ほとんどの学生たちが足を踏み入れたことのない、大昔のスタジオ器材の墓場のようなこの部屋は、見方によってはハードなコンクリート壁と完全暗転が、映像のプレゼンテーションには最適でした。 友人たちに手伝ってもらいながら、1週間かけて山のような民具を移動し、十数年分の分厚い埃を拭き清め、重たい撮影機材を整理しました。それから油絵学科のモチーフ室に交渉して、モデルポーズ用にコレクションされていたヨーロッパ製の古い曲げ木椅子を大量に運び込み、仮設の劇場をスタジオ内に組み上げました。照明機材はスタジオのものをそのまま流用し、ダンサーやミュージシャン、映像作家に協力してもらってパフォーマンスを映像と組み合わせたインスタレーションとしました。 展示施設として「発見/発掘」された地下墳墓のようなこの「忘れられたスタジオ」は、今では後輩たちの重要な展示会場として卒展やその他の企画展会場に運用されているようです。 美術館大学構想室/宮本武典 |
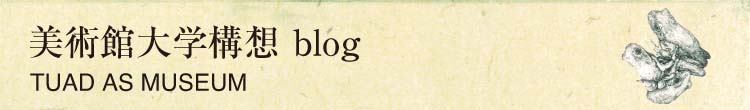



















■写真上:大勢の来館者が行き交うInformation Passage(情報回廊)でのライブ中継。
■写真中:総勢18名のカメラクルーがLANケーブル+PC +WEBカメラのセットで移動し続けた。
■写真下:523名へのインタビューは2名の美術科1年生・新津さん+諸岡さんが務めた。事前に各学科コースの特性や卒展までの取り組みに関する取材+勉強会を繰り返して本番に臨む真摯な姿勢に拍手。この企画の詳細は卒展ディレクターズHPで=http://gs.tuad.ac.jp/directors/index.php
----------------------------------------------------------------------------------
学生時代に読んだ武満徹のエッセイに、「ベートーベンの音楽は巨大な蛸」とのユニークな喩えがありました。長く太いたくさんの足で、いくつもの吸盤で、聴衆を圧倒し巻き込もうとする、渦のような音楽。その中心には、作曲家の強烈な存在感があります。
対して武満は、エリック・サティの曲を、聴くものの中に、それぞれの心の情景を喚起させるものだと語っています。聴者の感性を楽曲によって圧倒し、支配するのではなく、聴者自身の感受性を、密やかに導き出すものとして評価しています。
とりわけピアニスト・高橋悠治氏の弾くサティは、僕にとって特別な音楽です。そのメロディーは、日常の営みに漂っている密やかな何か、生にとって大切なものへの気付きを、今、自分が過ごしている部屋の情景から、導き出してくれるような気がします。
この感覚は、絵画ならポロックよりもサイ・トゥンブリ、ピカソよりもモランディ。見る人の内省の中で発生する光やリズムを感じさせてくれる筆致への共感に近いものです。世に名作と呼ばれる芸術作品と対峙する時、僕はいつも、この対比を思い出しています。それが巨大な蛸なのか、それとも僕自身の感動なのかを。
****
卒展の期間中、本館1FのInformation Passageで放映されていたクリエイターズ・マイクは、サティの音楽のように、若い人たちのエネルギーへの、共感の姿勢を、訪れた大勢の方々の心情に喚起させていたように思いました。運営に携わった卒展ディレクターズのスタッフ18名は、523名をつなげていかなければならないという意識で、人と情報とシステムの、有機的で合理的な運動を見事に走り切りました。
マイクを向けられたインタビュイーは、自分自身を語っているのに、数百人の語りがその背後で一体となって、ザワザワと常に穏やかにつながっているように思えたのです。
映像メディアを媒体として、語ること。聞き出すこと。耳を澄ますこと。すべてを等価に扱うこと。等価のなかで差異を際立たせること。空間に声を反響させること。それら全体が一つの風景として伝わっていくこと。それが出会いを媒介していくこと…
(彼らがキャンパス全体を駆け巡って奏でた声と映像は、中継システム上の制約もあり、決してクリアではなかったので、本館を行き交う人々は映像内の彼・彼女と出会いたいのなら、足を止めて注視することが必要でした。ここでの情報は、人々を積極的に支配しない。声高に叫ばない。反応を強要しない。)
あくまで出品者一人一人に丁寧に対応し、気がつくとそれらは空間や観客やスタッフ自身も巻き込んだ大きな円環に帰結していく。この運動の結末に、スタッフ自身が大きな感動と充足感を感じていたようでした。
****
同じく卒展期間中に各会場を巡回したギャラリートーク企画「カフェ@ラボ」においても、同様のコンセプトを設定しました。同じパッケージのなかで、多様性は多様性のまま、自由に批評を展開していきます。熱心な観者は、それぞれの言説のなかにある、「大学」や「教育」や「東北」にまつわる、ある共通の視点・提言・問題意識に気が付く。これが、同時代性の発見、世界とのリンクなのだと思います。
差異を認め合いつつ、つながってつながって、それがひとつの運動となって全体を共鳴させていく。音楽の喜びに似た、和音の感覚。
美術館大学構想室学芸員/宮本武典