展評
写真上:「CASTING IRON-ASAHIMACHI06-」の記録。5tの鉄が落下する瞬間。
写真中:落下直後、地面に沈み込んだ鋳鉄のまわりに集まる人々。 写真下:人々のざわめきが去った後、鉄は静かに校舎を背にして秋の広場に佇む。 -------------------------------------------------------------------------- 5tの鉄塊が空から大地へ舞い降りた日、10月29日・日曜は西雅秋さん60歳(還暦!)の誕生日でした。 西さんは「日本では人間は60歳を過ぎるともう一度子どもに還るんだ」といってこの大胆な作品『CASTING IRON』の公開設置におおいに意欲的で、かの5tの鉄塊は、林檎とワインで有名な山形県朝日町の小さな廃校で、彫刻家の無邪気な「生まれ変わりの儀」を祝うために、福井県金津市の公園から掘り出され、140名の人々に見守る中、苔むした雪国のグラウンドに着地しました。 この日は午前中から25tクレーンがけたたましい音を立てて鉄板を敷いたり、続々と車で乗りつけてくる学生たちがグランドで童心にかえり、奇声をあげて走り回ったりして、普段は静かな地区は非日常の喧騒に包まれましたが、「何事か」と散歩ついでに様子を見に来るお年寄りの皆さんは意外に好意的で、あるお婆さんは、僕と西さんが「すみません、今日はちょっとお騒がせします」と声をかけると、農作業の手を止めて、立派な白菜をくださいました。 このプロジェクトの実行にあたっては、立案当初から朝日町役場や立木地区の方々にご心配をおかけし(何しろ破壊の先入観が強い作品なので、、、)当日は周辺地域の方々の反応が懸念されましたが、実際はご年配の方々から子どもたち、役場の方々、朝日町長さんまで、実に沢山の地元の方々にお越しいただきました。 落下予定時刻の30分前には、人々が学校に集まりはじめ、巨大なクレーンと不穏な鉄のカタマリを遠巻きに眺めています。 若干ぎこちない雰囲気の中、旧立木小学校を根城に作家活動を続ける若きアーティスト集団「あとりえマサト」の板垣敬子さんが、ぬけるような爽やかな秋晴れのもと進みでてマイクを握ると、落下ポイント近くのグラウンドに自然に人々の輪が生まれ、さながら収穫後の秋の田んぼで催される村祭のような恰好になりました。 板垣さんからマイクを手渡された町長さんがおっしゃるには「こんなに大勢の若い人たちが、この立木地区に集まったことは、ここ十数年、久しくなかったことでした」とのこと。話をしている間にもひっきりなしに学生たちの車が到着「やれ、まだ落ちていないぞ、間に合った」と小走りで集まってきます。 さて、その落下の瞬間。 衝撃は足下に伝わるというよりも、楔を打ち込まれたような感覚が、視覚的インパクトを通過してみぞおちに「溜まる」感じで、しばらくのあいだ体内にとどまっていました。 少し高台の方から観ていた人は「瞬間、地面が液状化現象のように波打った」といい、近くで寝転んで観ていた人は「ズンという振動がダイレクトに伝わった」と語り、必死でカメラをかまえていた人は「ファインダー越しではなく、撮影をあきらめて直接観ようかと迷っているうちに落ちてしまった」と悔しがっていました。 思わず「あーっ!」と声を上げた人、笑い声をあげた人、衝撃に眼を見張らせたままの人、感動して涙をこぼした人・・・反応は千差万別でしたが『CASTING IRON』が生み出した振動は、そこに立ち合った約140人の身体に、忘れ難い記憶として刻み込まれたに違いありません。 「集まってくるときは無表情で、帰っていくときは満面の笑みだった」というのは、駐車スペースの交通整理に奔走してくださった『あとりえマサト』メンバーの版画家・三浦さんの談。 西さんの奥さん、お母様、2人の息子さんとそれぞれのパートナーが、この記念すべき瞬間を祝うため東京から集まり、前日のシンポジウムで司会を務められた酒井忠康先生も息子さんと娘さん同伴で朝日町まで足を伸ばされました。 様々な立場と世代の人々が、たった5分間の「鉄の落下」ために小さな谷間の広場に集まったという事実が、感動的というよりも、平穏で懐かしい、昔話の一場面のように思われたのでした。 宮本武典/美術館大学構想室学芸員 ↓大学HPに『西雅秋-彫刻風土-』展ボランティア・レポートが掲載されています! http://www.tuad.ac.jp/community/backnumberfiles/06-10/special/special.html |
■写真上:シンポジウム『神秘の樹と明日の鳥たち』の打ち上げ風景。会場はかつて芸工大がリノベーションを手がけた「蔵 オビハチ」。左から西雅秋氏、赤坂憲雄教授、酒井忠康氏(後ろ姿)、松本哲男学長、詩人の吉増剛造氏
■写真下:蔵の夜は舞踏家の森繁哉教授、『BT美術手帖』等で活躍されているライター白坂ゆりさん、彫刻家の古郡弘さんを交えて更けていった。 -------------------------------------------------------------------------- 10月28日土曜日の夕刻、『西雅秋-彫刻風土-』展とのタイアップ企画として、美術館大学構想室主催のシンポジウム第2回『神秘の樹と明日の鳥たち-詩・旅・思索-』が「こども劇場」で開催されました。 この企画は、毎回、各界の知の先達をお迎えし、座長の酒井忠康世田谷美術館長の司会のもと、ジャンルに限定されない即興的かつ横断的な「語り」によって、東北の風土のもつ豊かな文化的土壌を描写していこうとするものです。 昨年のシンポジウム『ことばの柱をたてる』にお招きした建築(史)家の藤森照信先生は、ベネチア・ビエンナーレ建築展2006日本館のコミッショナーとして活躍され、ますますお忙しそうです。(さきに『HOME』誌別冊として出版された『ザ・藤森照信』には、酒井先生がエッセイ『藤森照信氏の横顔』を寄稿され、文中「去年の秋、東北芸術工科大学で芳賀徹氏をまじえて諤々のシンポジウム〜」との記載がありました)また芳賀徹先生(京都造形芸術大学学長)は、お会いするたび「君、あの時の鼎談は楽しかったね、またやろうよ」と声をかけてくださいます。 3者の語りは、粋、というか軽みがあって、それでいて骨太な、研究室に籠っているだけでは得ることのできない、様々な土地の雨風にまみれ、靴に埃を積もらせて歩き続けた人の「大地の知恵」を感じさせるものでした。 そのユーモア溢れる知的な丁々発止は、本HP内アーカイブ『ことばの柱をたてる』の項でPDFファイルにて閲覧できます。 *** そして今年『神秘の樹と明日の鳥たち』のゲストとして、詩人の吉増剛造先生に本学にお越しいただきました。学内からは民俗学者の赤坂憲雄教授、座長は昨年に引き続き酒井先生です。 私事ですが、僕はかつて吉増先生が武蔵野美術大学の研究誌「季刊・武蔵野美術」(本学図書館に蔵書有)の巻頭グラビアにおいて、彫刻家の故・若林奮氏と共同執筆されていたテクスト『緑の森の一角獣座』に、はじめて芸術のなかの言葉を見いだした美大生でありました。以来、その詩のみならず、吉増先生が漂白の旅の中で記された銅板や写真(今回も鼎談の最中にカメラを何度も手に取られていました)にも、多大な影響を受け続けています。 吉増先生はポエトリー・リーディングの活動でも知られていますが、これまでなかなか参加する機会に恵まれず、いつもテレビモニターの中で写真家のアラーキーや、ジョナス・メカスなど、21世紀の眼の巨人たちと共にニューヨークや東京の路地を彷徨う、その筆跡に似た細身のお姿だけを拝見していました。 何年か前、東京国立近代美術館「ブラジル・ボディ・ノスタルジア」展での吉増先生の特別講演も、この時釧路から上京して同行していた友人の飛行機の時間と折り合いが合わず聞き逃したのです。 それだけに、今回の企画準備の過程で、初めて吉増先生から手書きのFAXをいただいたとき、あの独特の筆致で書かれた「宮本様」との宛名を見ただけで手が震え(ミーハーですみません)ました。吉増先生が「つばさ号」で山形駅に降り立たれた時には、出迎えの際の目印にと前もって伝えられていた「クタッとした茶色のジャケット」を追うまでもなく、改札をくぐってこられる吉増先生の姿を遠くから確認できたのでした。 茶色のジャケットの内ポケットには、細身のカラーペンが十数本、ぎっちりと並んでいて、これが「クタッと」の正体。吉増先生は、これらのペンを用い、山形新幹線の車中で、シンポジウムのために精緻な細い文字の連なりから成る「新聞」をお書きいただき、この日、集まった人々への手土産として手渡され、シンポジウムの中で詠み上げられたのでした! 前回のシンポジウムのテーマは『美術館大学』の「柱」を豪快に「ぶちあげる(酒井先生談)」こと。今回のテーマは「樹」ですから、地中深く、また天高く、大気や大地の滋味を吸い上げる、実にゆったりとした、心地よい「語り」の場になりました。とても洗練された読書会に招かれたような120分のシンポジウムが活字になるのは、来春の予定。行間からこぼれ落ちるはずの、詩的エッセンスにご期待ください。 宮本武典/美術館大学構想室学芸員 |
■写真:『混沌から踊り出す星たち』展オープニングレセプション+会場風景
撮影/石川将士(東北芸術工科大学大学院1年) -------------------------------------------------------------------------- 姉妹校の京都造形芸術大学が卒業生をフューチャーする展覧会シリーズ「混沌から踊り出す星たち」展レセプションに出席するため、久しぶりに東京へいってきました。 青山のスパイラルガーデンに展示された作品は、絵画や彫刻といった従来のアートのカテゴリーには収まらない、現代のハイブリッドなアートシーンを体現していて、それでいて関西っぽいというか、深遠さや重みを嫌うトンチの効いたアイデアと、職人的な技巧を凝らしたものが多かったです。 会期中のイベントも含め、展覧会のオーガナイズしているのは京都造形芸術大学ASP学科で、学生たちが授業の一環として運営に主体的に携わっています。 昨年もたいへん感心したのですが、彼らは、これくらいの展覧会はきちんとマネージメントできて、まだ学生然としたアーティストに、最高の舞台を用意していました。オープニングレセプションで、アーティストたちが大勢の観衆を前に、とても晴れやかに、堂々としていたのが印象的でした。 こういう雰囲気は、ただイベントプロモーターみたいに段取りをテクニカルにこなしていくだけではつくれません。運営サイドにアートやアーティストへの心からの敬意がなければ難しい。この思想的なモチベーションをしっかりと指導できているところに、ASPの後藤繁雄教授の手腕を感じました。 オープニングレセプションでは、後藤教授、評論家の市原堅太郎教授、アートディレクターの榎本了壱教授、そしてギャラリートークに招かれていた原田幸子氏に、芸工大の卒業生展『I'm here.』を出品作家の鈴木伸くんとPR。皆さんとても快い反応で、決まって「京都と山形で一緒に何かやろうよ」と言ってくださる。心強い。 一通り挨拶を終えると、パーティー会場を抜け出し、後は青山の賑やかなカフェで鈴木君と彼の制作をサポートしている石川君とともに、『I'm here.2006』の会場構成についてなど深夜まで打ち合わせ。眠らない街で、終電を気にしながらアートについて話すのも久しぶりでした。 *** 翌日の朝、帰りの新幹線は帰省するこども連れの家族で一杯です。福島を過ぎると、車窓には、眩しい日本の夏が流れていきました。 山形駅に着くと、改札口では『山形花笠踊り』の興奮がお出迎え。大混雑していた東京の人ごみのなかでエンターテイメントなアート作品を鑑賞し、普段は眠ったような私たちの街で、華やかで、力強い祭に出会う。 トランクを引いて、半ば駆け足で改札口に立つ出迎え人のもとへ向かう帰郷者に混じりながら、「一体、どっちが僕の求めているものだろう」と考えていました。 美術館大学構想室学芸員/宮本武典 ...もっと詳しく |
■写真上:大橋仁「いま」展会場風景
■写真下:右から大橋仁氏、宮本学芸員 2006年8月9日14:00-15:30/こども劇場 撮影:加藤芳彦 -------------------------------------------------------------------------- 夏の「TUADオープン・キャンパス」企画の一つとして、こども芸術教育研究センターで、写真家・大橋仁さんのギャラリートークが開催されました。僕も建築コースの公開コンペ審査の合間をぬって、インタヴュアーとして参加、写真集『いま』(青幻舎)についての対話およびスライドショーをおこないました。 トーク会場となったこども劇場の周囲には、一週間前から『いま』の写真の中から20点ほどが、大橋さん自身の手による構成で展示されていました。その中で、劇場の入口に掲げられた大延ばしのプリントが、出産シーンを真正面からとらえたショッキングな写真であったために、事務局の中には、こども芸大に通学する児童や保護者の反応を懸念する声もありました。こども劇場は、胎内とイメージした球形をしています。その入口(出口)に出産シーンの写真を高々と掲げるのが、大橋さんの意図するところだったのですが。 しかし、いざフタを開けてみると、こどもたちは「これ!赤ちゃんが生まれてくるところ!」と、いたって自然な反応。お母さん方は「生んでいる本人は見ることのできない瞬間なので驚きました。ウチの子もこんなふうに生まれてきたんだ…」、「出産はもっと奇麗なものだと思っていたのですが、こんなに壮絶な、命の切実さにみちた瞬間なのですね」等々、深いインパクトを受けたようです。 本学の徳山詳直理事長もご覧になり、ずいぶん長い時間、写真集に見入っておられ「感激した。〈こども芸術教育〉を掲げるなら、こういう視点をきちんと示さなければならない。京都造形大のこども芸大でもぜひ開催しよう!」とおっしゃっていました。 ギャラリートークには、展覧会を通して写真家・大橋仁の眼差しに惹かれた人々が集まり、写真家の言葉に耳を澄ませました。中には午前・午後の2回とも参加した学生も見受けられました。対話の冒頭では、インタヴュアーとして聞き役に徹しなければならない僕も、大橋さんに質問したいことが沢山あって、つい長々と私的な感想に夢中になってしまい、後で「7:3の割合でしゃべっていたよ」とトークを聞きに来ていた家内に指摘されてしまいました。私事ですが、僕たち夫婦も3月に第1子が誕生予定で、それだけに写真集『いま』の世界観は気になるところであったのです。 トークの話題の中心は、やはり分厚い写真集の3分の1を占め、克明に写し取られている出産の写真についてでした。 実際の分娩室は、母親やその家族は勿論のこと、医師、看護士など大勢の人がいるはずなのですが、写真にはそれらの人々の姿は登場しません。ただ取り上げられたばかりの青黒い赤ん坊が、生きているのか、死んでいるのかもわからないような命の境界点で人々の手に抱かれ、写真家の眼差しと向き合っています。大橋さんはこの点について「ある特定の個人の物語のように撮りたくはなかった。ただ生物としてのヒトの誕生の瞬間を写したかった」と語っていました。 前作『目の前のつづき』で、自らの家族の死と再生の記録を淡々と撮影し、荒木経惟に続く「私写真」の旗手としてデビューした大橋さん。 2作目となる『いま』では、あえて個人的な被写体を排除し、「出産」という誰もが経験したダイナミックな命の瞬きをテーマに選ぶことで、その眼差しは、見る側の記憶とリンクしていきます。 スクリーンに次々と投影されるスライドを見ながら、僕は大橋さんに「この赤ん坊は、かつての大橋さんであり、僕でもある気がします」と話していました。 美術館大学構想室学芸員/宮本武典 ※トークの内容は、こども芸術教育研究センターの紀要に後日まとめられるそうなので、その時にまたお知らせします。 |
■写真:大橋仁写真展「いま」DM表紙(デザイン:豊田あいか)
2006年7月24[月]ー8月10日[木] こども芸術教育研究センター・ギャラリー 10:00ー17:00 休館日/7.30[日]、8.5[土] -------------------------------------------------------------------------- 昨年末にこども芸術教育研究センターから、「こどもをテーマにした写真展を開きたいので、いい写真家を紹介して欲しい」とリクエストを受け、かねてより強く心を惹かれていた写真集『いま』(青幻社)の著者・大橋仁さんのお名前を伝えたところ、なんと、現実に個展が実現しました。今日から、こども芸術教育研究センターで開催しています。 大橋さんのデビュー作『目の前のつづき』は、親族の自殺未遂をドキュメントした写真集で、渋谷のパルコブックセンターで初めて手にした時、その圧倒的な現実感に、冷ややかな狂気を感じました。アラーキーが帯に「凄絶ナリ。A」との筆書きコメントを寄せていたのも印象深かった。 その、日常の中の死の予感を凝視した前作から一転して、出産の光景を通して、生まれてくる命をまっすぐに写した『いま』。展示は、大橋さん自身がギャラリー空間に合ういくつかのイメージを写真集から抽出したのですが、胎内をイメージして設計された楕円形の「こども劇場」とは、とても象徴的に絡みあって、忘れ難い印象を残します。 展示室のはじめには出産シーンを真正面からとらえた大判のプリントが掛けられていて衝撃的。それから林立する都市や、夜の小動物、カーテンの揺らめきを経て、再び羊水のイメージへ・・・。一点一点の意味を追うのではなく、彼岸と河岸を透過する、眩しい映像の叙事詩のような光の揺れが、静かに胸に迫ってくる展覧会です。 8月6日[日]には大橋氏が来学。私、宮本と「いま」展の会場でギャラリー・トークをおこないます。11:00-と14:00-の2回です。ぜひご来場ください。 美術館大学構想室学芸員/宮本武典 |
いつも図書館の机に陣取り、エスキース帳に、くしゃくしゃの文字やらドローイングを書きなぐっていた高木君の卒業制作は、池に張った氷の上、ずぶ濡れになりながら詠むポエトリー・リーディングだった。
途切れ途切れのドラムス、聞き取れない叫び声(「僕は 彼女の 赤ん坊に なりたかった・・・」)押しだまる聴衆、重たい灰色の空。 誰かに訴える為ではなく、叫びは、自分自身にこそ叫ばれるべき時がある。 今回、彼が「叫ぶため」に求めたシチュエーションは、芸術の名のもと以外に、この狡猾で、ややっこしい世界にはあまり用意されていないだろう。 長い詩の、真剣な朗読が続く間、僕は聴衆の背後をウロウロ歩き回ってばかりいて、落ち着いて聴く事ができなかった。 人々に踏みしだかれぐちゃぐちゃになった雪に足を取られながら、僕は、 「地下水道をいま通りき暗き水のなかにまぎれて叫ぶ種子あり」 という寺山修司の短歌を反芻していた。 宮本武典(美術館大学構想室学芸員) ※このブログに「図書館」がよく出てくるのは僕のデスクが貸し出しカウンター奥にあるためです。あしからず。 |
いつも図書館から借りていく本のセンスが秀逸だった阿部君の、これが指で描いた油絵。
重ねても重ねても濁らない色彩からは、盲目的に色彩と戯れるドローイング・ハイの高揚と、慎重にタッチを律する理論性が混在し、高い完成度に達している。 やったぜ。 阿部君は、絵画の経験を相対化する為に、普段から様々なジャンルから的確な要素を選びとれる人だった。 何よりも、それが決定的に強い。 例えば、去年の秋に開催した『珍しいキノコ舞踊団』のレジテンスでも、すべての公開練習、公演に立ちあって、ダンサーたちの動きから、絵画制作のヒントを見つけようとしていた。 けれども、そのタッチの集積が向かうフォルムについては、あくまで保留のまま。絵画の恐ろしいところは「迷い」がそのまま定着して、絵としては「完成」してしまうことだ。 自分自身の皮膚のように、日常生活に貼り付いた(時々は切ったら血が滴る)阿部君の「塗り」は、これからの彼の人生に纏わりつくのだろう。 ライフ・ワークの誕生ということ。 宮本武典(美術館大学構想室学芸員) |
『いつかみたー秋田平野を想うー』
千田郁代(工芸コース陶芸専攻) 道路端が寝雪がゆるんだ気がしたのもつかの間、再び雪と寒風吹き荒む今週から、2005年度の卒業制作展がはじまりました。 大学構内に加え、山形美術館、悠創の丘と3会場にわたり、学生たちがここ山形での生活で出した「答え」が展示されています。 それにしても、真白い雪に覆われた風景の中での卒業制作展というのは、緊張と、後悔と、疲労と、安堵に充ちた(歓喜はないですよね?)このイベントに、なんだか抗し難いある種の「切なさ」を補強している感じがするのは僕だけでしょうか? 卒業生のみなさん、きっと一生忘れる事はできませんよ。 さて、千田さんのダンス。 若い人たちの懸命な、身体を張った表現を直視すべきとき、僕はしばしば「強い観者」と「弱い観者」という言葉について考えてしまいます。 たいてい僕は逃げ出してしまうのですが、これは照れくさいというより、彼らのストレートな投げ出しを、肯定してしまうことに「恐さ」を感じるのです。 とても僕には引き受けることはできないし、その資格もない。 けれども千田さんのダンスは(そんな僕なんかより)雪の身を切るような冷たさと、彼女の背後で白くかすんだ山々に、確かに祝福され、肯定されているようでした。 彼女が山形で学んだ事が、しっかりこの地の「風景」になっていると感じましたよ。 宮本武典(美術館大学構想室学芸員) |
「展評」といっても、まだ見ていない展覧会なのですがご紹介を。
本学卒業生の佐藤妙子さんの個展が、東京都小平市は武蔵野美術大学の近く、のんびりとした東京郊外にある画廊『松明堂ギャラリー』で開催されます。 *** 新作家たち2006『佐藤妙子展「Life - traveling」』 会場:松明堂ギャラリー 〒187-0024 東京都小平市たかの台44-9 松明堂書店地下 PHONE.042(341)1455 FAX.042(341)9634 会期:2006年2月17日(金)〜2月26日(日)11:00〜19:00開廊時間 アクセス:西武国分寺線「鷹の台」駅前(JR中央線「国分寺」または西武新宿線「東村山」乗り換) *** 松明堂さんは、ムサビ生だけでなく、津田塾大や白梅短大など、多くの学生が利用する「鷹の台駅」の眼の前にある、一見して庶民的な書店です。 しかし、松本清張の息子さんが経営されているということもあり、書架をよく見ると渋いセレクションの文学書、哲学書、美術書が並び、地下には黒大理石を敷き詰めた無骨なギャラリースペースを有しています。 書店の運営するスペースだけあって、望月通陽さんや司修さんなど、挿絵や装幀を手がける人気作家を中心に紹介しています。 また、長倉洋海さんや関野吉晴さんなどドキュメンタリー写真の方が、出版記念展を開催したり、また、暗黒舞踏の公演、民族楽器によるコンサートをおこなうなど、地域の文化活動の拠点となっているんですね。 松明堂ギャラリーがもしなかったら小平市の芸術文化レベルは低いものだったでしょう。 僕も学生の頃から随分通って、コンクリートの壁面に展示されている、工芸的で、少しばかりアングラな香りのする作品に、かなり影響を受けています。 2000年には「模型世界」と題した僕自身の個展も、開催させてもらいました。 十年来のご縁があって、今回の佐藤妙子さんによる版画展は、松明堂ギャラリー若手支援企画展「新作家たち」シリーズに、僕が紹介する形で実現しました。 佐藤さんの作品は、芸工大本館2階北側に常設展示されています(コレクションINDEXにもデータ有)その黒々とした描画のずば抜けた密度は、きっとあの独特の地下空間で際立つことでしょう。 東京駅からオレンジ色の中央線に揺られ、約1時間。 皆さん、東京に行かれる際は、ぜひ覗いてください。 ちなみに松明堂から線路伝いに20メートルほど歩いたところにある古びたカフェ「シントン」も僕ら美大生の溜まり場でした。 竹中直人の映画のロケ地になったりして、これまた渋いスポットです。 茶色い壁紙に染み付いている三角の跡は、僕が学生時代に大きな銅板を貼付ける展示をして、つけてしまったものです。 「街が人を育てる」というフレーズがありますが、学外にこんな文化スポットがあると、地域社会が成熟していきますね。 芸術を介することの魅力は、いろいろな世代が集まれること。 そして「松明堂」の本も、「シントン」コーヒーも、若者も老人もしみじみ楽しめるものです。 芸工大の周辺にも、そんな場所ができないかな。 |
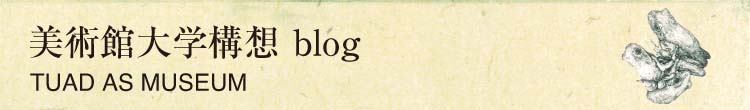















■写真中:ギャラリートーク企画「カフェ@ラボ」で映像コースが招いた映画評論家の村山匡一郎氏。氏は若い映像クリエイターの作品が、従来の「自分探し」から「エンターテイメント」への移行している世界的な傾向を紹介し、その過程ですり落ちてしまう表現者の視野の狭さ、モラルの低下に警鐘を鳴らしていた。「山形には距離的なハンデはあるものの、国際ドキュメンタリー映画祭の伝統があるのは素晴らしいこと。この地に世界中から集まってくる映像を通して世界の現状を知り、映像表現の役割について考えてほしい」と語った。
■写真下:同じく「カフェ@ラボ」で環境デザイン学科は東北大学の小野田泰明氏(右)をゲストに迎えた。対談の相手は「みかんぐみ」の建築家で、本学の竹内昌義助教授(左)。
----------------------------------------------------------------------------------
テレビのCMで、解剖学者の養老孟司氏が、高校生からの、「先生、〈知る〉ってどういうことですか?」との問いに、「〈知らなかった時〉と〈知った後〉では、まったく別の人間に生まれ変わることです」と答えていました。僕たちは、このような〈知る〉体験に、身体が死を迎えるまでの間に、いったいどれだけ出会うことができるでしょうか?
情報を記憶し、詰め込むだけのカタログ的な学びでは足りない、本質をまるごとつかみとるようなダイナミックな意識の転換。単なる蘊蓄ではなく、価値の押しつけでもなく、「常識」だと思い込んでいた物事の成り立ちの枠を取り払って、まったく広大な「知」の沃野へと押し広げてくれるような、機知に富んだ言葉との出会い。これはなかなか出会い難いもので、理解するための学びも当然必要でしょうし、ただ盲目的な批評の受け手であっても駄目だと思います。
けれども何よりも重要なことは、批評する側も、受け手も、その試行錯誤の果てに「辿り着きたい世界」において、漠然とではありますが、どこか似た指向性を持っていることだと思います。さまざまな「知」の現場で希求される、ある共通した新しい生成の予感。
これを「同時代性」といってもいいかも知れません。同じ時代の、知識人や才能ある表現者たちが、互いに影響し合いながら連鎖し、次の新しい時代を拓いていく。その一端に触れることが、教育現場における、もっとも素晴らしい(芸術)知的体験の一つだと、僕は思います。
前回のブログで書いたように、学部生時代は悶々と過ごしていた僕でしたが、進学した大学院では、幸いにも刺激的な批評の場に身を置いて、緊張感のある学びの時を過ごすことができました。
「オリジナルであれ」「権威に迎合するな」「自己満足は論外」「美術史を学べ」「社会問題に眼を向けよ」「内省を掘り下げよ」「徹底的にやれ」「手を止めず、自らの仮説を信じよ」…恩師の戸谷成雄先生の批評会は毎回厳しいものでしたが、それ以外にも、定期的に学外から国際的に活躍するアーティストを呼んできては、ディスカッションの機会を設定してくれました。(宮島達男副学長もその1人でした)
皆、破滅的・自己陶酔型の芸術家とはほど遠く、知的で紳士的。ギラギラした出世欲など微塵もなく、どちらかというと素朴で静かな方々だったのが意外でした。国際的に成功するアーティストって、熾烈な競争を勝ち抜いたアスリートか政治家のような性格なのだろうと思っていたのです。
講義の後、決まって国立駅前のレストラン『ロージナ茶房』でゲストを囲んで食事をしました。ワインを飲みながら、家族のこと、学生時代のこと、制作者としての悩みなど、リラックスして話をしました。彼らは経験から得た知識を編集し、自分なりの解釈と、世界観を構築し、しかもそこには誰でも住まうことのできる「器のひろさ」を持っていました。その根底には、あえて甘ったるい言葉を使えば、「人間愛」が横たわっていたように思います。
********
今回の卒展において、外部からのゲストを交えての「公開審査会」や「シンポジウム」、「カフェ@ラボ」など、たくさんのトーク企画を組んだのは(参照:http://www.tuad.ac.jp/sotsuten2006/events.html)僕の中に、大学時代の経験を通して、外部の視点を交えた「批評の場」の教育的な効果(←あまりいい言い方ではありませんが…)を、身をもって信じている部分があったからです。
各学科コースの先生の協力もあり、会期中は大勢の学識者の方々が来学され、キャンパスのあちこちで、教員や学生たちと語り合いました。ゲストの方々は、学生たちの取り組みを客観的な視点から批評してくださり、また、芸工大での学びを、卒業後、社会においてどのように実践・発揮していくのかなど、シャープな問題提起もしていただきました。(これらのイベントの詳細については、学生スタッフの取材チームが下記ウェブサイトにUPしています。卒展ディレクターズHP=http://gs.tuad.ac.jp/directors/index.php)
しかし中には、「卒展」とはあまり繋がりの感じられない講義や、作者とのコミュニケーションのない、作品への一方的な感想しか聞けなかった講評会もあったように思います。そのような態度から発せられる言葉と聞いていると、僕は本当に虚しくなってしまいます。批評する人は、その言葉を聞く学生たちの無表情な顔に敏感になるべきです。
学生たちは無知ではなく、ただ漠然としたその「何か」の輪郭を描くための、方法や言葉を、まだ獲得していないだけなのです。本当に聞く価値のある批評には、「私たちは何をすべきか、一緒に考えよう」という真摯なメッセージが含まれています。若い人たちと、一緒に何かを語り、考えることの楽しむ、批評者の魂の新鮮さが伝わってくるのです。
そして茂木健一郎さん。
まさに超多忙・時代の寵児でありながら、卒展オープン前日に山形入りし、アートディレクターの北川フラムさんとともに、4時間かけてキャンパスに展示された全出品作を観ていただきました。夜には大講義室にミーティングテーブルを設置し、卒展のコンセプト「OUR ART. OUR SITE.」の趣旨にのっとり、「ここでしか生まれ得ない作品や発想」を評価指標にして、523人の作品・研究のなかから5名の作品を『卒展プライズ2006(作品買い上げ賞)』に選出していただきました。
(審査員:酒井忠康/北川フラム/茂木健一郎/松本哲男/山田修市/宮島達男)
賞の選考課程は学生たちに公開されていたのです。夜の講義室には、たくさんの学生が集まり、「時代の眼」ともいえる審査員の方々が、約500の作品から、たった5点を選出する、100分の1へ至るスリリングなミーティングに立ち合いました。
翌日のシンポジウムでは、芸術作品の価値の優劣を生み出す歴史的・政治的な「文脈」と、作品自体が私たちに与える感動(クオリア)との関係について語ってくださいました。
現状の流行やアートシーンを牽引する「文脈」のイニシアチブは、私たちの生きるこの東北に存在しないことは明らかですが、だからといってグローバルな視点で見た時、東京がその中心にあるかというとそうでもない。Tokyo>Yamagata? 欧米>日本? 茂木さんは「言語や肌の色、国籍や文化、学歴や収入など、様々な文脈が生み出す優劣のコンプレックスから、私たちは完全に逃れることはできない」としながらも、「自分の生きる土地や、人生、作品の本質は、そこに完全に回収されるものではないことを自明のものとしているか、いないかは大きな違いだ」と語りました。
また、茂木さんは文脈の作用自体を揺さぶる〈認知テロリスト〉としての表現の打ち出し方を理論的に構築していく必要性を説き、「既存の価値の構造から逸脱して、この山形の土地にしかない歴史の深みへと降りて生きていく勇気を!」との熱っぽい提案で講演を締めくくりました。
確かに、ものをつくったり、研究していく過程で、自らの「勇気」が度々試されているのを、学生たちは自覚していたはずです。既にある評価の型に安住するか、しないか? 何か余分なものを捨てる勇気。大胆に変えていく勇気。威張ったもの、古いもの、淀んで溜まっているものと決別する勇気。
都市ではなく、「東北」で学ぶことの意味は、他と比較できる文脈において相対的に構築するのではなく、まずその競争自体から降りて、自分たちで価値の構造自体を生み出していくこと…。茂木さんの口調は穏やかでしたが、その語りは、実はこの大学がおかれている状況に対しての、極めて的確で、厳しく、そして素晴らしく建設的な批評であったと僕は受けとめています。
宮本武典/美術館大学構想室学芸員
(茂木氏はブログ「クオリア日記」で、山形での2日間を紹介してくださっています。)
http://kenmogi.cocolog-nifty.com/qualia/2007/02/post_bc16.html