メモ

|
背後の絵画作品『部屋・紫・少女の砂』は、後藤君の卒業制作で、2004年の損保ジャパン絵画大賞受賞作。その後、2004年度学長奨励賞として買い上げられ、今も学内に常設展示されている。
-------------------------------------------------------------------------------
美術館大学構想室のアシスタント後藤拓朗君が、2年間のアシスタント期間を終え、構想室を「卒業」します。キャンパス各所にある常設作品を巡る、入学希望の高校生を対象にした鑑賞ツアーで、作品解説をお願いしたのをきっかけに声をかけ、以来2年間、構想室が企画したすべての展覧会を裏方として懸命に支えてくれました。
これまでに構想室が招いた様々なアーティストや知識人たちとの出会いに影響され、「構想室に関わるようになって、これまでのようにシンプルに絵と向き合えなくなった」と語っていた後藤君。特に、レジテンスで山形に長期滞在したアーティストの富田俊明さん、彫刻家の西雅秋さん、珍しいキノコ舞踊団のメンバーといった、自由放漫かつ才気溢れる「マレビト」との交流は、山形で生まれ育った画家志望の青年に、少なからぬ若さ故の悩みをもたらしたようです。
春からは、「とにかく一度、故郷であるこの山形市を出て、自分の制作や生き方について考える時間を持ちたい」と心に決めたようです。そしてこの言葉は、後藤君だけでなく、親交のあった何人かの山形出身の卒業生たちの口からも聞いた固い決心でもありました。
僕が故郷と創作の愛憎関係について思い巡らすとき、心のなかでいつも反芻する言葉があります。それは、僕の敬愛するマルティニック諸島出身のアフリカ系フランス人小説家マリーズ・コンデの次の言葉です。
****
精神の彷徨がなければ創造性は生まれない、と私は思います。
不動性のなかで、盲目的に根をはった生活で、何かが生みだされるとは思いません。
彷徨しなければならない。
彷徨生活は人を解放してくれます。
(…中略…)
私は、創造行為、エクリチュールとは一種の無限運動、
絶えず変化する差異の運動だと思います。
それは流れる水のようなもので、
誰かが言ったように、その水は絶えず繰り返され、再開される。
つまり小説創造は絶えず再開されるのです。
私は一カ所に根を下ろす〈根付き〉ということを信じません。
肉体は故郷に帰りましたが、精神は航海を続けなければならないのです。
マリーズ・コンデ
****
クリエイトは終わりのない旅のようなもの。
故郷を離れ、たとえ何処に暮らしたとしても、そしてまた、たとえ創造の日々が中断したとしても、一度深く探し出された感性の鉱脈は、簡単に枯れることはない。これから先、虚ろな情報社会のパワーゲームに傷つくこともあるだろうけれど、芸術を学び、絵画に自分の可能性を賭けた日々に誇りを持って、生きていってほしいと思います。
後藤君ありがとう。
お疲れさま。
そしてこれからもよろしく。
宮本武典/美術館大学構想室学芸員

|
■写真下:ダンボールケースの中身は以下の3アイテムによる分冊形式。
1)卒展ガイドブック(下)
各学科コースの展示内容やイベントの詳細情報と、卒展出品者523名全員の顔写真、プロフィール、作品/研究コンセプトを紹介している。鑑賞ツールとして来場者に活用してもらうことを目指し、なんとか開催期間中に間に合うように制作した。523名からの原稿回収は、それぞれのPCからブログ書き込み形式をとって手間を省略。会期中はインフォメーションカウンターで1冊500円で販売した。
また、出展者データは学科コースの枠を取り払う50音順で掲載し、通し番号が実際の作品に付けられていたタイトルプレート(キャプション)と照合して検索しやすいように工夫をした。
2)卒展ドキュメントブック(左)
全出展研究・作品の展示写真を掲載するとともに、茂木健一郎氏の講義など、会期中に開催されたさまざまなトークイベントを採録している。フルカラー&厚さ3センチ。各写真は、ガイドブックの出品者データと照合できるようにナンバリングが施されている。DVDに収録されている論文と映像の作品については、サムネール的なテキストと写真をリストとして列記した。
3)卒展DVDデータ(右)
論文と映像作品はPC上で閲覧できるようにDVDデータにした。論文はpdfファイルをダウンロードさせることで、これまでの要約だけの掲載ではなく、ほぼフルボリュームのデータベース化が実現。映像作品はフラッシュでそれぞれ短編に再編集した動画をパソコン上で観ることができるようになった。
---------------------------------------------------------------------------
卒展カタログの紹介とともに、下に転載する「Guide」は、僕が年に4本書いている本学図書館発行の「ライブラリー通信」コラムです。今年卒業してしまった何人かの学生が、毎回「読みましたよ!」と声をかけてくれていたので、これからはこのブログに転載します。コラムの内容は、卒展カタログ編集時に、僕がいつも考えていたことでもあります。
****
Guide:出会い難き紙片
バルセロナのソフィア王妃芸術センターで、ピカソの『ゲルニカ』にはじめて対面した時のこと。ギャラリーには大勢の人がいたのだが、皆、絵と反対側の壁に張り付くようにして、できるだけ絵と距離をとって鑑賞していたのが印象的だった。巨大な画面の全体像を視界で隅々まで捉えるためには、およそ6mは画面から離れなければならない。人々は安心した表情で、予備知識として事前に蓄えた『ゲルニカ』の図(イメージ)を確認していた。そこには、教科書通りの構図、反戦のメッセージを伝える様々な寓意が織り込まれている。手元のガイドブックには、丁寧な解説もついている。
だが、僕は一人、信号のタイミングを間違って横断歩道を渡りはじめた人のように、見えない境界線を踏み越えて歩き出す。油絵の具の香りを嗅げるくらいキャンパスに近寄って、その力強い筆致と、黒い絵具の質感を眺める。この時、僕の目の前に存在するのは、画集どおりの「図」ではなく、人間パブロ・ピカソが引いた黒々とした線なのだ。そびえ立つ雄牛に圧倒され、暗い画面に灯る?燭の光を感じ、そして何より、画家が絵筆で告発した戦争のビジョンに包み込まれるようにして、一枚の太い木枠と、麻布と、絵具と、画家の腕の痕跡として、そこに確かに『ゲルニカ』が存在しているリアリティーを感じようとしていた。
図書館の画集で、美術館で販売されているポストカードで、僕たちは名画のイメージに慣れ親しんでいる。印刷物となって、手から手へ渡っていく無数の『ゲルニカ』。世に傑作と呼ばれる作品は、出会いの空間を限定されるオリジナルよりも、その作品を取りまくイメージや、ストーリーがひろく国境を越えて共有されていく。多くの人が、例えばルーヴルの『モナ・リザの微笑み』のオリジナルを観たとき、「本物はやっぱり違うよね」と、既に見知った『印刷物のモナ・リザ』との違いを表明せずにはいられない。(よくよく考えてみれば、これは奇妙な発言だ。僕たちは、絵画そのものに、いったい何を見出しているのだろう?)
ポストカードになって世の中を巡っているアート作品は、名画だけではない。美術館でアシスタントをしていた頃、毎朝、学芸員宛に届けられる展覧会の案内状の量に驚いたものだ。毎日、毎日、呆れるほど沢山の展覧会が開催されていて、それを宣伝する一枚一枚に、大仰なタイトルや但し書きが張り付いている。発表する側にとって、それは当然の態度だろう。このアーティストに理解のない国で、どんどん公立美術館から予算を削り、義務教育から情操教育を駆逐している国で、1年以上かけてゼイゼイと資金をかき集めて準備した発表の機会なのだから。
けれども現実は、送り手の淡い期待に反して、有力な美術館やギャラリーでは、コレクションされている作家の新作展などの重要な案内状以外は、ほとんどトランプのカードを切るようにして一瞥されゴミ箱へ直行する。勿論、1枚1枚きちんと眺めて、保管してあげたいが、そんなことをしていたら書類棚はすぐに一杯になってしまうのだ。
****
『ゲルニカ』であれ、無名の若手の意欲作であれ、また、それがオリジナルであれ印刷物であれ、美の価値は、様々な情報の力関係においてドライに分類され処理されていく。けれども、不意に送りつけられた何の予備知識のないポストカード上の作品に(ごく稀にだが)無条件に心を惹かれることだってある。
紙面に自分を大きく見せようとする誇大広告の因子が感じられないもの。「まだ答えは出ていない。結論は固まっていない。それを決めるのはあなただ」とメッセージを送ってくるもの。実際にその展覧会に足を運ばなくても、壁にピンナップしているだけで、充分そのアーティスティックな恩恵を与え続けてくれるもの…。
デザインワークは重要だ。写真、タイポグラフィー、コピー、紙質は洗練されていなければならない。だが、それ以上に、送り手のイメージの中で、一枚の紙片となった自身の作品が渡っていく街の風景や、受け取った人の心の動きを、どれだけ具体的に出会いのストーリーとして描いているかが大切だ。
心を打つアートとの出会いは、(どこかで読んだフレーズだけど)極めて起こり難いラブストーリーのように、デリケートにその瞬間を育てていく。膨大な情報の海のなかで生きる僕たちが、たった一枚の紙片を通して、偶然に「見知らぬ誰か」の瑞々しい感性と深く出会うことは、バルセロナでピカソと出会うことと同じくらい感動的な出来事なのだと思う。(東北芸術工科大学図書館発行『ライブラリー通信2007.spring』から転載)
宮本武典/美術館大学構想室学芸員

|
■写真下:4番目の孫を抱く父。山形で8年間の教授生活を終え、今春から長野県佐久の山荘に移る。これからは膨大な資料に囲まれた書斎で建築史家として総仕上げの研究に取り組む。
----------------------------------------------------------------------------------
私事ですが、このブログで度々書いてきたことなので報告します。
今月10日に、はじめての子どもを授かりました。
助産師さんから連絡がはいった深夜0時から家内の陣痛の波が激しくなり、明け方に分娩室に一緒に入って出産に立ち合いました。
しっかりした身体付きの女の子が生まれたのは、まだ夜も明け切らない5:30で、窓からは蔵王の灰色のシルエットが、薄ら空と大地の境界線を描きはじめていました。白々とした蛍光灯の明かりの下で目撃したその瞬間は、以前、大橋仁氏を紹介したブログでも書きましたが、本当に壮絶で切羽詰まった、愛しい命の瞬きでした。
入退院していた時期が、卒展の準備が加速度的に激しくなっていた期間と、ちょうど並行していたこともあり、大学の同僚、先生方、そして大勢の学生たちから暖かい気遣いをいただきました。感謝。
ディレクターズのメンバーからは、沢山の紙オムツのプレゼントが届いたのです。(示し合せていたようです)一つ一つちゃんと包装してあって、むくつけき男子学生が、東青田の『ツルハドラック』で神妙な顔で注文したのかと思うと、頬が緩みます。
ありがとうございます。充分活用させてもらいます。
赤ん坊の名前は、「結子(ゆいこ)」としました。
どのような生き方をするにしても、彼女なりの方法で、人と人の、文化と文化の良きつなぎ手として生きていってほしいとの願いを込め、「つなぐ糸」が「吉をもたらす」という組み合わせを選びました。現在は家内ともども退院し、大学近くのマンションで、3人での静かな生活がはじまっています。
そして、新しい家族が加わると同時に、歴史遺産学科で教授を8年間務めた父・宮本長二郎が、東京芸大時代からの、長かった大学生活を辞し、山形の仮住まいから自邸のある長野県佐久市に移ります。日本全国の遺跡を歩き続け、この列島に埋もれた古代の建築史の謎に向かい続けた筋金入りの研究人生に、不出来な息子たちは只々敬服するのみですが、不思議な縁で2年間、同じ大学に勤められたことは幸せでした。お疲れさまでした。
*****
さて、折しも今日3月21日は東北芸術工科大学の卒業式。
僕は式自体には立ち合わず、寒風の中、ディレクターズの活動よろしく駐車場誘導をしていたのですが、卒展でなじみになった学生たちが、きちんと正装して、堂々と歩いていくのを、嬉しく眺めていました。若い人たちの旅立ちを見送る立場として、「おめでとうと、さりげなく」よりも、どこか寂しさを感じている自分に、この1年間のそれなりの充実感を噛み締めていました。
寂しいので、この後の祝賀会には出席しません。が、父と僕との不思議な巡り合わせのように、この業界でそれぞれにきちんと仕事をしていれば、いつかまた一緒になることもあります。その可能性に期待して。
卒展を終え、山形のキャンパスを巣立っていく学生たちにとって、そして僕たち家族にとって、それぞれの「産みの苦しみ」を通過し、今、ひとつの時代が穏やかに幕を閉じました。
宮本武典/美術館大学構想室学芸員
...もっと詳しく

|
■写真中:ギャラリートーク企画「カフェ@ラボ」で映像コースが招いた映画評論家の村山匡一郎氏。氏は若い映像クリエイターの作品が、従来の「自分探し」から「エンターテイメント」への移行している世界的な傾向を紹介し、その過程ですり落ちてしまう表現者の視野の狭さ、モラルの低下に警鐘を鳴らしていた。「山形には距離的なハンデはあるものの、国際ドキュメンタリー映画祭の伝統があるのは素晴らしいこと。この地に世界中から集まってくる映像を通して世界の現状を知り、映像表現の役割について考えてほしい」と語った。
■写真下:同じく「カフェ@ラボ」で環境デザイン学科は東北大学の小野田泰明氏(右)をゲストに迎えた。対談の相手は「みかんぐみ」の建築家で、本学の竹内昌義助教授(左)。
----------------------------------------------------------------------------------
テレビのCMで、解剖学者の養老孟司氏が、高校生からの、「先生、〈知る〉ってどういうことですか?」との問いに、「〈知らなかった時〉と〈知った後〉では、まったく別の人間に生まれ変わることです」と答えていました。僕たちは、このような〈知る〉体験に、身体が死を迎えるまでの間に、いったいどれだけ出会うことができるでしょうか?
情報を記憶し、詰め込むだけのカタログ的な学びでは足りない、本質をまるごとつかみとるようなダイナミックな意識の転換。単なる蘊蓄ではなく、価値の押しつけでもなく、「常識」だと思い込んでいた物事の成り立ちの枠を取り払って、まったく広大な「知」の沃野へと押し広げてくれるような、機知に富んだ言葉との出会い。これはなかなか出会い難いもので、理解するための学びも当然必要でしょうし、ただ盲目的な批評の受け手であっても駄目だと思います。
けれども何よりも重要なことは、批評する側も、受け手も、その試行錯誤の果てに「辿り着きたい世界」において、漠然とではありますが、どこか似た指向性を持っていることだと思います。さまざまな「知」の現場で希求される、ある共通した新しい生成の予感。
これを「同時代性」といってもいいかも知れません。同じ時代の、知識人や才能ある表現者たちが、互いに影響し合いながら連鎖し、次の新しい時代を拓いていく。その一端に触れることが、教育現場における、もっとも素晴らしい(芸術)知的体験の一つだと、僕は思います。
前回のブログで書いたように、学部生時代は悶々と過ごしていた僕でしたが、進学した大学院では、幸いにも刺激的な批評の場に身を置いて、緊張感のある学びの時を過ごすことができました。
「オリジナルであれ」「権威に迎合するな」「自己満足は論外」「美術史を学べ」「社会問題に眼を向けよ」「内省を掘り下げよ」「徹底的にやれ」「手を止めず、自らの仮説を信じよ」…恩師の戸谷成雄先生の批評会は毎回厳しいものでしたが、それ以外にも、定期的に学外から国際的に活躍するアーティストを呼んできては、ディスカッションの機会を設定してくれました。(宮島達男副学長もその1人でした)
皆、破滅的・自己陶酔型の芸術家とはほど遠く、知的で紳士的。ギラギラした出世欲など微塵もなく、どちらかというと素朴で静かな方々だったのが意外でした。国際的に成功するアーティストって、熾烈な競争を勝ち抜いたアスリートか政治家のような性格なのだろうと思っていたのです。
講義の後、決まって国立駅前のレストラン『ロージナ茶房』でゲストを囲んで食事をしました。ワインを飲みながら、家族のこと、学生時代のこと、制作者としての悩みなど、リラックスして話をしました。彼らは経験から得た知識を編集し、自分なりの解釈と、世界観を構築し、しかもそこには誰でも住まうことのできる「器のひろさ」を持っていました。その根底には、あえて甘ったるい言葉を使えば、「人間愛」が横たわっていたように思います。
********
今回の卒展において、外部からのゲストを交えての「公開審査会」や「シンポジウム」、「カフェ@ラボ」など、たくさんのトーク企画を組んだのは(参照:http://www.tuad.ac.jp/sotsuten2006/events.html)僕の中に、大学時代の経験を通して、外部の視点を交えた「批評の場」の教育的な効果(←あまりいい言い方ではありませんが…)を、身をもって信じている部分があったからです。
各学科コースの先生の協力もあり、会期中は大勢の学識者の方々が来学され、キャンパスのあちこちで、教員や学生たちと語り合いました。ゲストの方々は、学生たちの取り組みを客観的な視点から批評してくださり、また、芸工大での学びを、卒業後、社会においてどのように実践・発揮していくのかなど、シャープな問題提起もしていただきました。(これらのイベントの詳細については、学生スタッフの取材チームが下記ウェブサイトにUPしています。卒展ディレクターズHP=http://gs.tuad.ac.jp/directors/index.php)
しかし中には、「卒展」とはあまり繋がりの感じられない講義や、作者とのコミュニケーションのない、作品への一方的な感想しか聞けなかった講評会もあったように思います。そのような態度から発せられる言葉と聞いていると、僕は本当に虚しくなってしまいます。批評する人は、その言葉を聞く学生たちの無表情な顔に敏感になるべきです。
学生たちは無知ではなく、ただ漠然としたその「何か」の輪郭を描くための、方法や言葉を、まだ獲得していないだけなのです。本当に聞く価値のある批評には、「私たちは何をすべきか、一緒に考えよう」という真摯なメッセージが含まれています。若い人たちと、一緒に何かを語り、考えることの楽しむ、批評者の魂の新鮮さが伝わってくるのです。
そして茂木健一郎さん。
まさに超多忙・時代の寵児でありながら、卒展オープン前日に山形入りし、アートディレクターの北川フラムさんとともに、4時間かけてキャンパスに展示された全出品作を観ていただきました。夜には大講義室にミーティングテーブルを設置し、卒展のコンセプト「OUR ART. OUR SITE.」の趣旨にのっとり、「ここでしか生まれ得ない作品や発想」を評価指標にして、523人の作品・研究のなかから5名の作品を『卒展プライズ2006(作品買い上げ賞)』に選出していただきました。
(審査員:酒井忠康/北川フラム/茂木健一郎/松本哲男/山田修市/宮島達男)
賞の選考課程は学生たちに公開されていたのです。夜の講義室には、たくさんの学生が集まり、「時代の眼」ともいえる審査員の方々が、約500の作品から、たった5点を選出する、100分の1へ至るスリリングなミーティングに立ち合いました。
翌日のシンポジウムでは、芸術作品の価値の優劣を生み出す歴史的・政治的な「文脈」と、作品自体が私たちに与える感動(クオリア)との関係について語ってくださいました。
現状の流行やアートシーンを牽引する「文脈」のイニシアチブは、私たちの生きるこの東北に存在しないことは明らかですが、だからといってグローバルな視点で見た時、東京がその中心にあるかというとそうでもない。Tokyo>Yamagata? 欧米>日本? 茂木さんは「言語や肌の色、国籍や文化、学歴や収入など、様々な文脈が生み出す優劣のコンプレックスから、私たちは完全に逃れることはできない」としながらも、「自分の生きる土地や、人生、作品の本質は、そこに完全に回収されるものではないことを自明のものとしているか、いないかは大きな違いだ」と語りました。
また、茂木さんは文脈の作用自体を揺さぶる〈認知テロリスト〉としての表現の打ち出し方を理論的に構築していく必要性を説き、「既存の価値の構造から逸脱して、この山形の土地にしかない歴史の深みへと降りて生きていく勇気を!」との熱っぽい提案で講演を締めくくりました。
確かに、ものをつくったり、研究していく過程で、自らの「勇気」が度々試されているのを、学生たちは自覚していたはずです。既にある評価の型に安住するか、しないか? 何か余分なものを捨てる勇気。大胆に変えていく勇気。威張ったもの、古いもの、淀んで溜まっているものと決別する勇気。
都市ではなく、「東北」で学ぶことの意味は、他と比較できる文脈において相対的に構築するのではなく、まずその競争自体から降りて、自分たちで価値の構造自体を生み出していくこと…。茂木さんの口調は穏やかでしたが、その語りは、実はこの大学がおかれている状況に対しての、極めて的確で、厳しく、そして素晴らしく建設的な批評であったと僕は受けとめています。
宮本武典/美術館大学構想室学芸員
(茂木氏はブログ「クオリア日記」で、山形での2日間を紹介してくださっています。)
http://kenmogi.cocolog-nifty.com/qualia/2007/02/post_bc16.html

|
■写真上:大勢の来館者が行き交うInformation Passage(情報回廊)でのライブ中継。
■写真中:総勢18名のカメラクルーがLANケーブル+PC +WEBカメラのセットで移動し続けた。
■写真下:523名へのインタビューは2名の美術科1年生・新津さん+諸岡さんが務めた。事前に各学科コースの特性や卒展までの取り組みに関する取材+勉強会を繰り返して本番に臨む真摯な姿勢に拍手。この企画の詳細は卒展ディレクターズHPで=http://gs.tuad.ac.jp/directors/index.php
----------------------------------------------------------------------------------
学生時代に読んだ武満徹のエッセイに、「ベートーベンの音楽は巨大な蛸」とのユニークな喩えがありました。長く太いたくさんの足で、いくつもの吸盤で、聴衆を圧倒し巻き込もうとする、渦のような音楽。その中心には、作曲家の強烈な存在感があります。
対して武満は、エリック・サティの曲を、聴くものの中に、それぞれの心の情景を喚起させるものだと語っています。聴者の感性を楽曲によって圧倒し、支配するのではなく、聴者自身の感受性を、密やかに導き出すものとして評価しています。
とりわけピアニスト・高橋悠治氏の弾くサティは、僕にとって特別な音楽です。そのメロディーは、日常の営みに漂っている密やかな何か、生にとって大切なものへの気付きを、今、自分が過ごしている部屋の情景から、導き出してくれるような気がします。
この感覚は、絵画ならポロックよりもサイ・トゥンブリ、ピカソよりもモランディ。見る人の内省の中で発生する光やリズムを感じさせてくれる筆致への共感に近いものです。世に名作と呼ばれる芸術作品と対峙する時、僕はいつも、この対比を思い出しています。それが巨大な蛸なのか、それとも僕自身の感動なのかを。
****
卒展の期間中、本館1FのInformation Passageで放映されていたクリエイターズ・マイクは、サティの音楽のように、若い人たちのエネルギーへの、共感の姿勢を、訪れた大勢の方々の心情に喚起させていたように思いました。運営に携わった卒展ディレクターズのスタッフ18名は、523名をつなげていかなければならないという意識で、人と情報とシステムの、有機的で合理的な運動を見事に走り切りました。
マイクを向けられたインタビュイーは、自分自身を語っているのに、数百人の語りがその背後で一体となって、ザワザワと常に穏やかにつながっているように思えたのです。
映像メディアを媒体として、語ること。聞き出すこと。耳を澄ますこと。すべてを等価に扱うこと。等価のなかで差異を際立たせること。空間に声を反響させること。それら全体が一つの風景として伝わっていくこと。それが出会いを媒介していくこと…
(彼らがキャンパス全体を駆け巡って奏でた声と映像は、中継システム上の制約もあり、決してクリアではなかったので、本館を行き交う人々は映像内の彼・彼女と出会いたいのなら、足を止めて注視することが必要でした。ここでの情報は、人々を積極的に支配しない。声高に叫ばない。反応を強要しない。)
あくまで出品者一人一人に丁寧に対応し、気がつくとそれらは空間や観客やスタッフ自身も巻き込んだ大きな円環に帰結していく。この運動の結末に、スタッフ自身が大きな感動と充足感を感じていたようでした。
****
同じく卒展期間中に各会場を巡回したギャラリートーク企画「カフェ@ラボ」においても、同様のコンセプトを設定しました。同じパッケージのなかで、多様性は多様性のまま、自由に批評を展開していきます。熱心な観者は、それぞれの言説のなかにある、「大学」や「教育」や「東北」にまつわる、ある共通の視点・提言・問題意識に気が付く。これが、同時代性の発見、世界とのリンクなのだと思います。
差異を認め合いつつ、つながってつながって、それがひとつの運動となって全体を共鳴させていく。音楽の喜びに似た、和音の感覚。
美術館大学構想室学芸員/宮本武典

|
■写真中:工芸4年・大槌英樹君によるマジカルな作品配置「希薄なる境界」。雑然とした陶芸工房に、美しく磨かれた漆の黒い板が並べられていた。
■写真中:同じく、芸工大で漆を学んだ井上裕太君の乾漆と写真によるインスタレーション「Maybe that is.」。溶接工房の内部を板で囲み、地下墳墓のような緊張感のある空間を創出した。
■写真下:西蔵王から冷たい風が吹き下ろす鉄場に、無数の鉄パイプが継ぎ合わさった巨大な球体が吊り下げられた。新関俊太郎君の「父に買ってもらった鉄」
撮影:姜哲奎、井上裕太(写真上のみ)
----------------------------------------------------------------------------------
もうすぐ我が家にやってくる小さな命のために、散らかり放題だった自分の部屋を片付けていたら、靴の紙箱に無造作につっこんであった学生時代に撮った大量のモノクロ写真を見つけ、しばらく眺めていました。父から譲り受けた古くて重いNikomatで、アトリエの友人たちを撮りまくっていたのは、もう12年も前のこと。
テレピンオイルのガラス瓶や、絵具のこびりついた床に転がっているJACK DANIELや、ツナギ姿でタバコをふかす女の子たち。学食のタヌキ蕎麦に、ベルボトムジーンズと午後の玉川上水。大きな石油ストーブの近くで痩せた背中を丸めて座っている僕は、誰が撮ったのだっけ?親たちの世代と同じような70年代フォークや、ぬかみそ臭い同棲や、インドやアフリカを放浪する旅が、皆を熱中させていた頃。
懐かしさを感じると同時に、そこに写っている友人たちは、果たしてこの時代に、このアトリエに帰りたいと思うだろうか?と考えました。少なくとも、僕の答えは「NO」です。90年代のトレンドから乖離することを楽しんでいた、居心地のいいアトリエでの日々は、その実、社会との接点が見いだせない、漠然とした不安を常に抱えていたのでした。「芸術を学ぶと、不幸になる」
自分への自信のなさが、年を追うごとに皆を寡黙にさせ、マッチョな社会構造から卑屈に逃げるような無力な「ひたむきさ」で、作品をつくり続ける生活は、結局僕たちに何をもたらしたのだろうかと、考え込んでしまいます。そして、あれは「教育」だったのだろうか?との憤りも、また。
「OUR ART. OUR SITE.」をキーワードに、これまでメーン会場として借りていた山形美術館から撤退し、展示会場をキャンパスに一本化した今年の卒展。その賛否と可能性を問う、今日に至るまでの全学的かつ膨大な議論は、時にきわどい問題にも触れていきました。ある教授は、「15年経たって、今、卒展の議論によって学内に溜まった膿が一気に噴出しているんだ」と語っていました。
感情的な、あるいは腹の内を探り合うような気のおけない卒展を巡る議論の最中、不謹慎ながら、どこかでこのような状況を好ましく思う自分がいました。僕が学んだアトリエには、閉じた関係の中での居心地の良さはあっても、そうした自分達のいる「場」や「教育」そのものを深く激しく検証していくような議論はなかった。自らが属する社会への批評的な視座の欠如が、その後の12年間、僕たちを現実の生活において、常に苦しめたものだったから。
今回の卒展は(段取りには不手際もあったが、幸いにして)結果的に大成功だったとの評価を、学内外からいただくことができました。しかし、ここで示すことができた「質」は、もともと私たち芸工大が持っていた基本的な力で、これまではその創造への欲求を出力するに相応しい「場」と、「これでいいのか」という自発的な問いがなかっただけなのかな、と僕は感じています。
*****
さて、議論が生まれたことを喜ばしく思う反面、今回の卒展では、互いに批判し合うだけで何の生産性も生まれないという悪循環に陥る危険性も充分ありました。主張した自分のポリシーを実際の行動に移し、自分なりの仮説(作品+展示)に鍛え上げていくには、9ヶ月という時間は充分な期間ではありませんでした。議論が深まりを見せても、結果、表面化した展示物が質の低いものであったなら、「卒展一本化」は暴挙でしかなく、対話に明け暮れたこの9ヶ月は、虚しい徒労であったことでしょう。
そんな中で、上の写真で紹介した工芸コース有志による実習棟周辺での展示は、漆芸や彫金の伝統的なスキルと、4年間を過ごしたSITEへの愛情を見事に作品に結実させていた点で、今回、もっとも僕の心を打つ展示でありました。「卒展の会場一本化」への激しい批判から上手に距離を置きながら、建学15周年、そして全入時代の到来を機に、変わろうとする大学のもがきを、他ならぬ自分自身への挑戦として(大学への愛憎も含め)真っすぐに「作品」に向き合った彼ら。
一心に打ち込む労働的な制作の積み重ねと、互いに支え合う仲間同士のコミュニケーションが、若者たちが真摯に生きた時間を感じさせる、独立した、緊張感のある空間を生み出していました。この力強さは、大学という教育の場が自然につくりあげたもので、「サイトスペシフィック」謳ったどんな展覧会よりも、より純粋で、自然で、そして切実に、そこにありました。
一見、静かで素朴なようで、実は猛々しい東北の精神風土の中で、それに見合った精神とフィジカルのタフさを、僕たちの大学は身につけなければならない時期に来ているのではないでしょうか。
そのことを、今回の卒展を機に噴出した「若さ」が抱えているひたむきさ、好奇心。そして愚かさや不条理な制度に対する破壊衝動にさえ、教わったような気がしてなりません。懸念すべきは組織に疲れた大人たちの「無気力・無関心」なのです。ルーティンワークの中で、対話することから逃避し、若者たちの向う見ずな欲望と正面からぶつかっていくことから逃げてしまう姿勢は、自分も、自分の属するコミュニティーも、寂しく疲弊させていくことに気がつかなければなりません。
若い人たちと向き合うことで、常に新しく(懐かしく)実験的で、誠実でありたいと強く思いました。
美術館大学構想室学芸員/宮本武典

|
---------------------------------------------------------------------------
4ヶ月ぶりの更新です。
西雅秋さんの展覧会を終え、息継ぎする間もなく、そのまま卒業制作展の準備に没頭してしまいました。こんなにほったらかしにするなんて、人気ブログの条件からほど遠いですね。もし、このブログを定期的に見ている人がいたとしたら、大変申し訳ない事をしました。すみません。
しかし、宮本も美術館大学構想室も、このHP上では眠っていた4ヶ月は、今年大きく変革された「卒業/修了研究・制作展2006」の運営を担い、総合ディレクターの宮島達男副学長と、30名の学生スタッフ(卒展ディレクターズ)とともに、冬のキャンパスを駆け回る激動の日々を過ごしていました。このブログで途中経過を実況すると、弱音とカラ元気で埋め尽くされることが懸念される程、それはそれはハードな毎日でした。
これまで山形美術館で開催していた芸工大の卒展を、松本学長が「キャンパスに一本化する」と宣言してから、気の遠くなるほどの時間を議論に費やしてきました。学生はもちろん、教員、事務局、卒業生をも巻き込み、9ヶ月間「産みの苦しみ」にもだえ続けた卒展。その顛末については、学生スタッフが、卒展ディレクターズHP上にたっぷりとUPしてくれていますので、空白の時間はそちらで埋め合わせしていただければ幸いです。
卒展ディレクターズHP=http://gs.tuad.ac.jp/directors/index.php
TUAD卒展公式HP=http://www.tuad.ac.jp/sotsuten2006/
その卒展も、1週間前になんとか成功に終わりました。
アトリエや研究室を展示会場に転用し、キャンパス内17カ所でパピリオン形式で開催された展覧会を、一週間でのべ2万人の人々に見ていただきました。各サイトで展示されていた作品も、本当に素晴らしかった。
緊張の糸が切れたのか、寒風の中、野外で駐車場管理に立ち続け、次々とインフルエンザで倒れていった学生スタッフたちも、今はもうそれぞれの地元へと帰郷しました。卒展に出品した523名の卒業生たちは、一ヶ月後の卒業式までに、引っ越しや身辺整理に余念がありません。
そして、準備期間と並走するように3ヶ月間病院で過ごしていた身重の妻は、卒展終了と同時に無事に臨月を迎え、今は自宅で静かに出産の時を待っています。
過ぎてしまえば、過ぎ去るには惜しい、さまざまな出来事があった日々。静まり返っている学内で、ようやく自分なりにこの4ヶ月を見つめる余裕が出てきたので、少しずつ、自分の眼で見た卒展について、このブログに書き残しておこうと思います。
繰り返しになりますが、忘れ去られてしまうには惜しい情景だけが、雑然とした意識の片隅で、その本当の価値を当人が理解するまで、雪の夜に灯る街灯のように、微かに輝き続けます。心地よい身体と精神の披露を感じながら、この9ヶ月の経験は、まだまだ多くの事を僕とこの大学に与えてくれると感じています。
美術館大学構想室学芸員/宮本武典
...もっと詳しく

|
■写真下:クライマックスで水上能舞台から池に飛び降りた森先生。この時、闇の中には学生スタッフが流木で木造船を叩く鈍い音が響き渡り、頭上には秋の名月がありました。
--------------------------------------------------------------------------
一昨日、11月16日[木]をもって、7階ギャラリーの『西雅秋-彫刻風土-』展を終了しました。(本館1F周辺の展示は27日まで継続します)
西さんの作品は、サイズ、重量ともに大きな金属彫刻が中心のため、本学での滞在制作や展覧会設営には多くの困難が伴いましたが、大勢の学生スタッフに支えられ、タイトな準備日程ながら、当初の作品プランのスケール感を損なうことなく展示し、無事期間を全うすることができました。
本展運営にあたり、学生への周知や機材の貸し出しなどでご協力いただいた関係者の皆様には心より御礼申し上げます。ありがとうございました。
今、西さんは上海での『〈With Sword〉Contemporary Art Exhibition(http://www.jingart55.com)』参加のため、山形で制作したシリコン型とともに中国に滞在しています。現地では7Fで展示されていた『デスマッチ-山形-』の中国バージョンを制作しているとのこと。
会場の撤収にあたって西さんは、作品『デスマッチ・山形』や『バルチック・テイスト』で積み上げた数百個にもおよぶ石膏パーツを「皆で分け合って、持ち帰ってほしい」との伝言を残して山形を去られました。
その旨、掲示やメールで周知したところ、16日の夜には大勢の方が拾いに集まり、大学の同僚たちも『バルチック・テイスト』のテーブルから西さんがバルト海沿岸諸国で収集したレーニンやスターリン、マルクスの石膏胸像を持ち帰っていきましたが、これらが事務局のデスクに並んでいる景色を想像してちょっと心配になりました。(笑)
人々が石膏の瓦礫の中から、めいめい気に入った石膏片を大事そうに箱や紙袋に詰めていく姿を眺めながら、僕はミレーの『落穂拾い』や、熊谷守一の『焼き場の帰り』といった絵画作品とその絵の背後にあるストーリーについて考えていました。家々に散らばっていったこれらのカタチたちは、棚や、机の上や、引き出しの中で、ゆっくりと時間をかけて、石膏の欠片に、カタチなき存在に還っていくことでしょう。
『彫刻風土』展制作にかけた西さんとスタッフの一ヶ月間は、最後には、いくつかの小さなダンボール箱に収まってしまいました。
****
さて、もっとも大きな規模で展開した能舞台『伝統館』における西さんの彫刻作品についても、説明しておかなければ。
池に浮かぶ水上の舞台に、西さんが葉山の老漁師から譲り受けたという2艘の木造船(各5m)が置かれ、その中に石膏製の二宮金次郎像、卵、木魚、金精さま(木製の奉納男根)、砲弾、弁財天の頭、連座、梵鐘がたくさん積み上げられています。
オープン当初には整然と能舞台への渡り橋に並んでいたこれらの石膏像が、10月30日[月]の朝には、すべて木造船に暴力的といってもいい荒々しさで投げ込まれていたのですが、これは10月28日[土]の夕刻、『彫刻風土-時の溯上-』と題したパフォーマンスにおいて、西さんの彫刻と森繁哉教授の舞踏がコラボレーションした結果の景色なのです。
表現領域は違えど、里山に生き、その土地の風土と向き合いながら制作を続けるお二人の出会いは、今回のプログラムなかでももっともスリリングな空間を創出しました。
「西さんの作品は鑑賞するのではなく体感する作品だ。本番では観客席を排してお客さん自身も作品の中に取り込んでしまおう」という森繁哉教授の強い提案によって、公演当日は桟敷席を使用せず、133名の観客全員が「能舞台」に上がり、至近距離で西さんの彫刻と、森さんの舞踏の出会いに立ち合ったのでした。(公演の記録映像を、エントランス北側のプラズマテレビで27日まで放映しています)
頭からつま先まで真白な装いの森さんが舟から這い出して踊っていくにつれ、舟に満載された石膏像の白い小山は徐々に崩れていき、そのうちいくつかの欠片は、能舞台からこぼれ落ちて周囲の池に沈みました。路肩に積み上げられた小象ほどの山形の寝雪が、春の日差しを受けて徐々に溶け出し、路面を這って大地に染み入って消えていくように。
クライマックスでは、池に飛び込んだ森さんが、四国は足摺岬から黒潮に放たれた桂の大木(『colonist』の記録映像)に導かれるように、冷たい水の上をゆっくりと東へと進み、薄暮から漆黒へ、蔵王丘陵の夜の訪れとともに幕となりました。
大きな拍手とカーテンコール、感極まった西さんが森さんを抱えて石膏の中に一緒に倒れ込むというハプニングもありました。
この公演の前にこども劇場で開催されていたシンポジウム『神秘の樹と明日の鳥たち-詩・旅・思索-』で、1人の学生が「土地や風景から受ける神秘的な印象や体験を、どのように理解し消化すればいいのでしょうか」と質問したのに対して、詩人の吉増剛造氏が「イングランドには〈ghosty/ゴースティー〉っていう表現がある。的を得た、いい言葉だと思いませんか」と答えておられましたが、「奇跡のような一日」(※吉増氏談)となったこの夜の能舞台周辺は、まさに「Ghosty Night」と形容してもいい、この世の光景とは思えない場となっていました。
****
石膏の粉に塗れていた7階ギャラリーでは、撤収と念入りなクリーニングによって元通り完全に〈empty〉な空間に戻り、今日からはまた、新しい展覧会『助手展2006』がはじまっています。飯能のアトリエに戻された彫刻群は、また土中に埋め戻され、次の展示機会までの束の間の眠りにつくことでしょう。
美の殿堂として名高いルーブルに展示されている名画や古代エジプトの彫像も、見方を変えると死者たちの視覚や触感の残像という、ある種の「幽霊的な存在」を眺めていると言えます。
そういう、近代以降の芸術作品や美術館における「永遠」の思想そのものに、批判的でいることが彫刻家・西雅秋氏の作品の本質なのだと、撤収を終えて、あらためて気付かされたのでした。
宮本武典/美術館大学構想室学芸員

|
■写真中:隣の教室では石膏の鋳込み作業を継続中。原型となるのは、朝日町のワインや林檎、冬瓜、この廃校に残されていた郷土玩具など。石膏に写し取られた「朝日町のカタチ」は、隣の教室に運ばれ、記憶の断片に組み込まれていく。
■写真下:廊下には西さんの棲む里山(埼玉県飯能市)で同様に廃校になった小学校におかれていた二宮金次郎像が佇んでいました。台座には古い鉄製の金庫が使われています。
--------------------------------------------------------------------------
大地に落下した『CASTING IRON』が朝日町立木地区を賑していた一方で、旧立木小学校の校舎の中では、西雅秋さんと本学建築・環境デザイン学科生との共同制作による展覧会『彫刻風土-ASAHIMACHI'06-』が静かにオープンしていました。
学生たちと西さんが連夜の話し合いの末、生み出した作品は『余韻』。これは、オープン・スタジオ形式をとり、参加した学生一人一人が「家族・学校・記憶」の語り部となり、石膏のフィギアを用いて自らの物語を、円の中で「箱庭」のように客体化していく、というものです。
けれども、その小さな石膏像による箱庭は、次の語り部に移る前に取り外され、後には置かれていた「カタチ」の関係図が、失われた記憶の影のように、雪の模した石膏の粉によって教室の床にトレースされていきます。
取り去られていない石膏像は、語り部が「失ってしまいたくない」としてあえて残したもの。語りの内容は黒板に詳細に記述されていきますが、そのはじまりに西さんは「円の中心には、決してかえることはできない」と、くっきりと書いていました。
山形の展示会場では骨のような、軽く、鋭利な印象だった石膏は、ここではふわりと軽く、柔らかく空間に積もっていて、西さんは「何だか少し女性的で自分の作品じゃないみたいだ」と語っていましたが、廃校の教室で眺めるこの作品は、どこか哀しく、美しく、僕はとても好きでした。
作品は10月29日から雪が降り始める今月後半(11/27)まで展示されています。紅葉狩りを兼ねて、是非、朝日町立立木小学校を訪ねて、作品『余韻』の成り行きを見届けてください。
宮本武典/美術館大学構想室学芸員
(アクセスに関して詳しくは→http://www.tuad.ac.jp/asahi-a-gakko/)

|
写真中:落下直後、地面に沈み込んだ鋳鉄のまわりに集まる人々。
写真下:人々のざわめきが去った後、鉄は静かに校舎を背にして秋の広場に佇む。
--------------------------------------------------------------------------
5tの鉄塊が空から大地へ舞い降りた日、10月29日・日曜は西雅秋さん60歳(還暦!)の誕生日でした。
西さんは「日本では人間は60歳を過ぎるともう一度子どもに還るんだ」といってこの大胆な作品『CASTING IRON』の公開設置におおいに意欲的で、かの5tの鉄塊は、林檎とワインで有名な山形県朝日町の小さな廃校で、彫刻家の無邪気な「生まれ変わりの儀」を祝うために、福井県金津市の公園から掘り出され、140名の人々に見守る中、苔むした雪国のグラウンドに着地しました。
この日は午前中から25tクレーンがけたたましい音を立てて鉄板を敷いたり、続々と車で乗りつけてくる学生たちがグランドで童心にかえり、奇声をあげて走り回ったりして、普段は静かな地区は非日常の喧騒に包まれましたが、「何事か」と散歩ついでに様子を見に来るお年寄りの皆さんは意外に好意的で、あるお婆さんは、僕と西さんが「すみません、今日はちょっとお騒がせします」と声をかけると、農作業の手を止めて、立派な白菜をくださいました。
このプロジェクトの実行にあたっては、立案当初から朝日町役場や立木地区の方々にご心配をおかけし(何しろ破壊の先入観が強い作品なので、、、)当日は周辺地域の方々の反応が懸念されましたが、実際はご年配の方々から子どもたち、役場の方々、朝日町長さんまで、実に沢山の地元の方々にお越しいただきました。
落下予定時刻の30分前には、人々が学校に集まりはじめ、巨大なクレーンと不穏な鉄のカタマリを遠巻きに眺めています。
若干ぎこちない雰囲気の中、旧立木小学校を根城に作家活動を続ける若きアーティスト集団「あとりえマサト」の板垣敬子さんが、ぬけるような爽やかな秋晴れのもと進みでてマイクを握ると、落下ポイント近くのグラウンドに自然に人々の輪が生まれ、さながら収穫後の秋の田んぼで催される村祭のような恰好になりました。
板垣さんからマイクを手渡された町長さんがおっしゃるには「こんなに大勢の若い人たちが、この立木地区に集まったことは、ここ十数年、久しくなかったことでした」とのこと。話をしている間にもひっきりなしに学生たちの車が到着「やれ、まだ落ちていないぞ、間に合った」と小走りで集まってきます。
さて、その落下の瞬間。
衝撃は足下に伝わるというよりも、楔を打ち込まれたような感覚が、視覚的インパクトを通過してみぞおちに「溜まる」感じで、しばらくのあいだ体内にとどまっていました。
少し高台の方から観ていた人は「瞬間、地面が液状化現象のように波打った」といい、近くで寝転んで観ていた人は「ズンという振動がダイレクトに伝わった」と語り、必死でカメラをかまえていた人は「ファインダー越しではなく、撮影をあきらめて直接観ようかと迷っているうちに落ちてしまった」と悔しがっていました。
思わず「あーっ!」と声を上げた人、笑い声をあげた人、衝撃に眼を見張らせたままの人、感動して涙をこぼした人・・・反応は千差万別でしたが『CASTING IRON』が生み出した振動は、そこに立ち合った約140人の身体に、忘れ難い記憶として刻み込まれたに違いありません。
「集まってくるときは無表情で、帰っていくときは満面の笑みだった」というのは、駐車スペースの交通整理に奔走してくださった『あとりえマサト』メンバーの版画家・三浦さんの談。
西さんの奥さん、お母様、2人の息子さんとそれぞれのパートナーが、この記念すべき瞬間を祝うため東京から集まり、前日のシンポジウムで司会を務められた酒井忠康先生も息子さんと娘さん同伴で朝日町まで足を伸ばされました。
様々な立場と世代の人々が、たった5分間の「鉄の落下」ために小さな谷間の広場に集まったという事実が、感動的というよりも、平穏で懐かしい、昔話の一場面のように思われたのでした。
宮本武典/美術館大学構想室学芸員
↓大学HPに『西雅秋-彫刻風土-』展ボランティア・レポートが掲載されています!
http://www.tuad.ac.jp/community/backnumberfiles/06-10/special/special.html

|
■写真下:蔵の夜は舞踏家の森繁哉教授、『BT美術手帖』等で活躍されているライター白坂ゆりさん、彫刻家の古郡弘さんを交えて更けていった。
--------------------------------------------------------------------------
10月28日土曜日の夕刻、『西雅秋-彫刻風土-』展とのタイアップ企画として、美術館大学構想室主催のシンポジウム第2回『神秘の樹と明日の鳥たち-詩・旅・思索-』が「こども劇場」で開催されました。
この企画は、毎回、各界の知の先達をお迎えし、座長の酒井忠康世田谷美術館長の司会のもと、ジャンルに限定されない即興的かつ横断的な「語り」によって、東北の風土のもつ豊かな文化的土壌を描写していこうとするものです。
昨年のシンポジウム『ことばの柱をたてる』にお招きした建築(史)家の藤森照信先生は、ベネチア・ビエンナーレ建築展2006日本館のコミッショナーとして活躍され、ますますお忙しそうです。(さきに『HOME』誌別冊として出版された『ザ・藤森照信』には、酒井先生がエッセイ『藤森照信氏の横顔』を寄稿され、文中「去年の秋、東北芸術工科大学で芳賀徹氏をまじえて諤々のシンポジウム〜」との記載がありました)また芳賀徹先生(京都造形芸術大学学長)は、お会いするたび「君、あの時の鼎談は楽しかったね、またやろうよ」と声をかけてくださいます。
3者の語りは、粋、というか軽みがあって、それでいて骨太な、研究室に籠っているだけでは得ることのできない、様々な土地の雨風にまみれ、靴に埃を積もらせて歩き続けた人の「大地の知恵」を感じさせるものでした。
そのユーモア溢れる知的な丁々発止は、本HP内アーカイブ『ことばの柱をたてる』の項でPDFファイルにて閲覧できます。
***
そして今年『神秘の樹と明日の鳥たち』のゲストとして、詩人の吉増剛造先生に本学にお越しいただきました。学内からは民俗学者の赤坂憲雄教授、座長は昨年に引き続き酒井先生です。
私事ですが、僕はかつて吉増先生が武蔵野美術大学の研究誌「季刊・武蔵野美術」(本学図書館に蔵書有)の巻頭グラビアにおいて、彫刻家の故・若林奮氏と共同執筆されていたテクスト『緑の森の一角獣座』に、はじめて芸術のなかの言葉を見いだした美大生でありました。以来、その詩のみならず、吉増先生が漂白の旅の中で記された銅板や写真(今回も鼎談の最中にカメラを何度も手に取られていました)にも、多大な影響を受け続けています。
吉増先生はポエトリー・リーディングの活動でも知られていますが、これまでなかなか参加する機会に恵まれず、いつもテレビモニターの中で写真家のアラーキーや、ジョナス・メカスなど、21世紀の眼の巨人たちと共にニューヨークや東京の路地を彷徨う、その筆跡に似た細身のお姿だけを拝見していました。
何年か前、東京国立近代美術館「ブラジル・ボディ・ノスタルジア」展での吉増先生の特別講演も、この時釧路から上京して同行していた友人の飛行機の時間と折り合いが合わず聞き逃したのです。
それだけに、今回の企画準備の過程で、初めて吉増先生から手書きのFAXをいただいたとき、あの独特の筆致で書かれた「宮本様」との宛名を見ただけで手が震え(ミーハーですみません)ました。吉増先生が「つばさ号」で山形駅に降り立たれた時には、出迎えの際の目印にと前もって伝えられていた「クタッとした茶色のジャケット」を追うまでもなく、改札をくぐってこられる吉増先生の姿を遠くから確認できたのでした。
茶色のジャケットの内ポケットには、細身のカラーペンが十数本、ぎっちりと並んでいて、これが「クタッと」の正体。吉増先生は、これらのペンを用い、山形新幹線の車中で、シンポジウムのために精緻な細い文字の連なりから成る「新聞」をお書きいただき、この日、集まった人々への手土産として手渡され、シンポジウムの中で詠み上げられたのでした!
前回のシンポジウムのテーマは『美術館大学』の「柱」を豪快に「ぶちあげる(酒井先生談)」こと。今回のテーマは「樹」ですから、地中深く、また天高く、大気や大地の滋味を吸い上げる、実にゆったりとした、心地よい「語り」の場になりました。とても洗練された読書会に招かれたような120分のシンポジウムが活字になるのは、来春の予定。行間からこぼれ落ちるはずの、詩的エッセンスにご期待ください。
宮本武典/美術館大学構想室学芸員

|
写真下:宴の後。参加した人々のカタルシスが白い粉となって作品に定着した。
--------------------------------------------------------------------------
11月5日日曜の早朝。既に山形からの帰路・東北道を走っている筈の西雅秋さんから思いがけず電話が入り「ちょっと窓から顔を出してみなよ」との呼びかけに応じて3階の部屋から慌てて視線を落としてみると、そこには一緒に山形じゅうを駆け巡ったダットラと、缶コーヒー片手に、いたずらっぽく笑う彫刻家の姿がありました。
紅葉燃え立つ朝日町旧立木小学校でのオープン・スタジオ終了後は、山形市には寄らずに、まっすぐ飯能の工房に帰る予定を遠回りし、西さんは妊娠後あまり経過のよくなかった家内の具合を心配して、大学近くの僕のマンションに来てくれたのです。
そして、かの地では地元の猟師さんたちとの連日の交歓で、熊や鹿、キジや猪、果てはダチョウまで、野趣に富んだ肉ばかリ食べさせられて腹の調子が悪いよと語りつつ、活力あふれる声で、弱気になっていた僕たち夫婦を励ましてくれたのでした。(家内と西さんの息子さんは、偶然にも同じ大学、同じ学科の同級生なのでした)
***
彫刻家・西雅秋さんをお迎えして、連日100名を越える観客とともに進行した『西雅秋-彫刻風土-』展にまつわるプログラムも、彫刻家の次なるプロジェクト(11/19〜上海)への旅立ちとともに、熱を失ってしまいました。
けれども7階ギャラリーには彫刻家の格闘の残骸が散らばり、能舞台には2艘の舟が座礁し、朝日町の廃校には白い輪と、地表に沈み込んだ5tの鉄塊が、そこで何がおこなわれたのかを静かに語っています。
彫刻家が去っても、これらの遺物を頼りに、彼がこの地で何を造り、壊していったのか、そのアクションを想像することはできます。
10月24日から10月29日にかけて、西さんが用意したいくつかの神話的な光景に、毎回多くの人々が立ち合いましたが、この大学の総学生数は2000人です。目撃することにできなかった多くの学生諸君の為に、これより4回に分けて、このブログで補足説明をしていきたいと思います。
***
上の写真は10月24日夜に7階ギャラリーでおこなわれた非公開パフォーマンスです。山形での西さんの制作をサポートした学生・教職員約60名が、「彫刻の宴」に招かれ、作品『デスマッチ・山形』の「最後の仕上げ」に参加しました。
かつて養蚕に使われた藁の平籠に、西さんが山形滞在中に収集した野菜や果実、郷土玩具や、仏像やコケシ、金精様など信仰の造形が石膏で鋳抜かれ、「カタチ」に込められたさまざまな意味が渾然一体となって積み上げられています。
まるで巨大な亀の甲羅に盛られた古代インドの世界観のような、神聖さとキッチュさの共存する不思議な塚が7つ、ギャラリーの床に築かれ、招待客がそのまわりに円座を組みました。
西さんの「乾杯!」の合図とともに山盛りの石膏が次々と砕かれていきます。
歓声と、耳をつんざく破壊音が5分間響き渡って、再び西さんの「終わり!」との掛声が響き、一同が拍手のともに退場すると、その後には粉々になった石膏片が、恐いくらい静かな緊張感を、白い澱のように空間にたなびかせていました。
永遠に属する彫刻ではなく、一瞬の魂の高まりに懸ける「彫刻」への熱狂。
駅前や公園に立つ、厳めしい政治家の銅像や、ぬるりとした裸婦像や、金ぴかのモニュメントにおける「彫刻」とは明らかに異質で、むしろ伊勢神宮や、沖縄の御嶽、竜安寺の石庭にも通じる「なにも置かない」ことをギリギリまで研ぎすました、この国の文化でもっとも上質な地霊(ゲロウス・ニキ)へのアプローチを感じました。
彫刻家としては異端な、その感性が存分に発揮された、西さんによる初日のイベントでした。
その後は宮島達男副学長が(本物の)一升瓶を差し入れてくださり、しみじみと乾杯。秘密の宴は、その夜遅くまで。
宮本武典/美術館大学構想室学芸員

|
■写真下:水上能舞台のアプローチに整列する石膏製の二宮金次郎像。原型は彫刻家のアトリエがある埼玉県飯能市の廃校に立ってたものだそうです。斜めに立てかけているのはある神社に奉納されていた子宝祈願の金精様を型取りしたもので、その他、不発弾や仏頭、蓮座など、聖俗・性死にまつわる象徴的なカタチがズラリと整列し、28日17:30、舞台上で森繁哉教授の舞踏『時の溯上』とともに一気に積み上げられます。

|
--------------------------------------------------------------------------
このブログは大学からの帰宅途中、24時間営業のドトール・コーヒーで書くことが多いです。あのひっきりなしに呼び出しの電話が響くオフィスでは、到底向き合うことはできない自分自身と語り合う、僕にとって貴重な時間です。
1年間過ごしたパリでは、日中は失語症のように黙々といくつかのカフェをi-Bookとともにハシゴし、深夜のメトロで撮影した画像データ(上写真)を編集したり、小説らしきものを書いて過ごしました。
僕のことを最後まで中国人だと思い込んでいたインド人のギャルソンが仕切るカフェ『緑の象』で、「世界」は解決不可能なぐらい複雑で、一人一人が孤独で、それでいてはっきりと人と人が求めあう引力のようなアートの作用を信じることができました。「人が生きていくために、アートは必要なのだ」と、いつも感傷的に思ったものです。
自転車で漆黒の蔵王の丘を駆け下りていく家路の途中で、ついついコーヒーを飲みにいってしまうのは、あの無為な日々の概視感を求めてのことです。
***
このところ、打ち合わせの数が膨大なのです。
学生に、同僚に、アーティストに、上司に、朝から晩までとめどなく何かを説明し、その正当性を主張し、主張を覆され、企画書で挽回し、書いたからには実現のために具体的に実働をはじめる頃にはその他の「正当性」が頭をもたげ、、、一週間が運動会の50メートル競争のように過ぎていきます。与えられた職業的クエストを一つ一つ解決するためにのみ生きているかのようです。
かえってこのごろは「世界」がすべてシンプルに見えてくる。力の構造、あらゆる組織に組み込まれるヒエラルキーの骨格、これらをトレースするように与えられた仕事をスムーズに処理していき、そうして徐々に自分の感覚的な世界を失っているように感じてしまいます。
だから、今年の「I'm here.」で出会った岩本あきかずさんや、坂田啓一郎さんといった同世代のアーティストたち、そして西雅秋さんの作品に刻まれた、静かで確かな痕跡を見て、僕は僕自身が失ったものの疼きを感じずにはいられません。
机に向かって、ただまわってくる書類を左から右に流しているだけでも、人は生きていける。そういう安泰な場所から、厳しい現実の中で制作を続ける彼らに憧れを表明している自分に救いのないエゴイズムを感じつつも。
世界はとても謎めいていて、単純な「力」の行使だけでは、決してボジティブな解決には至らないことを再認識するために、僕は仕事帰りに13号線沿いのドトール・コーヒーに立ち寄ります。
深夜の店内には、いつも同じ顔ぶれ、学生のH君やK君がいます。(アルバイトスタッフも、みんな芸工生です)彼らはカフェテーブルを抱きかかえるように身を屈めて、スケッチブックにいったい何を書き付けているのでしょう?(あるいは「宮本さんはしょぼくれた目と無精髭をコスリコスリ、パソコンに何を打ち込んでいるのだろう?」)
「今は近視眼的な学生たちの世界地図が、これから現実のひろがりへとつながっていくように、僕がこの大学でやるべきことは何か?」
ここで感じることのできるそんな不遜な使命感もまた、明日を頑張れるエネルギーとなります。僕も彼らと同じように、相変わらず、同じ私的世界を堂々巡りしているだけなのかも知れません。これは希望的観測ですが。
『西雅秋-彫刻風土-』展開催まであと10日です。サポートする側のポテンシャルが試されるのはこれから。「秋の夜長」に頼る日々が続きます。
宮本武典/美術館大学構想室学芸員
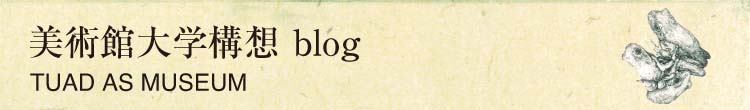




■写真下:栃木県立美術館の収蔵庫にて、本学の文化財保存修復研究センターが修復を受ける作品について打ち合わせ。彫刻の修復家として活躍する藤原徹教授(左)と、栃木県美学芸員の木村理恵子さん(右)。中央には舟越桂氏の初期の傑作「風をためて」と、奥にはイギリス現代美術の巨匠デヴィット・ナッシュの無骨な木彫群が見える。いずれも秋に芸工大で公開予定。
----------------------------------------------------------------------------------
芸工大周辺に植樹されている細身の「大山桜」は、見頃は過ぎたものの、キャンパスにはまだ少し桜色の余韻が漂っています。暖冬の影響か、ずるずると冷気を引きずっている山形では、未だに上着なしでは朝夕は辛いですが、学食の混雑と、新入生たちのフレッシュな装いに、すっかり卒展後の憑き物が落ち切った「春」を実感する毎日です。大学に残った僕たちも、再出発です。
さて、デザイン工学部に新しく着任された先生方の仕事を紹介する展覧会『New face at TUAD』が、先週クローズしました。マルチに活躍するアーティスト・中山ダイスケさんや、写真家・屋代敏博さんの教員就任は、コンテンポラリーアート界ではちょっとしたトピックスであるはずですが、肝心の芸工大関係者(学生+職員)がその事実に気がつくのはもう少し先でしょうか。
7名の先生方は、とても意欲的にショーに参加していただきました。学生の関心も高く、学内向けの展示のわりに、2週間で約1,700名の入場者数を記録しました。地元メディアの取材も多くて、僕も簡単な解説を依頼され、2回もテレビ出演しました。昨年、ちょうど同じ時期に松本哲男学長の大規模な個展『松本哲男展-鼓動する大地-』を開催し、こちらも大好評だったので、新春の「顔見せ」的企画展は恒例になりそうな予感です。
****
今年度も美術館大学構想室は様々なプロジェクトに挑戦します。4月一杯は、出展交渉とスケジュール調整のため日本各地を飛び回っていました。2007年度のラインナップがほぼ確定してきたところで(詳細はおいおいメインHPにUPしますが)ここで、ここ最近の動きと年間のコンテンツを数回に分けて紹介しておきます。
まずは今年一番の目玉から。
----------------------------------------------------------------------------------
【4月10日東京・西村画廊】
日本橋の老舗現代美術ギャラリー西村画廊へ。秋の企画展にお招きする彫刻家の舟越桂さんと、美術館大学構想プロジェクトリーダーの酒井忠康先生、そして西村健治社長とミーティング。西村画廊でアルバイトをさせていただいたのはムサビ院生時代で、もう10年以上も前のことです。その後、4年間を過ごしたタイのバンコクでは、ギャラリー所属作家の小林孝亘さんにお世話になって、そして今、こうして「仕事」として西村社長にお会いできることに不思議なご縁を感じてしまいました。
舟越桂さんには、本プロジェクトの主旨(学生への教育的還元/地域に開かれた大学づくり)に共感いただき、「アイデンティティーの追求」をテーマに、なんと現在制作中で、2008年2月にNYのグリーンバーグギャラリーで発表予定の国内未発表作品5点を、先駆けて山形で出品してくださることになりました。そこにさらに、栃木県立美術館所蔵の初期の代表作2点と、作家所蔵の近作を加え、彫刻作品12〜15点の展観となります。この展示は、12月に京都造形芸術大学ギャラリーオーブにも巡回しますよ。
『舟越桂展 -他人の顔-(仮称)』
会期:2007年10月12日[金]〜11月10日[土]
開館時間:10:00〜18:00(会期中無休/入場無料)
会場:東北芸術工科大学7Fギャラリー
****
それから、オレンジ色の高尾行中央線快速に乗り、西荻窪のカフェで、グラフィックデザイナー立花文穂さんにお会いする。立花さんには今年度のアーティスト・イン・レジデンス招聘作家として、山形で滞在制作をお願いするとともに、『舟越桂展』のグラフィックワークも手がけていただけることになりました。立花さん、舟越さんという魅力的なカップリングが実現するのなら、ついでに何か実験的なアートブックが出版できないかと、赤々舍代表の姫野希美さんと思案中。こちらもご期待ください。
『TUAD ARTIST IN RESIDENCE PROGRAM 2007 -立花文穂-』
期間:2007年10月12日[金]〜11月11日[日]
会場:東北芸術工科大学図書館2Fガレリアノルド
----------------------------------------------------------------------------------
【4月16日:栃木県立美術館へ】
保存修復学科の藤原徹教授とともに栃木県立美術館へ。文化財保存修復研究センターが修復を依頼された3点の彫刻作品の現状調査に同行しました。学芸員の木村恵理子さんにご案内いただき、休館中の館内を行ったり来たり。
栃木県美は今年収蔵庫の耐震補強工事を実施するため、工事期間中は、修復を受ける作品だけではなく、その他の彫刻もセンターの収蔵庫に預かることになりました。収蔵庫で舟越桂さんの初期の代表作2点に遭遇し、10月の舟越展と奇跡的なコミットが決定! そして、僕が敬愛してやまないデヴィット・ナッシュのコレクションも預かることになり、秋の展覧会は国内外の優れた木彫作品が山形に集まることになりました。
『栃木県立美術館所蔵彫刻コレクション展』
日時:2007年10月12日[金]〜11月11日[日]
会場:東北芸術工科大学図書館スタジオ144+ガレリア・ノルド、文化財保存修復センター4階展示室
出展作品:アンディー・ゴールズワージー(英)/神山明/清水九兵衛/デヴィット・ナッシュ(英)/ニアグ・ポール(英)/戸谷成雄/深井隆/ユン・ソンナム(韓)etc.
宮本武典(美術館大学構想室学芸員)