���

|
�����Ԥdz�ư���Ƥ���֤����Ʋ�פ���κ��ʤǤ���
������ٹ��Ϲ��ͻ����Ⱦ�����ܤ�ȤˤĤ�����ή����ν����μ�ˤ�äơ���ʪ�˻Ȥ�줿�Ĥ��ۤ�˥����碌�ơ��֤�Ļ��ưʪ���ͷ��ʤɤ����줿����ΤҤ�ܤ�ۤɤ��礭���ʤ��顢����¿�����ޤˤʤäƤ��ơ����ޡ����ᡢ���������ʤɤȤ��ư��Ѥ��줿��
�������������������������������������������¤�ͷ�ӡ�������ٹ���ͺ�ܼҤ��
��������������������������������������������������



|
�����Ԥdz�ư���Ƥ���֤����Ʋ�פ���κ��ʤǤ���
������ٹ��Ϲ��ͻ����Ⱦ�����ܤ�ȤˤĤ�����ή����ν����μ�ˤ�äơ���ʪ�˻Ȥ�줿�Ĥ��ۤ�˥����碌�ơ��֤�Ļ��ưʪ���ͷ��ʤɤ����줿����ΤҤ�ܤ�ۤɤ��礭���ʤ��顢����¿�����ޤˤʤäƤ��ơ����ޡ����ᡢ���������ʤɤȤ��ư��Ѥ��줿��
�������������������������������������������¤�ͷ�ӡ�������ٹ���ͺ�ܼҤ��
��������������������������������������������������

��ǯ�����������7��19���ʲСˡ���������7��28�����ڡˤǤ���
���Ѵ��֤��8��Τ��߲�ޤǤ����Ѥʺ�����ͽ�ۤ���ޤ���
���Τ��ᡢ�ޤ��Ȥ˾���ʤ���
7��16�����ڡˤ��8��21���������ޤǤ�
���ʽŤΤߤΤ����Ȥ������פ��ޤ���
������������ñ����������������������˾�Τ����ͤϡ�
�����ޤǤ�ͽ�������ޤ��褦���ꤤ�����夲�ޤ���
����������ꤤ�������ޤ�
���Ѵ��֤��8��Τ��߲�ޤǤ����Ѥʺ�����ͽ�ۤ���ޤ���
���Τ��ᡢ�ޤ��Ȥ˾���ʤ���
7��16�����ڡˤ��8��21���������ޤǤ�
���ʽŤΤߤΤ����Ȥ������פ��ޤ���
������������ñ����������������������˾�Τ����ͤϡ�
�����ޤǤ�ͽ�������ޤ��褦���ꤤ�����夲�ޤ���
����������ꤤ�������ޤ�

|
�����Ԥdz�ư���Ƥ���֤����Ʋ�פ���κ��ʤǤ���
������ٹ��Ϲ��ͻ����Ⱦ�����ܤ�ȤˤĤ�����ή����ν����μ�ˤ�äơ���ʪ�˻Ȥ�줿�Ĥ��ۤ�˥����碌�ơ��֤�Ļ��ưʪ���ͷ��ʤɤ����줿����ΤҤ�ܤ�ۤɤ��礭���ʤ��顢����¿�����ޤˤʤäƤ��ơ����ޡ����ᡢ���������ʤɤȤ��ư��Ѥ��줿��
�������������������������������������������¤�ͷ�ӡ�������ٹ���ͺ�ܼҤ��
��������������������������������������������������

�����������ΤҤȤĤˡַ˧���ڤΤ�������פ�����ޤ���
�ڤ������ԤǤ����л�����ϡ��������ա��ɶ���β������Ǥ⤢�ꡢ
�¤������ˡ�˴ְ㤤�Ϥ���ޤ���
���ξڵ�˽��ߤ��ޤä����ʤ��������Τ�Τ�̣��ڤ��ळ�Ȥ��Ǥ��ޤ���
���ڤο�������˶�̣���äƤ�ä����Τ�ī����ʹ�Ҥ���Ǥ���
�ֽܤΰ컮�Ȥ줿�ƥ쥷�ԡפȤ�������ý�����ǡ���Ź��Ҳ𤷤Ƥ��������ޤ�����
�����Ԥδ餬�����뿩����������äƤߤ褦���Ȥ������Ǥ���
�ڤ���ַ����Τ��ޤߴ�ǽ
�ڤ������ԤǤ����л�����ϡ��������ա��ɶ���β������Ǥ⤢�ꡢ
�¤������ˡ�˴ְ㤤�Ϥ���ޤ���
���ξڵ�˽��ߤ��ޤä����ʤ��������Τ�Τ�̣��ڤ��ळ�Ȥ��Ǥ��ޤ���
���ڤο�������˶�̣���äƤ�ä����Τ�ī����ʹ�Ҥ���Ǥ���
�ֽܤΰ컮�Ȥ줿�ƥ쥷�ԡפȤ�������ý�����ǡ���Ź��Ҳ𤷤Ƥ��������ޤ�����
�����Ԥδ餬�����뿩����������äƤߤ褦���Ȥ������Ǥ���
�ڤ���ַ����Τ��ޤߴ�ǽ

|
�����Ԥdz�ư���Ƥ���֤����Ʋ�פ���κ��ʤǤ���
������ٹ��Ϲ��ͻ����Ⱦ�����ܤ�ȤˤĤ�����ή����ν����μ�ˤ�äơ���ʪ�˻Ȥ�줿�Ĥ��ۤ�˥����碌�ơ��֤�Ļ��ưʪ���ͷ��ʤɤ����줿����ΤҤ�ܤ�ۤɤ��礭���ʤ��顢����¿�����ޤˤʤäƤ��ơ����ޡ����ᡢ���������ʤɤȤ��ư��Ѥ��줿��
�������������������������������������������¤�ͷ�ӡ�������ٹ���ͺ�ܼҤ��
��������������������������������������������������

|
�ۥƥ륪���̥ޤβ���ή�졢��Ź�˿��Ϥ褤�����餮��ʹ�����Ƥ���ޤ���
���θ���λ�������������ζ���ؤ�³�����Ǹ�����̤ξ���������ˤ֤Ĥ���ޤ���
�ۤȤ�ɰ�ľ����ή��Ƥ�����ϡ�������ľ�Ѥ˶ʤ��ꤵ��ˤ⤦���ٶʤ���ޤ���
����η��Ƥ���ΤǤ���
��Į�Ϸ��Ф����뤿�ᡢ��������ϸ����ܤ�����Ȼפ��ޤ���
���Τ��������̤ˤ������ФϤȤƤ��礭����������ɤ��Ǥ���ΤǤ���
��Ź�ǻ��Ѥ��Ƥ�����ϡֹȵ���ʤ��������ˡפǤ���
�����������������������ˤ���Ƥ���˥�ȥ꤬�����������Ǥ��Τ�
�¿����ƿ��٤��ޤ���
�ֹȵ���פϥ⥹�С������Ρ־�̣�ץ�����˺��Ѥ���Ƥ��ޤ���
���������ꥢ���������ǰ¿��ʿ���Ǥ���Ȥ����ڵ�Ǥ��͡�
����礻
������¼��������ٻ��ʤ����ޡ�3135
¼����Ť���������
������������������������������������������������������������
1000�ߥС������ɤ��̣
�֥⥹�С������פ�Ÿ������⥹�ա��ɥ����ӥ���16�����ϥ�С�������������Ǥϻ˾�ǹ��ͤ�1000�ߡ��ǹ��ˤι��ϥ�С������֥˥åݥ�ΥС�������̣���ʡפ����Ф���
����ñ���Υǥե췹���˻��ߤ������ڤ껥�פȤ��Ƴ�ȯ����Ʊ�Ҥϡֻפ��ڤä����ʤ�������ʬ�����Ǥ��פ�PR���롣
��03ǯ8���ȯ�䤷�Ƥ���־�̣�ץ��������4�ơ��������ͤ����ѥ�ȹ뽣���������ȥޥȡ��쥿�����١�������ʤ�10������Ǻ��Ťͤ��١����å��С������ǡ�������10����������Τ���ʸ����10ʬ�ʾ夫���롣
�ֺǹ��ʰ̡פΰդ����ơֽ��ʡפ�̾�դ����������ʤϺǶ�����������Х⥹����300Ź�˸¤ä�1��10�������ȯ�䤹�롣
���������ȤǤ�90ǯ���Ⱦ��������ʲ����ʤߡ��ϥ�С��������������ܥޥ��ɥʥ�ɤ����ȯ�䤷��59�ߤΥϥ�С��������֥ǥե�ξ�ħ�פȸ���줿���⥹�ϡ�æ�ե����ȥա��ɡפ�ᤶ���ƴ�¸Ź���鴶�Τ���Ź�˲��������Ȥ���Ƥ��롣
ī����ʹ����2005.3.16��
������������������������������������������������������������
1��1000�ߡ����С�����
---�ܸ�����ʤ�10�������꿩�����---
���ϥ�С������������⥹�С�������Ÿ������⥹�ա��ɥ����ӥ���15����1��1000�ߤΡ֥˥åݥ�ΥС���������̣���ʡפ�16���������Ź�ޤ�ȯ�䤹���ȯɽ����������Ǥϻ����ԡ�ŷƸ�ԡ������ԤΣ�Ź�ǰ�������Ź�ޤ����꣱��10�Ĥθ�������ǡֲ��ʤ˸��礦�ʼ������������פȼ�����Τ������Ƥ��롣
���ֽ��ʡפ���Ļ�˰����ʱ¤�Ϳ����줿����Τ狼�뻳��������ξ������������䡢�̳�ƻƻ������Υ١�����ʤ�10����Τ������ο������������礦��Ȥߤ����Ȥ߹�碌�ƺ�ä������ǥߥ��饹��������Ĥ��ƿ��٤롣
���⥹�ϡ�����ޤǤ�600��800����ξ��ʤ����䤷�Ƥ��뤬������Ϥ�����������ʡ�
������ʹ����2005��3.16��
�����������������������ˤ���Ƥ���˥�ȥ꤬�����������Ǥ��Τ�
�¿����ƿ��٤��ޤ���
�ֹȵ���פϥ⥹�С������Ρ־�̣�ץ�����˺��Ѥ���Ƥ��ޤ���
���������ꥢ���������ǰ¿��ʿ���Ǥ���Ȥ����ڵ�Ǥ��͡�
����礻
������¼��������ٻ��ʤ����ޡ�3135
¼����Ť���������
������������������������������������������������������������
1000�ߥС������ɤ��̣
�֥⥹�С������פ�Ÿ������⥹�ա��ɥ����ӥ���16�����ϥ�С�������������Ǥϻ˾�ǹ��ͤ�1000�ߡ��ǹ��ˤι��ϥ�С������֥˥åݥ�ΥС�������̣���ʡפ����Ф���
����ñ���Υǥե췹���˻��ߤ������ڤ껥�פȤ��Ƴ�ȯ����Ʊ�Ҥϡֻפ��ڤä����ʤ�������ʬ�����Ǥ��פ�PR���롣
��03ǯ8���ȯ�䤷�Ƥ���־�̣�ץ��������4�ơ��������ͤ����ѥ�ȹ뽣���������ȥޥȡ��쥿�����١�������ʤ�10������Ǻ��Ťͤ��١����å��С������ǡ�������10����������Τ���ʸ����10ʬ�ʾ夫���롣
�ֺǹ��ʰ̡פΰդ����ơֽ��ʡפ�̾�դ����������ʤϺǶ�����������Х⥹����300Ź�˸¤ä�1��10�������ȯ�䤹�롣
���������ȤǤ�90ǯ���Ⱦ��������ʲ����ʤߡ��ϥ�С��������������ܥޥ��ɥʥ�ɤ����ȯ�䤷��59�ߤΥϥ�С��������֥ǥե�ξ�ħ�פȸ���줿���⥹�ϡ�æ�ե����ȥա��ɡפ�ᤶ���ƴ�¸Ź���鴶�Τ���Ź�˲��������Ȥ���Ƥ��롣
ī����ʹ����2005.3.16��
������������������������������������������������������������
1��1000�ߡ����С�����
---�ܸ�����ʤ�10�������꿩�����---
���ϥ�С������������⥹�С�������Ÿ������⥹�ա��ɥ����ӥ���15����1��1000�ߤΡ֥˥åݥ�ΥС���������̣���ʡפ�16���������Ź�ޤ�ȯ�䤹���ȯɽ����������Ǥϻ����ԡ�ŷƸ�ԡ������ԤΣ�Ź�ǰ�������Ź�ޤ����꣱��10�Ĥθ�������ǡֲ��ʤ˸��礦�ʼ������������פȼ�����Τ������Ƥ��롣
���ֽ��ʡפ���Ļ�˰����ʱ¤�Ϳ����줿����Τ狼�뻳��������ξ������������䡢�̳�ƻƻ������Υ١�����ʤ�10����Τ������ο������������礦��Ȥߤ����Ȥ߹�碌�ƺ�ä������ǥߥ��饹��������Ĥ��ƿ��٤롣
���⥹�ϡ�����ޤǤ�600��800����ξ��ʤ����䤷�Ƥ��뤬������Ϥ�����������ʡ�
������ʹ����2005��3.16��
�֥ȥ���������פȤ�JR�����ܤ�ȯ�Ԥ��Ƥ���ι�ξ�����
�������κ��ʤ˰��������֤��Ƥ���ޤ���
�ֿ����ܾ줫��פȤ���Ϣ�ܥ�������Ź���Ǻܤ���ޤ�����
������������������������������������������������������������
�ֻ����Τ����Ҥ�����--���㥭���㥭�Ȥ��������������ξ������
����������Φ�������뻳�����������֤����Ҥ����פλ��ϤϤޤ��ˤ��α����ˤ��롣��Ȥ�ȳ��ߤǼ������Ƥ��������Ҥ����������������Υ�줿�Ϥǽܤ�ޤ��Ƥ��롣
�֤����Ҥ����פϡ��֤�Ƥ���ڤȸ����Ƥ��롣��������Φ���Ǥϡ������ؤ�ȤȤ��Ź����¤ӻϤ�뤫������ָ��ε���Ȥ�ʤ�ȡ�����̾ʪ�ζ̥���˥㥯�ʤɤȰ��˽�Ȣ�ΰ�Ѥ�ź�����롣�����Ȥ��ƤϿɻ��¤����Ǥ�ݥԥ�顼�ǡ������ڱ�Ǥ����������Τ褦�˼狼���Ƥ�졢10������ۤɤˤʤ�ȼ��Ϥ���롣
�����⤽��֤����Ҥ����פȤϤɤ�ʿ���ʤΤ���
���֤�Ȥ�ȤϺǾ���βϸ���¦�γ������˼������Ƥ��������������ʡʥۥ�����ʤɤ���֡ˤ�����Ǥ����פ��ä��Τϻ��������ӿ建���ΰ�����������������ΤҤ����˻��Ƥ��뤳�Ȥ��餽��̾���դ����Ȥ�������Ͽ�ˤ��ȡ��Ť�����12ǯ��1672ǯ�ˤ�����ݤ���Ƥ������Ȥ�ʬ���äƤ��롣
�����ʹ�����Ⱥ��ݵ��ѤϾ���ǰ�Ƥ�줿�������פʸ���ϩ�Ǥ��ä��Ǿ�������DZ��Ф졢���夭��Τ��ä����ۻԤ˾�Φ������������Φ�˹����ä��Ȥ��⤬���롣���衢�����Ǿ������ǤϤ��ޤ꿩��ˤϾ�餺�������ԡ����ۻԡ��廳�ԡ��캬�Ԥʤɡ������������褤����Φ���Ǽ�˺��ݤ��졢����ǿ�����Ƥ��롣
���֤����Ҥ�������ħ�ϡ���Ϥꤽ�Υ��㥭���㥭�Ȥ��������Ǥ��礦�������դ�Ǥϡ������ߥĥФΤ褦�ʴ��ФǻȤ��Ƥ��ޤ��פȸ��Τϡ�ŷ��2ǯ��1782ǯ���϶ȤΡֶ������������Ĥޡ�8���ܤΤ���͡��Ⱥ���������ƱŹ�Ǥϡ��Ƽ�λ��������ȤȤ�ˡ�4�����ܤ����ˤʤ�ȡ������Ҥ�������˥塼�˲ä�롣
�����λ�����������ˬ�줿�顢�����ѡ�����������Τ����Ƥߤ褦���ͥ��䥭��٥Ĥ�Ʊ���褦�ˡ��ߤ��ߤ����������Ҥ����λѤ��ܤˤ��뤳�Ȥ��Ǥ���Ϥ�����
�֥ȥ���������6��桦�����ܾ줫��פ��ȴ��
�������κ��ʤ˰��������֤��Ƥ���ޤ���
�ֿ����ܾ줫��פȤ���Ϣ�ܥ�������Ź���Ǻܤ���ޤ�����
������������������������������������������������������������
�ֻ����Τ����Ҥ�����--���㥭���㥭�Ȥ��������������ξ������
����������Φ�������뻳�����������֤����Ҥ����פλ��ϤϤޤ��ˤ��α����ˤ��롣��Ȥ�ȳ��ߤǼ������Ƥ��������Ҥ����������������Υ�줿�Ϥǽܤ�ޤ��Ƥ��롣
�֤����Ҥ����פϡ��֤�Ƥ���ڤȸ����Ƥ��롣��������Φ���Ǥϡ������ؤ�ȤȤ��Ź����¤ӻϤ�뤫������ָ��ε���Ȥ�ʤ�ȡ�����̾ʪ�ζ̥���˥㥯�ʤɤȰ��˽�Ȣ�ΰ�Ѥ�ź�����롣�����Ȥ��ƤϿɻ��¤����Ǥ�ݥԥ�顼�ǡ������ڱ�Ǥ����������Τ褦�˼狼���Ƥ�졢10������ۤɤˤʤ�ȼ��Ϥ���롣
�����⤽��֤����Ҥ����פȤϤɤ�ʿ���ʤΤ���
���֤�Ȥ�ȤϺǾ���βϸ���¦�γ������˼������Ƥ��������������ʡʥۥ�����ʤɤ���֡ˤ�����Ǥ����פ��ä��Τϻ��������ӿ建���ΰ�����������������ΤҤ����˻��Ƥ��뤳�Ȥ��餽��̾���դ����Ȥ�������Ͽ�ˤ��ȡ��Ť�����12ǯ��1672ǯ�ˤ�����ݤ���Ƥ������Ȥ�ʬ���äƤ��롣
�����ʹ�����Ⱥ��ݵ��ѤϾ���ǰ�Ƥ�줿�������פʸ���ϩ�Ǥ��ä��Ǿ�������DZ��Ф졢���夭��Τ��ä����ۻԤ˾�Φ������������Φ�˹����ä��Ȥ��⤬���롣���衢�����Ǿ������ǤϤ��ޤ꿩��ˤϾ�餺�������ԡ����ۻԡ��廳�ԡ��캬�Ԥʤɡ������������褤����Φ���Ǽ�˺��ݤ��졢����ǿ�����Ƥ��롣
���֤����Ҥ�������ħ�ϡ���Ϥꤽ�Υ��㥭���㥭�Ȥ��������Ǥ��礦�������դ�Ǥϡ������ߥĥФΤ褦�ʴ��ФǻȤ��Ƥ��ޤ��פȸ��Τϡ�ŷ��2ǯ��1782ǯ���϶ȤΡֶ������������Ĥޡ�8���ܤΤ���͡��Ⱥ���������ƱŹ�Ǥϡ��Ƽ�λ��������ȤȤ�ˡ�4�����ܤ����ˤʤ�ȡ������Ҥ�������˥塼�˲ä�롣
�����λ�����������ˬ�줿�顢�����ѡ�����������Τ����Ƥߤ褦���ͥ��䥭��٥Ĥ�Ʊ���褦�ˡ��ߤ��ߤ����������Ҥ����λѤ��ܤˤ��뤳�Ȥ��Ǥ���Ϥ�����
�֥ȥ���������6��桦�����ܾ줫��פ��ȴ��
��Ź�Ǥ��֤��Ƥ�����ײ���¤����Ρֻ�ɴǯ���ݤ�֤�פ����俷ʹ�ε����ǾҲ𤵤�ޤ�����
����ޤǤ�̾����������륤����ǿ͵��Τ���ǤϤ���ޤ�����
���ε����ʹߡ�������䤤��碌���������Ƥ��뤽���Ǥ���
����������������������������������������������������
���ü�Ȥνй礤--�ٻΤ���ʤˤ⾡��̴�Τ褦��˧�Ὠ̣��
��¼����
����ʸά��
�ͤϤ��ΰ쾣�Ӥ�ĥ��줿��٥�ơ��������������Υ�٥�ˤϡ��ֻ�ɴǯ���ݤ�֤ꡢ̵������������ס�����������65����70���륳����ʬ20�ٰʾ�21��̤���������ԡ����ײ���¤�פȤ��ä������٤�й�ä����ȤΤʤ�����������������٤Ȳʤ��ۤɤδ�����ü�Ǥ��뤳�Ȥ��ͤϤ��Υ�٥��������ľ���������ͤϡ�ιͧã���������ǡ������Ǹ������ɤΤ����ߤ���䤵�����������Ӥ���ߤ��ˤä���
�������ϸ��ο�ʹ�����λ�ϼ���������ɤ�����ˡ�¢����¢�Ф��κݤ˴�������Τ˰㤤�ʤ���̵��������Ȥϡ��Ǥ�����˰�ũ��ÿ夷�Ƥ��ʤ����ȡ���������Ƥʤ����Ȥ��̣���롣
���פ��̤ꡢŷ�����ʤΤ�Τ��ä���
��20�٤Υ��륳����ʬ�Ȥ����Τˡ��ޤ��Ȥˤ���䤫��̴�Τ褦��˧�Ὠ̣�ΰ��ʤǤ��ä������������ॵ����ʤΤˡְ���Х����פˤʤäƤ��ޤä���
���俷ʹ����ॵ�����2005.5.1�ˤ��ȴ��
����ޤǤ�̾����������륤����ǿ͵��Τ���ǤϤ���ޤ�����
���ε����ʹߡ�������䤤��碌���������Ƥ��뤽���Ǥ���
����������������������������������������������������
���ü�Ȥνй礤--�ٻΤ���ʤˤ⾡��̴�Τ褦��˧�Ὠ̣��
��¼����
����ʸά��
�ͤϤ��ΰ쾣�Ӥ�ĥ��줿��٥�ơ��������������Υ�٥�ˤϡ��ֻ�ɴǯ���ݤ�֤ꡢ̵������������ס�����������65����70���륳����ʬ20�ٰʾ�21��̤���������ԡ����ײ���¤�פȤ��ä������٤�й�ä����ȤΤʤ�����������������٤Ȳʤ��ۤɤδ�����ü�Ǥ��뤳�Ȥ��ͤϤ��Υ�٥��������ľ���������ͤϡ�ιͧã���������ǡ������Ǹ������ɤΤ����ߤ���䤵�����������Ӥ���ߤ��ˤä���
�������ϸ��ο�ʹ�����λ�ϼ���������ɤ�����ˡ�¢����¢�Ф��κݤ˴�������Τ˰㤤�ʤ���̵��������Ȥϡ��Ǥ�����˰�ũ��ÿ夷�Ƥ��ʤ����ȡ���������Ƥʤ����Ȥ��̣���롣
���פ��̤ꡢŷ�����ʤΤ�Τ��ä���
��20�٤Υ��륳����ʬ�Ȥ����Τˡ��ޤ��Ȥˤ���䤫��̴�Τ褦��˧�Ὠ̣�ΰ��ʤǤ��ä������������ॵ����ʤΤˡְ���Х����פˤʤäƤ��ޤä���
���俷ʹ����ॵ�����2005.5.1�ˤ��ȴ��

|
�����Ԥdz�ư���Ƥ���֤����Ʋ�פ���κ��ʤǤ���
�֤����Ʋ�פ���ϡ�������ٹ����Ȥ�̡ܶ�Ǵ�ںٹ���˹�ҡ��Хå��ʤɤ�����Ƥ��ޤ����֤Ӥ�ΰ�����硢�¤ΤҤȤĤҤȤĤ���ǫ�˻ž夲���Ƥ��ޤ��Τǡ�������Τ��̣�襤�ȼ�Ť���β��������ȤƤ⤤�������Ǥ���
������ٹ��Ϲ��ͻ����Ⱦ�����ܤ�ȤˤĤ�����ή����ν����μ�ˤ�äơ���ʪ�˻Ȥ�줿�Ĥ��ۤ�˥����碌�ơ��֤�Ļ��ưʪ���ͷ��ʤɤ����줿����ΤҤ�ܤ�ۤɤ��礭���ʤ��顢����¿�����ޤˤʤäƤ��ơ����ޡ����ᡢ���������ʤɤȤ��ư��Ѥ��줿��
�������������������������������������������¤�ͷ�ӡ�������ٹ���ͺ�ܼҤ��
��������������������������������������������������

��ꯡ�3��5����19����
�������ߤ����Ƥ����ư���Ф����Ǥ�
��Ǭ�ȱ�±�ο�̣���¤�
����纬�ȿȷ礭�٤μ�ʪ
�ڤβ֤�ϡ���οɻ��¤�
�����ʼ�
������̾ʪ �̤���ˤ㤯
���˺襫�饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
�������ߤ����Ƥ����ư���Ф����Ǥ�
��Ǭ�ȱ�±�ο�̣���¤�
����纬�ȿȷ礭�٤μ�ʪ
�ڤβ֤�ϡ���οɻ��¤�
�����ʼ�
������̾ʪ �̤���ˤ㤯
���˺襫�饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
�����2��18����3��4����
������ɹ�㤬�Ȥ��Ʊ��夬¿���ʤ뺢�Ǥ�
����纬�ȿȷ礭�٤μ�ʪ
�ڤβ֤�ϡ���οɻ��¤�
�����ʼ�
�ֻ��̣ ���
������̾ʪ �̤���ˤ㤯
���˺襫�饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
������ɹ�㤬�Ȥ��Ʊ��夬¿���ʤ뺢�Ǥ�
����纬�ȿȷ礭�٤μ�ʪ
�ڤβ֤�ϡ���οɻ��¤�
�����ʼ�
�ֻ��̣ ���
������̾ʪ �̤���ˤ㤯
���˺襫�饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
��ʪ�Ľб�ϩ�ܤȵ������
��ʪ�ļ��ݽ�
��ʪ�IJ������ĺ��ҡ����
�ǥ����ȡĺ���¼�� ����Ʀ������
��ʪ�ļ��ݽ�
��ʪ�IJ������ĺ��ҡ����
�ǥ����ȡĺ���¼�� ����Ʀ������
Ω�ա�2��4����17����
�������դε���Ω���Ϥ�뺢�Ǥ�
����纬�ȿȷ礭�٤μ�ʪ
�����餳�ҤŤ���
�ֻ��̣ ���
�����������
������̾ʪ �̤���ˤ㤯
���˺襫�饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
�������դε���Ω���Ϥ�뺢�Ǥ�
����纬�ȿȷ礭�٤μ�ʪ
�����餳�ҤŤ���
�ֻ��̣ ���
�����������
������̾ʪ �̤���ˤ㤯
���˺襫�饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
�紨��1��21����2��3������
�������������κǤ⸷�����Ȥ��Ǥ�
ŷ�����ѿ���
����̾������ϤȽб�ϩ�ܤȿͻ��μ�ʪ
�ֻ��̣��� ������̣
����Ʀ��
������̾ʪ �̥���˥㥯
���˺� ���饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
�������������κǤ⸷�����Ȥ��Ǥ�
ŷ�����ѿ���
����̾������ϤȽб�ϩ�ܤȿͻ��μ�ʪ
�ֻ��̣��� ������̣
����Ʀ��
������̾ʪ �̥���˥㥯
���˺� ���饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������

|
����Ҥ��פȡ��礫�֡פ�����ͤγݼ���������ê�ˤ����������˱ɤ�Ĺ����ꤦ�ΤǤ���
���θ塢��Ҥ��Ϥߤ���Ĥ��ƿ���
�礫�֤Ϥ֤ä����ˤ����Ǥ�Ʀ�����줿�����ˤ��ޤ���
��ϥ��餳��֡�����Ȼ庫�ۤμ�ʪ�˥ͥ��ȾƤ�Ʀ���ź���ޤ���
����Ҥ��סĤ����Ĥ��Τ��ȡ�����Ҥ��˸�Ω�Ƥơ��Ҥ����ʤ�ޤ�Ĺ�����Ǥ��ޤ��褦�ˡ��Ȥ����ꤤ��������Ƥ��롣
���礫�֡סĹ��ͻ���ˤ�¸�ߤ���������������������ˤʤ�ޤ��褦�ˡ��Ȥ����˱ɤ�ꤦ��Ρ�
��ʪ�Ľб�ϩ�ܤȵ������
��ʪ�Ĥʤᤳ�Τߤ���
��ʪ�IJ������ĺ��ҡ����
�ǥ����ȡĤ��ܤ��㥢����
��ʪ�Ĥʤᤳ�Τߤ���
��ʪ�IJ������ĺ��ҡ����
�ǥ����ȡĤ��ܤ��㥢����
���12��22����1��6����
���������κǤ�û������
���
����̾������ϤȽб�ϩ�ܤȿͻ��μ�ʪ
�ֻ��̣��� ������̣
����Ʀ��
������̾ʪ �̥���˥㥯
���˺� ���饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
���������κǤ�û������
���
����̾������ϤȽб�ϩ�ܤȿͻ��μ�ʪ
�ֻ��̣��� ������̣
����Ʀ��
������̾ʪ �̥���˥㥯
���˺� ���饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
�����12��7����21����
�������㤬�礤�˹ߤ뺢�Ǥ�
�դ��դ��纬 �ij�̣���������ڤβ�
����̾��������ϤȽб�ϩ�ܤȿͻ��μ�ʪ
�ֻ��̣ ��� ������̣
����Ʀ��
������̾ʪ �̥���˥㥯
���˺� ���饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
�������㤬�礤�˹ߤ뺢�Ǥ�
�դ��դ��纬 �ij�̣���������ڤβ�
����̾��������ϤȽб�ϩ�ܤȿͻ��μ�ʪ
�ֻ��̣ ��� ������̣
����Ʀ��
������̾ʪ �̥���˥㥯
���˺� ���饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
�����11��22����12��7�����ޤ�
�������㤬�����ߤ�Ϥ�뺢�Ǥ�
������̾ʪ �̥���˥㥯
���˺� ���饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
�������㤬�����ߤ�Ϥ�뺢�Ǥ�
������̾ʪ �̥���˥㥯
���˺� ���饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
Ω�ߡ�11��7����21����
���������ߤε���Ω���Ϥ�뺢�Ǥ�
������̾ʪ �̥���˥㥯
���˺� ���饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
���������ߤε���Ω���Ϥ�뺢�Ǥ�
������̾ʪ �̥���˥㥯
���˺� ���饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
���ߡ�10��23����11��6������
�����������ιߤ�Ϥ�뤳���Ǥ�
�����Ӥ�̣����
�Ƥ��ʤ��Τ̤��¤�
�ֻ��̣ ��� ������̣
����Ʀ��
������̾ʪ �̥���˥㥯
���˺� ���饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
�����������ιߤ�Ϥ�뤳���Ǥ�
�����Ӥ�̣����
�Ƥ��ʤ��Τ̤��¤�
�ֻ��̣ ��� ������̣
����Ʀ��
������̾ʪ �̥���˥㥯
���˺� ���饫���μ�ʪ��������
������ǯ��˥塼�Ǥ�
��˥塼�Ϥ������ˤ�ä��Ѥ�뤳�Ȥ��������ޤ��Τ�ͽ�ᤴλ����������
��Ź�Ǥϻ͵��ޡ��λ�Į�����ʤ���Ǥ��Ϥ����Ƥ���ޤ���
�Ⱥʻ���
���̷ݽѹ�����ء����Ѳ����ܲ襳����´�ȡ�
�䳨����������ˤҤ������ܲ���칶���롣
º�ɤ����Ȥ��컳���С�������ѡ�
���Τ��Ф餷�����ޤ俧�Ȥ��˿����Ǥ���롣
�Ƕ�ǤϿ��ϲ�ȿ�̲���ٶ��档
�Ⱥʻ���
���̷ݽѹ�����ء����Ѳ����ܲ襳����´�ȡ�
�䳨����������ˤҤ������ܲ���칶���롣
º�ɤ����Ȥ��컳���С�������ѡ�
���Τ��Ф餷�����ޤ俧�Ȥ��˿����Ǥ���롣
�Ƕ�ǤϿ��ϲ�ȿ�̲���ٶ��档
(C) �������������Ĥ�

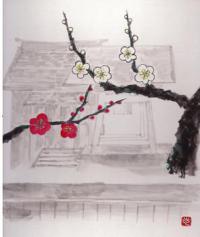

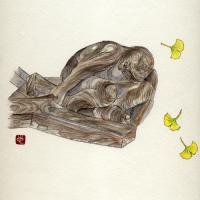




�����Ԥdz�ư���Ƥ���֤����Ʋ�פ���κ��ʤǤ���
�֤����Ʋ�פ���ϡ�������ٹ����Ȥ�̡ܶ�Ǵ�ںٹ���˹�ҡ��Хå��ʤɤ�����Ƥ��ޤ����֤Ӥ�ΰ�����硢�¤ΤҤȤĤҤȤĤ���ǫ�˻ž夲���Ƥ��ޤ��Τǡ�������Τ��̣�襤�ȼ�Ť���β��������ȤƤ⤤�������Ǥ���
������ٹ��Ϲ��ͻ����Ⱦ�����ܤ�ȤˤĤ�����ή����ν����μ�ˤ�äơ���ʪ�˻Ȥ�줿�Ĥ��ۤ�˥����碌�ơ��֤�Ļ��ưʪ���ͷ��ʤɤ����줿����ΤҤ�ܤ�ۤɤ��礭���ʤ��顢����¿�����ޤˤʤäƤ��ơ����ޡ����ᡢ���������ʤɤȤ��ư��Ѥ��줿��
�������������������������������������������¤�ͷ�ӡ�������ٹ���ͺ�ܼҤ��
��������������������������������������������������