最上義光歴史館
|
義光のニックネーム…虎将!?
義光の代表的なキャッチコピーをみてみると… 「奥羽の驍将」「羽州の狐」「修羅鷹」「戦国の驍将」「北天の巨星」などがあげられます。いずれも現代の地元山形の方々が義光に冠したものです。大変誇らしいものもあれば残念なものもあります。これらは義光を紹介する際にしばしば引用されています。義光の最初のイメージを決定付けるきわめて重要な文言といえるでしょう。 ちょっと昔にさかのぼってみましょう… 義光が亡くなってから約230年後…幕末の儒学者塩谷宕陰(しおのやとういん/1809-1868)は、山形藩主水野忠精(みずのただきよ/1832-1884)に従って嘉永2年(1849)からその翌年まで山形に滞在し、その間に作った漢詩を『山形従役詩』にまとめました。その中に義光を讃えた詩が発見されました。 雑咏 英風千古快心胸 (英風千古、心胸に快し。) 散歩時尋虎将蹤 (散歩して、時に虎将の跡を尋ぬ。) 四十八城何處是 (四十八城いづれの処か是なる。) 秋高天半玉蟾峯 (秋高き天の半ば、玉蟾の峰。) 【大意】 英雄のなごりは消えず、思うだに、胸に快い。 そぞろ歩きのおりふしに、虎将(義光)の跡を尋ねる。 (最上領)四十八城。それは今、いずこ。 高く澄む、秋の空。中天に浮かぶは、月山の美しい峰。 宕陰は義光を「虎将(こしょう)」と称し、その業績を讃えています。これは、現在わかる最も古い義光のニックネームです。「虎将」とは義光が叙任した「近衛少将」の漢名「虎賁郎将(こほんろうしょう)」から発したものと考えられています。義光が「虎将」で甥の伊達政宗が「独眼竜」。戦国の奥羽では竜虎がたがいに競い合い並び立っていたわけです。 |
|
国宝「伴大納言絵巻」の変遷について
−最上家の臣・武久庄兵衛が所持していた− 現在、国宝に指定されている「伴大納言絵巻」(以下、「絵巻」と呼ぶ)は、我国の絵巻物を代表する傑作の一つである。内容はそこに書かれている「絵詞」を通して知ることができるが、伴大納言善男の陰謀による放火事件により、内裡とその周辺が混乱状態に陥っている様子を描いた、12世紀後半に創作された説話絵巻である。 ここでは、これを美術的に解明するのではなく(尤も小野自身が学問的には全く無縁ではあるが)、これが何時しか最上家(義光か)の手に渡り、元和8年(1622)山形藩最上家の消滅以後に、若狭の小浜藩酒井家に再仕官した武久庄兵衛昌勝の手により最上家より、賜った「絵巻」を子孫に伝えていった事実を追っていきたい。 まずこの「絵巻」が15世紀中頃に、「彦火々出見尊絵巻」や「吉備大臣入唐絵巻」という名品と共に、松永庄(小浜市の内)の新八幡宮に収められていたことが、後崇光院(伏見宮貞成親王)の当時の日誌に書かれている。それが何時しか三巻とも流出し、「絵巻」がはっきりと武久氏所有のものだと確認できたのは、天明・寛政年間以後のことである。 武久庄兵衛は近江の出である。父は佐々木六角氏に仕えていた。六角氏が織田信長との抗争に破れ没落、父の討死の後に羽州の由緒ある者を頼り、やがて最上義光に五百石で仕えた。義光の間近かにつかえていたことが、数々の記録に残されている。特に家親の代の大坂の陣では、「権現様大坂御陣之節、為使者大坂エ罷登」とあり、戦後にその功として、五百石を加増されている。 武久家に伝えられている、大坂の陣の折の庄兵衛使用の指物に、血で黒く染まった箇所があるというから、山形藩の実戦への参加を裏付ける、有力な証拠にもなろう。 庄兵衛は時の幕閣の一員である酒井忠勝に仕え、小浜の老役として千石を給された。個人的にも忠勝の孫娘を養女に貰い受けるなどして、承応3年(1654)12月、83歳で没するまで、藩政に関与する立場にあった。 この「絵巻」が何時の頃に若狭を離れ、最上家に入ったのかは確かなことは判っていない。ただ酒井家の関係者が著した『若むらさき』という随筆に、「絵巻物者賜於最上家焉」と、庄兵衛が最上家より賜ったことを示す、貴重な記録を書き残している。 この随筆は、文化6年(1809)に大田南畝(蜀山人)が編んだ『三十輻(みそのや)』の中に収められている。著者は酒井家で学問方の人物と思われる「津田かみはや」という人物である。藩主忠貫代の寛政10年(1798)に書かれ、次のような書きだしで始まっている。 「我国の守の従者、武久昌扶なるものゝ家に、伴の善男の応天門を焼たりし絵巻物を、年久しく秘め置しに、いかなる風の便にか、天のすめらみことのきこし召して、久我の前内大臣殿の妹君は、頼み奉りし殿の北の方にてわたらせ給ふゆかりあれば、頃は寛政の初めつかた内大臣殿して、召し出し給ふ、……」 紙面の都合で全文は掲載できないが、天明8年(1788)の京の大火により内裏が焼失した。その際に、平安の昔の古制復活に、「絵巻」が内裡の造営の参考にと、武久氏に久しく秘め置かれた「絵巻」が召し出されたのである。津田はその時の公家と酒井家との「絵巻」を巡っての経緯を、多方面の資料を駆使して書き上げている。要は「絵巻」が武久氏の所有物であったことを、述べていることである。 明暦2年(1656)に、将軍家綱が酒井邸に赴いた際に、書院の飾り付けの品々の中に「絵巻」が置かれていた。従来、諸書の多くは、「絵巻」は藩祖忠勝が手に入れたものというが、それを裏付ける確かな記録は確認できていない。この時の「絵巻」が果たして酒井家のものであったかは疑わしい。酒井家内で「絵巻」が確認され出したのは、天明・寛政年間に於ける武久氏の記録からである。明暦の「絵巻」は将軍に供覧するために、武久氏から一時的に借り受けたものと考えられる。 津田は、主家や武久氏などの資料から、「絵巻」の移り変わりを、精力的に説き明かした。その「絵巻」は最上家に於いて貰ったという一言が、部外者ではなく、酒井家関係者の口から発せられたことに、大きな意味がある。 安永3年(1774)に六代目の内蔵昌扶が書き上げの由緒書には、初代庄兵衛と「絵巻」との関わりについての記述は見当たらない。内蔵助は何故にその事実を記載しなかったのか。あくまで秘事として明らかにしたくなかったのか。しかし、結局は表に出さざるを得なかったのである。 文化8年(1811)に七代目庄兵衛昌生は、 「寛政九丁巳年正月七日、於評定所被仰出者、先年差上置候所持之伴大納言絵巻物、御用相済御下ケ被遊候、右者此度禁裡御用ニ相立、殊ニ被備天覧候処、叡感不斜、」 と書き伝えている。全文は長くなるので省略するが、寛政9年(1797)正月に、先の年に京へ差し出していた「絵巻」が内裡の完成により役目を果たし、戻されてきた事を伝えている。また、「絵巻」は天覧に浴して大変喜ばれ、褒美として小袖壱枚・銀子十枚と、久我大納言家の口上書などが添えられていたことも記されている。 主家の関連資料の内から、藩主忠寛の「忠寛様御年譜」には、 「十月(天明八年)久我様ヨリ京都御屋敷迄、以御使者御家来武久庄兵衛所蔵之伴大納言焼応手門候絵巻物□□関白様被□□御覧度ニ付被成被供用度而被仰処、……」 として、その年の正月の京の大火から時を経ずして、「絵巻」が京の話題となってきたことが判る。そして、寛政9年(1797)正月7日に、武久氏に戻された「絵巻」を見るために、同輩の山岸惟重が訪れた。4日後の12日付の惟重日記には、 「武久殿ニ而伴大納言絵巻拝見、右者拾ケ年以前造内裡御用之由ニ而、久我様ヨリ御願ニ而御提出被成、……」 とあり、惟重もその内部事情については、承知していたのであろう。ところがこの「絵巻」にとんでもない異変が生じたのである。それは天覧に浴した名品を、藩主は黙っている筈もなく、以後、城からは出さず、たとへ勅命・台命あるとも応ぜず、永の預かりとして酒井家の所有とするという、非常な結末を迎えたのである。 「伴大納言絵巻物入 右武久内蔵丞方より、老衆エ預ケ被置候由、寛政九丁巳年七月朔日御宝蔵エ入置候様、御談にて小原操方より受取」([御譲道具入日記]) とあるように、半年後の7月には強制的に取り上げられ、藩の宝庫に収められ、そのまゝ維新を迎え現在に至ったのである。武久氏にとっては、悲しき結末を迎えたということである。そして、いかなる事情か知らぬが、酒井家から離れ出光美術館に移ったのは、昭和五十年代のことである。 参考のために、古書から武久氏所持の記事を拾ってみる。 [類聚目録]伴大納言絵、小浜酒井家家人武久某蔵 [古絵目録]伴大納言絵三巻、著若狭国小浜家中武久庄兵衛蔵、 [画図品類]伴大納言草紙、若狭小浜武久平蔵書伝、 (執筆:小野末三/「歴史館だよりNo12」より) |
(C) Mogami Yoshiaki Historical Museum


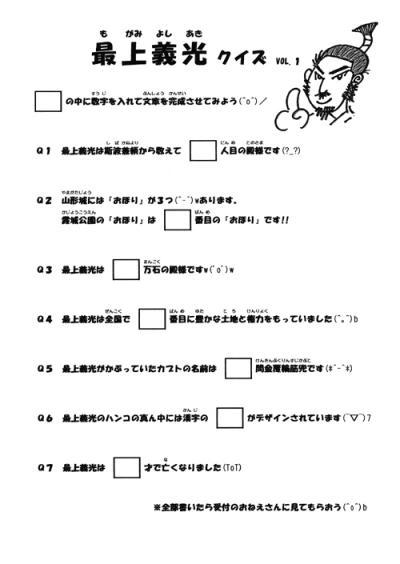



(書籍等名称 / 発行年月日 / 著者等 / 販売価格)
※2024年6月現在
■「戦国の明星 最上義光」
平成26年1月
片桐繁雄著
(公財)山形市文化振興事業団 最上義光歴史館発行
1,000円
■「重要文化財 光明寺本 遊行上人絵」
平成25年9月14日
山形市発行/(公財)山形市文化振興事業団 最上義光歴史館編集
2,000円
■「翻刻資料6 最上義光注里村紹巴加筆『連歌新式』」
平成21年3月31日
(財)山形市文化振興事業団 最上義光歴史館
1,000円
■「(案内冊子)最上義光歴史館(第三版)」 平成20年3月
(財)山形市文化振興事業団 最上義光歴史館
500円
■「翻刻資料5 最上下向道記」
平成19年3月31日
(財)山形市文化振興事業団 最上義光歴史館
1,000円
■「山形城と城下町の面影」
平成18年3月
(財)山形市文化振興事業団 最上義光歴史館
100円
■「翻刻資料4 最上義光連歌集 第三集」
平成16年3月31日
(財)山形市文化振興事業団 最上義光歴史館
1,500円
■「翻刻資料3 最上義光連歌集 第二集」
平成15年3月31日
(財)最上義光歴史館
1,500円
■「翻刻資料2 最上義光連歌集 第一集」
平成14年3月31日
(財)最上義光歴史館
1,500円
■「新稿 羽州最上家旧臣達の系譜 −再仕官への道程−」
平成10年3月31日
小野末三著
(財)最上義光歴史館発行
3,000円
■特別企画展図録 「武人画家 郷目右京進貞繁」
平成6年4月26日
(財)最上義光歴史館
1,000円→→500円