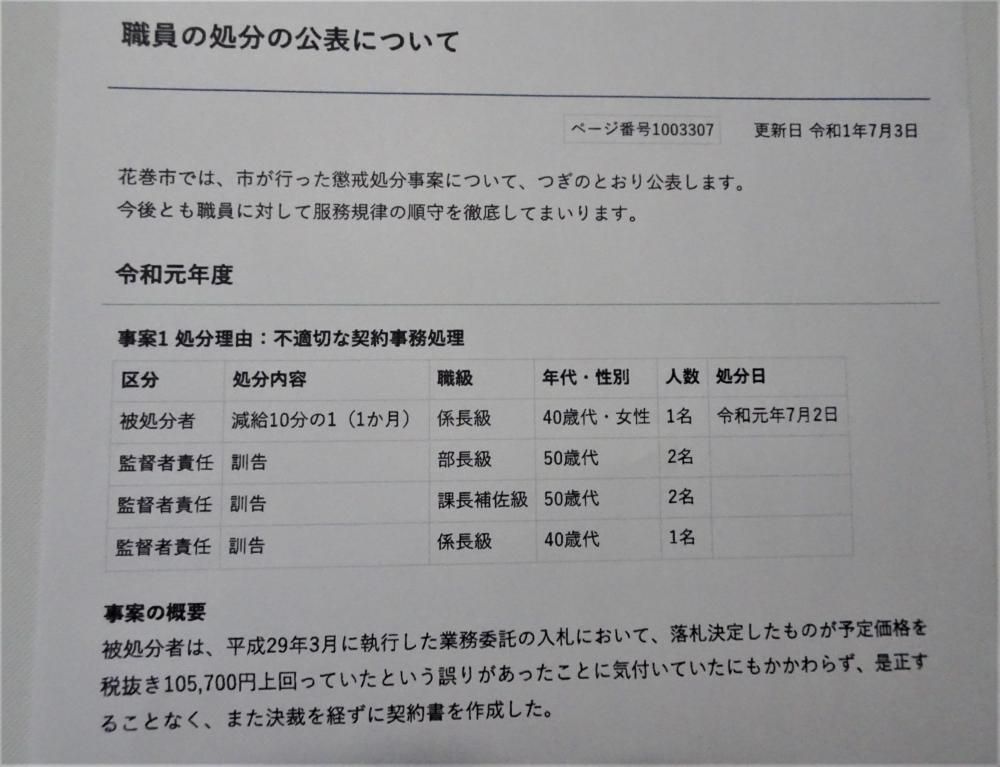「国境の長いトンネルを抜けると雪国だった。夜の底が白くなった」(『雪国』)。ノ-ベル賞作家、川端康成の有名な書き出しを借用すれば、こんなイメ-ジになるのだろうか。「花巻駅に降りたら、賢治さんが目の前に立っていた。そこは銀河宇宙への入り口だった」―。私たち有志はこんな願いを込めて、「『イ-ハト-ブ』の実現を目指す花巻有志の会」(略称「イ-ハト-ブ花巻有志の会」)をこのほど、結成した(趣意書は10月15日付当ブログに掲載)。来年1月に誕生する新市長に対しては、こうした見果てぬ夢にもぜひ「聞く耳」を持ってほしいと思う。以下に記す当会の政策提言は将来の市政運営にとって、欠かせない基本施策だと考える。商工業や農業、健康・福祉、教育、少子高齢化、防災など社会のセーフティネット(安全網)に関わる基本分野については割愛する。
※
●合併15周年の検証
~旧3町と旧花巻市との平成の大合併から今年は15年。この節目の機会に総合支所体制やコミュニティ会議の役割や機能を再点検し、たとえば、総合支所の機能強化など見直しが必要な部分については大胆に変革する。「境界領域マネジメント」(役重眞喜子)手法の活用。
●旧3町のレガシ-(遺産・資源)の掘り起こしと再生
~大迫、東和、石鳥谷の旧3町には独自の歴史や文化、風土が育まれてきた。しかし、少子高齢化の影響をもろに受け、過疎化の波にほんろうされている。こうした逆境の中で求められるものこそが「発想」の転換である。
~国の重要無形民俗文化財の指定第1号で、ユネスコ無形文化遺産登録の「早池峰神楽」とハヤチネウスユキソウなど5種類の固有種が自生する霊峰・早池峰山、(最近では食害被害が多いが)山野をかっ歩する野生のニホンジカ、ワインの香り…。こうした自然環境をまるごと「ユネスコエコパ-ク」(生物圏保存地域)に登録申請し、自然と人間との共生を目指す。また、大迫高校に「神楽専攻科」を設置し、山村留学のモデル校として全国発信する。「SDGs」(持続可能な社会)の未来へ向けて。
~旧東和町は阪神淡路大震災(1995年)の際、全国に先駆けて「被災者受け入れ」条例を制定するなど移住者に広く門戸を開いてきた自治体として知られる。この時の体験は「川崎市との交流」や「全国東和町サミット」「滞在型農園」「山野草クッキングツア-」など様々な成果となって、現在に引き継がれている。こうした「移住定住」政策の先験に学ぶ。
~旧石鳥谷町は酒文化と南部杜氏のまちとして、大迫、東和とは別の歴史を歩んできた。音楽家の佐藤司美子さんが「酒つくり唄」(作業唄)を復刻・CD化するなど伝統文化の継承も盛ん。「記憶」の再生の大切さを学ぶ。
●上田(東一)市政のキ-ワ-ドのひとつ―「立地適正化計画」の総点検
~計画立案に至る経緯=「市長就任」(2014年=平成26年2月5日)→「改正都市再生特別措置法(立地適正化計画の創設)」(同2月12日閣議決定、同5月21日公布、同8月1日施行)→「花巻市立地適正化計画」が全国で3番目に策定(2016=平成28年6月1日)=補助金行政への過度の依存とそれに伴う独創性の欠如。
~総合花巻病院の移転・新築、花巻中央広場、新花巻図書館構想、JR花巻駅の東西自由通路(橋上化)構想の政策立案過程とその是非の検証。新花巻図書館については「図書館とは何か」という”そもそも”論に立ち、ゼロベ-スから議論をやり直す。橋上化についてはその受益者負担の不公平性や立案過程の不透明性、「レインボ-計画」というレガシ‐(遺産)の破壊につながるなどの観点から、全面白紙撤回へ。
●将来都市像「イ-ハト-ブはなまき」を実践するための具体的な処方箋の策定
~1市3町には宮沢賢治の愛好家らでつくる読書団体や読み聞かせグル-プが数多く存在する。いわば、花巻(イ-ハト-ブ)を全体として貫く「思索」の基軸ともいえる。全域の精神的な土壌(風土)としての新たな”賢治学”の創設へ。
~一方、賢治の影響を受け、宮沢賢治賞やイ-ハト-ブ賞を受賞した人たちは128の個人・団体にのぼっている。この中には高木仁三郎(物理学者、故人)や井上ひさし(作家、故人)、池澤夏樹(作家)、アフガンでテロの銃弾に倒れた医師の中村哲、高橋源一郎(作家)、吉本隆明(評論家、故人)、むのたけじ(ジャーナリスト、故人)、高畑勲(映画監督、故人)、色川大吉(民衆思想家、故人)の各氏など各界各層のキラ星のような人材が並んでいる。こうした“賢治人脈”の源流を探る。
~たとえば、「イ-ハト-ブ花巻有志の会」の趣意書にはこんな処方箋が示されている。「現在のJR花巻駅はそのまま残し、隣接する地下道には賢治童話をイメ-ジしたメルヘンチックな空間を創出し、『銀河鉄道始発駅』みたいな雰囲気のまちづくりを目指したい」。どこでも賢治と“遭遇”できるまちづくりへ。
●遊休跡地の有効活用~未来世代を見つめて
~旧花巻市内の中心部には「末広町」(旧花巻警察署)、御田屋町(旧新興製作所=花巻城址三の丸)、吹張町(旧料亭「まん福」)、花城町(旧総合花巻病院)などの一等地が遊休跡地として放置されたままになっている。その立地条件の良さの有効利用こそが将来のまちづくりの生命線と言える。
~たとえば過日、開催された「まん福」跡地の利活用を話し合うワ-クショップ(WS)ではその地の利を生かしたアイデアが多く出された。中でも現在、建設場所をめぐって迷走を続けている「新花巻図書館」については「この高台こそが最適地ではないか」という意見が3人から出されて注目された。一方、花巻駅前への立地計画もJRとの土地取得交渉が不透明な状況にあり、さらに候補地のひとつとされている「花病跡地」の建物撤去作業は大幅に遅れる見通しが明らかにされるなど難問が山積している。
~こうした状況下、「新興跡地」の市有地化なども視野に入れ、一部受益者だけではなく、旧3町を含めた全市民の意見集約を市政課題と位置付ける。新幹線「新花巻駅」誘致を成功に導いた全市民的な“住民運動”の記憶を呼び戻す。
●中心市街地の活性化~「賢治」の息遣いが聞こえるまちに
~賢治の生家や賢治童話『黒ぶだう』の舞台とされる菊池捍(きくちまもる)邸、交流施設「賢治の広場」などが集中するこの一帯を「賢治」と一緒に散策できるゾ-ンに。賢治は生前、「下の畑」で収穫した野菜や花きなどをリヤカ-積み、この界隈で売り歩いた。この「リアカ-」行商を復活させる現代版「楽市楽座」(どでびっくり市=フリ-マ-ケット)の常設化。「まん福」跡地への新花巻図書館立地が実現すれば、一体的な導線効果も期待できる。
●理念型観光ル-トの確立~「メルヘンル-ト」の形成
~「平泉」(藤原清衡ら”奥州藤原3代”の歴史と記憶)―「花巻」(宮沢賢治、新渡戸稲造、佐藤昌介、島善鄰、高村光太郎、萬鉄五郎らの風土的な足跡)―「遠野」(柳田国男、佐々木喜善、 伊能嘉矩らの民俗史の軌跡)―「釜石・大槌など三陸」(井上ひさしの全身小説家としての奇想天外譚)を結ぶ観光ル-トをめぐりながら、単なる物見遊山型観光から「理念型」観光への脱却。
●広域行政の模索~隣市・北上との対話の促進
~工業化が進む北上市では現在、住宅ラッシュは続いている。ほとんどが「キオクシア」など大規模な工場団地で働く労働者向けの住宅建設で、空き地に余裕がなくなった同市では居住地を「花南」地区など温泉地・花巻に求める動きが加速している。こうした一体的な地域開発にとって不可欠なのは行政トップ同士の意思疎通。市境の壁を取り払って、広域行政のモデルを構築する。
(写真はJR花巻駅前の「風の鳴る林」を取り入れた、賢治をイメ-ジさせるチラシ)