{PDF} ����������� 3.6MB_Adobe PDF
���Ե�������(�̿����Წ�Ա��������ε��տ���) ����ˤ�����18���ȿ��ŷ�Ĥλ����1600ǯ�����˷��Ƥ�줿�Ȥ�����ϲ�֤��Ť˲��������˾�ä��̰�ɱ�����������Τܤäƿ��ͯ���Ф�ζ��Ĥ������˼��¤���Ƥ��ȸ����뤽������ ���Ĥ����ɤ���ͤ�פäƤ��롣 677ǯ����˱6��1300ǯ�����ˤϼ��¤�¤���ؤ����Ȥμ��������ꡢ�ºݤΤȤ����Ϸ���ǯ����Ծܡ����ܤ�����Ȥ��ú��ϡ�1055ǯ(ŷ��3)�˱��ܤ�긽�ߤξ��˰��ۤȤ����Τ����ܵܡ�ʬ��Ҥ�500�ۤɤ���ȸ����������������������ա�����Ǫ������ǩ���������٤�Ʊ���Ȥ������Ȥ��� �ȡ��������Ȥ����ܸ��ɤߤˤϴط��ʤ����ҤȤ������Ȥ��� ����Ƥߤ�ȡ��Ͽ���Τꤨ���Ȥ�����7�սꤢ�ä����ʳ���¿���Τ��� 705ǯ������3�ˡ����� ���� ����Į���������տ��ҡ�����ȴ31��(����20���Ǿ���0��) ���һ��塡�٤��������� ���Ļ�ʿ�ĺ��ܡ��������ҡ���ȴ52���ʺǾ���10���� �������塡Ļ����� �� ���Ļ��ںꡡ�������ҡ�����ȴ5���ʺǾ���0�������������ϳ��椫�� 804ǯ�ʱ���23�ˡ����������캬�������ҡ�����ȴ177��(�����175���Ǿ���84��) 1863ǯ��ʸ��3��Ļ����������Ե���ɡ��������ҡ���ȴ100��(����92��) 1863ǯ��ʸ��3��Ļ�������������Į��������Ǫ���ҡ�����ȴ100��(����92��) �������������������� �� ������������7���������ҡ�����ȴ260��(����250��) ���͡�709ǯ����Ƽ2�˰����������ĻԾ��ء����غ�����ȴ11�� ���ʤߤ��Ϸ�Ū�ʰ��ִط��Ϥ��ƺǾ���Ȥο�̺���Ƥߤ������ߤʤΤǤ��ޤ껲�ͤˤʤ�ʤ��� �ɤ��⤳��ʾ�Ϥ狼��ʤ��ä��������Ū�˸��Ƥߤ�� ��ʯ 7�����ν�ᡢ���졦���̤Dz��꼰�м�����ĸ�ʯ�������¤��줿�� ��ʯ����¤�ϡ����⡦�����ܤǤ�7������Ⱦ��������Ǥ�8�����Ϥ��Ả�����������Ǥ�8���������ۤܽ���롣 �б����� 585ǯ��������ǯ��- �����ϻҤ˻����줿����������ŷ�Ĥ��軰�Ļҡ�˪�ҹĻҤ������������곫����������������˶̰�ɱ̿�Ȥ��������Ƥ��롣 ����ī�� 658 �������۹�鰤�������ס�������Ψ���ƲܰФ���Ƥ������(����)������(ǽ��)�βܰС������� 714 ��Ƽ�� 9.23 �б������� (����)���б������ۤ����Ԥ���ϩ�ΰ�����ͤ��롣 �ܰп� 7�������ˤϡ��ܰФϸ��ߤεܾ븩�������黳�������̤����������ȡ��̳�ƻ������ʬ�˹������ߡ����ΰ��������ܤ��ΰ����ˤ��ä����ܰпͤ������¤˽�°�����Ԥ�������ʬ�����Ȥν���Ū��ͻ����ߤ뤳�Ȥ��ʤ����� ɴ�Ѳ�² 697ǯ - 766ǯ���ܤ�˴̿����ɴ�Ѳ�²�λ�¹�����˵������ī������Ѥ��졢�ܰ���Ȳ�ˤ�ä�����̤ˤ��äƤ��Ƥ������������Ϥʤ��Τ����������̰�ɱ����夫���äƤ����Ȥ����� �߳��� 727ǯ���߳�����ȼԤ�¿��ˬ��Ƥ��롣���ܳ��ε����������Ѥ��Ƥλ����ĤʤΤǡ������ˤ���Ƥ�����Τȹͤ��롣�ɤ��դ͡��ɤߤ�������Ѥ���Τ�⤷�����Ƥ��δط��������Τ���������ƻ���ν��������������ͤʤɤ�ƻ��������Ƥ��롣�� 777 ��������12.14 Φ���ü龭���������ꡢ�б���η����ܰФ��Ԥ����(�����ĻԤޤDz����ä�) 778 �������б��βܰ�ȿ��Ͻ��ᡣ ʩ�� ��Ʊ��ǯ(806ǯ)10�������̵����ī��������ܤ��ںߤ��롣���ܤǤϤ���ǯ��3�����ŷ�Ĥ�������ʿ��ŷ�Ĥ�¨�̤��Ƥ��������ΤΤ����۶���ư������ˤʤ롣 �����夫�鹾�ͻ���κǾ�����κǾ��������ˤ���糫��ʤɤʤɡ��� ñ��˹ͤ��ơ��Ǿ��������ˤ�����ꤢ��ȹͤ����뤬���ºݤ��Ϸ������ϳƽ�㤦�� ���������ͻ���ʹߤǤ�����������줿���Ȥˤ�ä�����ˤʤä������ˤ�äƿ屿��̵����ꤤ�Ϸ����뤳�ȤϤ��ꤦ�롣 ��������˷��Ƥ�줿ʪ�ˤĤ��Ƥϡ��������ܳ���ϩ�ΰ������ä���Τȡ�����Ū�����ʤΤ�Τ�����Ȼפ��롣�ʤ��ʤ�屿�Ȥ��ۤɴ�Ϣ�Τʤ����֤˷��äƤ����Τ����뤫����� ������¿���Τ�ŷε��ڤ�¿�����롣�Ȥʤ�Ȥ�Ϥ���ִ�Ϣ��¿���Τϡ��屿�Τ褦���� ���������Ƥ���ʪ�˴ؤ��Ƥϡ��椬�Ĥ롣���Τ����϶��餯����ۤ��Ϥ���ä���²���뾦���ϸ��ˤϤ��ʤ��Ϥ������Ԥ�褯�Τꡢ�屿��ɬ�פȤ������ԤǤ��������������Ҥ���������ͳ�������ʪ�ʤΤ��� �������ΤȤ��������ޤǤ��³��Τ褦�Ǻ����Ĵ��³�Ԥ������Ȼפ��ޤ����ʽ����Ϥ���Τ��� ��Ϣ�������������Ϣ�����Ԥ����ޤ�������ξ���ˤ���ѹ�������������®�䤫�����Ƥ��ѹ��������ޤ��� |
|
���Ѥˤϡ��������������Ǥˤ�ä��Ѥ߾夲����ˡ�⤤�������Ȥ��롣
���ΰ�Ĥ�ʬ�����˸��ۤ����ꡢ��������Ҥ䡢��ԤǸ������г����� ����ʬ�����̯�ʤΤ������ɻ����ۡɤȡɵܸ��ۡɤȤ���ʬ�ब���롣 �Ѥ߾夲��줿�г��ΰ��־���Ѥ��С��ޤ��Ͼ夫�鲿�ʤ����Ѥ��Ф� ��ľ���Ѥ����Τ�ɻ����ۡɤȤ������������鲼���ϡ����ۤ��Ѳ��� ���ʤ���ΤΤ��Ȥǡ���ľ����ʬ��ɱ���ɤȸƤ֡� ����Ȱ�äơ���������־�˸����äƶѰ�ʥ����֤��������Ѥ߾夲��졢 ���־���Ф���ľ�ˤ虜�ȿ������Ƥ��ʤ��Ѥ�����ɵܸ��ۡɤȸ����� �ܸ��ۤȻ����ۤ��Ȥ߹�碌����Τ⤢��Τǡ��쳵�ˤϸ����ʤ����� ����֤��ȸƤФ���Τϡ��ܸ��ۤ�¿����ȿ���֤äƤ������Ѥ��� ����ȿ���֤�ϡ�����Фν��̤�ƨ��������ˤ��Τ褦���Ѥ����� �ͤ��Ф����ȸ����Ƥ��롣��ͤ��ηä��� ���ʤߤˡ�Ǧ���֤����г��ξ���礭�ʲ�����ĥ��Ф��Ƥ����Τ������ |
�Ф��ڤ�Ф��Ϥ������٤��礭�����㤨��
��4����5����3���Ȥ��˶��ڤä� �����ʥޥ��Ȥ���30cm�ֳ����٤� ������Ȥ�������������ˤ����٤� ��ä���˵����ϤĤʤ�����פ���Υ��� ���Ȥϵ�����̵����ʬ�˥С��ʡ���ȤäƲб����Υ�����ƤϤ������� �������Ƽ�줿�ФΥ֥��å���˱��ӹ���� �Ȥϸ��äƤ�160����ۤ��֥��å��� ���ʤ���緿�ȥ�å�����ʤ��ȱ��٤ʤ� ���ӹ�����֥��å���1�̤�ü���Ȥä�ʿ�����ʬ���� ����1�̤���Ȥ���¾���̤��ڤ�Ф� �����̿��Τ褦���ھ�ȸƤФ�뻳�ˤϤ��������ʳ���ܤ� ¸�ߤ��ʤ��ФϤʤ��ۤɤ��Фˤϵ��������� ����Ǥ����ܤ�͢��������ФϤ��Τ����Ȥ����Ф��꤬���Ф���ڤ�Ф���Ƥ��� �����Фε������ϵ������Ω����魯��� ����������������ФȤ���Τ��������ڤˤ��ʤ���Ф����ʤ� �������ܤ�����Ź���¤�����Фϡ�99�����ʤΤ� ���ä����������٤����Ф�Ƥ����ϵ�κ��̵�̤ˤ��뤳�Ȥʤ� �Ȥ��٤����Ȼפ� �̿������ݎĎ�˿�к�η��ȼԽ�ͭ�� |
|
�������ϵ�������С����ޡ����桢ܪ�С������С������Фʤɤ��ꡢ
���Ф�ܪ�Ф����Τ�Τ���ϻ�ѷ����߷��Τ�Τ⤢�롣 ���������ʻ����ή�Ԥ��Ƥ��줾�������㤦�����������ˤ���м���͡��� ��Τλ���ˤϡ�Ļ�ä�Ħ�������ꤷ����Τ�ή�Ԥä��ꤷ���� ����㸫��϶�Ȥ���̾���ǸƤФ����϶�����롣�ʤ��ʤ�����Ƥ�̾���� ���Ҥ��ɤ����������϶�ϡ�������Ҥ���϶���Ϥ�����Τ��� �礭���ˤ�����ͤ��Ѥ��ʤ���Ħ�ä���Τ����Ǥ��뤫�狼��ʤ���礬����Τ����դ�ɬ�פ��� |
|
¢���Фϡ������Ǥϰ����褯�Ȥ�줿�С����ߤϼ������ݸ�뤿��ˡ����������줿�Ȥ����Ǥ����μ�Ǥ��ʤ���
�ܷ��Сʤ᤹�������ˤȸƤФ���Фϡ�ʸ���̤������ޤ���ޤǤޤä��ϴ�ǡ�����Τ�äȤ�����δޤߤ�¿����Τ��ܷ�ȸƤӽ�������Ƥ��롣 ���ܷ��Ф�Ħ�����Ǻ��줿���ޤ���϶�ϡ�̣�襤�����겹���ߤ������Ƥ���뤬��������� �������ˤ����Ϥ�̾�����Ф�¸�ߤ������ޤ��ޤ�������Ѥ����Ƥ����� ���ߤ������Ѥ��뤳�Ȥϡ����ʤ��ʤä����ܤμ������˲����뤳�Ȥ�ľ�ܤĤʤ��äƤ��뤿�ᡢ���Ѥ���ΤϿ��Ťʹͤ��ξ�ǻ��Ѥ��Ƥ����٤������ɤλ��ˤ�����뤳�Ȥ��Ȥϻפ����� |
�Ҥ֤�������϶�βФ�Ȥ⤹�Ȥ������������ڤ����Ʃ�����������äƤ��ơ����Ϥ��������ϳ�����Ϲ�������βФ�Ȥ⤷����Ρ����Ҥ䤪����Ƨ�Фκ��������֤��Ƥ��ȤŤ��ͤ�����Ȥ餷����Τ��������Ť���Τǡ��褯���ޤ�̵����Τ����뤬�����Τ褦���������������ˤ����Ƥ��ޤ������Ф������ܤ��������ˤʤäƤ����Τ���¿�������롣��γ��Ф��礭�����뤳�Ȥ��������뤯���褦�Ȥ����Τ��������Τ��������ˤʤ��Ͽ����Dz���Ƥ��ޤä���Τ���Ⱦ����
���������Ф��礭�������Ф�����夲�Ƥ���Ѥⰵ���ǻ���϶�ȸƤФ�롢�����Фβ��̤����Ǥ������ФȤ��ƤΤ�����Τ�����϶�Ȥ������Ť���ͤ�¿���� �����Ǥ�¢���Ф�Ȥäơ�����϶������Ƥ���Ȥ����⤢�롣 (�̿���ϻ���㸫��϶) |
|
�դߤ��������Ф�°���ơ�Ƨ�Ф���������Ф�ޤޤ�롣
���������������٤θ��ߤ���äƤ��켫�ΤǾ�˾����̤�٤������Τ��� �⤯�ͤ�������ͤ��ƿ�����줿Ƨ�Ф������Ф��⤭�䤹����ư����(�⤤���̤�饤��)���乭��ʤɤθ�������褯�ͤ��ơ����֤����٤����� �㤨���ؾ�ۤɤμ��ڤΤ��Фϡ��ޤ����⤹��Τ�Υ����̤�褦�ˤ������뤳�ȤǤ��μ��ڤ������Ƥ��롣���ڤξ��ϡ��ֶ���̤äƾ����ʲ��ܤ⸫����褦�ˤ���ʤɡ� |
copyright/golem










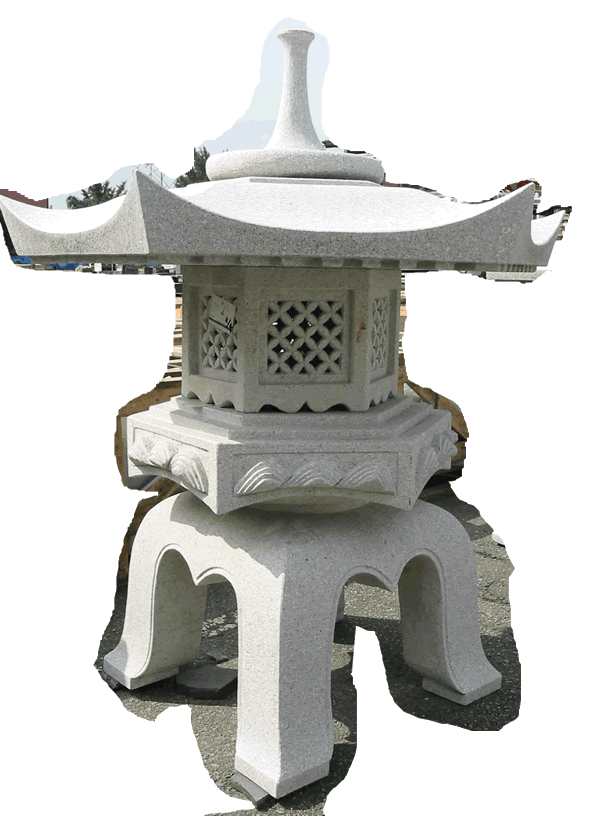



�в��Ȥ����ΤϤ�Ϥ��Τ��餢�äơ��в��Ȥ��������й��Ȥ����ۤ����������⤷��ʤ���
�Ĥޤ��ڤ�ù������繩���Ф����Ф�ù������й��ʤΤǤ��롣
�ڤ�Ʊ�͡���Ź����礬���Ⱥ��������ơ��������й�����ʬ�ʤ�˳�ȯ�������������
ƻ�����ä���ƺ�Ȥ�ϫ�¤����������褹�롣
�Τϡ����ȥ�������ɤʤɤϤʤ��ΤǹŤ���(��־��ˤϤ��ޤ�ù��ˤ�Ŭ��������餫���ų����
�»���ʤɤ�ù��������Ф���϶�ʤɤ��ä���
���Ȱ㤤���߷ޤʤɤϤʤ��ΤǸ�Ƭ������ɮ��Ȥä��»�˽줿���ʤɤˤ��Ƴ�ǧ�����ʤ������Ƥ��ä���Τ��Ȼפ�������Ǥ⤢�����ٻž夬���Ƭ�ˤ����Ʋù����ʤ��Ƚ���夬��
����äƤ��롣
������������й���Ȥ�ʬ�����ơ��Фμ��뻳�Ǻη����Ƥ����й�������ա����դȸƤ�
�����Фӹ���Dzù��в����ž夲�롣���餯�ϡ��۾롢�һ����ۤʤɤ��緿����ʪ��
�ˤ�ꤽ�Τ褦��ʬ��������ΤȻפ��롣
���������ФϤɤ���äƺ���Ƥ��뤫��
��ư�θ��ᵡ���ںﵡ�к��ںﵡ�ˤ�꼫ư�����ǽ�ˤʤꡢ�ù����ѤϿ�Ÿ������
���������������Ϲ���Ǥ������ݤ�������Ģ�����꤭��ȤʤäƤ��롣�ä�
���ϡ�����������̴ؤ�1������ݎĎޤϡ�1.5����ȥ������Ǥ�����ۤȤ�ɤȤʤäƤ��Ƥ��롣
�βù�����Ǥϡ���Ϥ�ʬ������Ƥ�������Ȳù��Ȥ��̡��ΤʤäƤ��롣
�Ǥ��в��ζ�̳���֤Ϥɤ��ʤä����ȸ����ȡ�����ԡ��в����ǹ礻����͢�����Ҥ���ƿް��ꡡ�����Ҥ���ο����в���ǧ�����в�������Ԥ���ƿ��ǹ礻�����в����Ҥؽ�����ȯ��
�����ҡ������ޤ�ù������ȯ����������ù���������ƥ����Ѥߡ�����������
�����̴ء���Φ���������ҲٽФ�ʬ�ۡ���ʬ��Φ�������в����դ��������Ϥ����㼰
�ȤʤäƤ��롣
��ƿޤ�ɬ�פʤΤϡ����ϤȰ���Ԥ��в��Ⱦ��ҤȲù����줬���줷����Τ�����뤿��
ɬ�פʤΤ���
95��ʾ�Ͼ��Ҥ���ƿޤ������Ƥ��롣�ʤ��в������̤������ʤ����ȸ����ȡ�ñ�ˤ��ε��Ѥ�
�ʤ��ΤǤ��롣
�����в��ϲ��뤫�ȸ����ȡ����Ͼ���(�ܵ�)�μ��������Ҥ��Ͱ���ȯ�������ʤμ��դ���
�Ȥʤ롣
�����������
�в��Ȥ��ǹ礻�Ǥϡ��ɤΤ褦�ʻܹ����Ѥ���äƤ��뤫����ɤ���
�㤨�С��ѿ��ȿ̤ι�ˡ���������Ƥ��뤫������ˡ�������������Ǥ��Ƥ��뤫��
���ù����ˤĤ��ƤϤɤ������ʤɤǤ��롣
ʩ���ط������뤤�в��ʤɤȸ����Ƥ��Ƥ⺣�Ϥɤ����Ǥ���Ƥ������ʤΤ���
�ޤ��ϡ��ܹ����ѤǤ��롣
���ä˴��ù����ϡ����ڵ��ѼԤ��μ���ɬ�פʤ��ᡢ�����ø��ʻ������Ф��ѿ̻ܹ�
���Ƥ�̵��̣�ʤ��Ȥ�¿����������Τ�ʤ��в���¿���Τ����դ�ɬ�פ���
����������ʤ��ʤ��Ƥ��в��Ϥ���ΤǤ��롣
�������϶��ʩ���ط����ΤäƤ���С����ڵ��Ѥʤɤʤ��Ƥ�Ϥ��餫�����Ȥ����뤫�鵤��
�Ĥ��ʤ���Ф����ʤ���
�������������϶�ʤɤ���������ꤹ��С���������Ҳ�⤷�Ƥ�館�롣��������ξҲ�
�Ȥʤ�С��ɲȤ�����ä����Ǥ뤳�Ȥ����ʤ���
�����ϡ������ͥåȸ����Ǥ�����Ǥ�ʩ���ط����������뤳�ȤϤǤ��뤬������μ¼�Ū��
�ܹ��ˤĤ��ƤϾ���ϤĤ���ʤ����ɤ���в��ʤΤ��Ϥ狼��ʤ��ΤǤ��롣
�����㡢�ɤ���äƤ��Τ褷�������ǧ���뤫�ȸ����ȡ��ޤ����ù��������ο��̤��餦�ΤǤ��롣
��ʬ�ΤȤ����˹�碌�����ù����ײ����������Ǥ���й�ʤ���
�����Ҥϸ��ϤˤϹԤ��ʤ��Τǡ����ä˴ؤ��ƤϿ��̤�Ƥ���ʤ��Τ����⤷���Ҥ�������
��Τʤ鸽�Ϥ˴ط��ʤ�������Ƥ���Ϥ�����
������ۤ��礭�����ѤǤϤʤ��Τ��礲����¬�̤�ɬ�פʤ����鸫�Ѥ���˻��ä�����Ϥ�����
���Ǥ⤫��Ǥ�Ʊ���ˤ���Ф����ȻפäƤ��ڤ���Τ������դǤ��롣
�������Ǥ��ʤ����������٤ε��Ѥ��������ʤ��в��ǡ����褿����Ϥ⤷��������¤�����
����ʤ�����ǯ�夫�ˤɤ��ʤ뤫�ϡ����鷺���Τ줿���ȤȤʤ롣