朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報
12.五百川峡谷エリア
明治8年(1875)経費のすべてを地元で負担し、最上川本流で初めての橋「明鏡橋」が架けられました。その後、洪水等で流失が相次ぎますが、昭和12年(1936)ついにコンクリート製のアーチ橋が完成しました。これが「旧明鏡橋」です。六代目明鏡橋が完成するまで、69年間にわたり国道を行き交う人々の往来を支えてきました。平成18年、優れたデザインを理由に選奨土木遺産に指定。橋の写真家平野暉雄氏(京都在住)は「開腹型アーチ橋の中では日本一心和む橋」と絶賛されました。
※撮影/高橋茉莉さん(仙台市) →アクセスマップはこちら 平野暉雄さんのお話 →心なごむ明鏡橋を見つめて 菅井敏夫さん、志藤正雄さんのお話 →旧明鏡橋の思い出 志藤正雄さんのお話 →夏の芋煮会“えるか汁” 志藤三代子さんのお話 →すいとん入りえるか汁 佐久間 淳さんのお話 →明鏡橋の思い出 菅井敏夫さんのお話 →明鏡橋物語全12話(PC) →書籍『明鏡橋物語』について →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |
五百川三十三観音第32番札所。
→五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 →アクセスマップはこちら ※分かりにくい場所です。事前にエコミュージアムルームまでお問い合わせ下さい。 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |
→用のはげ“明神断崖”と周辺めぐり(PC)平成19年(2008)
→最上川フットパスあさひ見学会(PC)平成20年(2009) →最上川フットパスあさひ見学会2(PC)平成20年(2009) →見学会情報はこちら →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |
All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

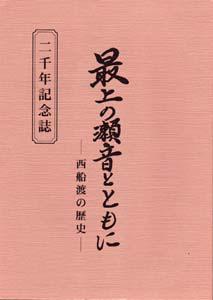



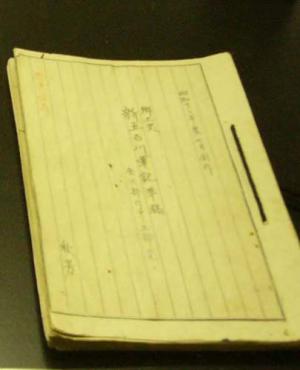

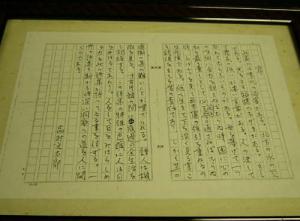
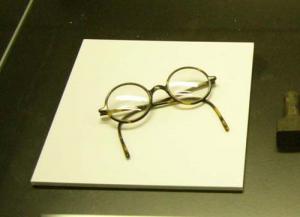








編集・発行/西船渡区史編纂委員会 発行日/平成6年3月31日
※町立図書館で借りられます。